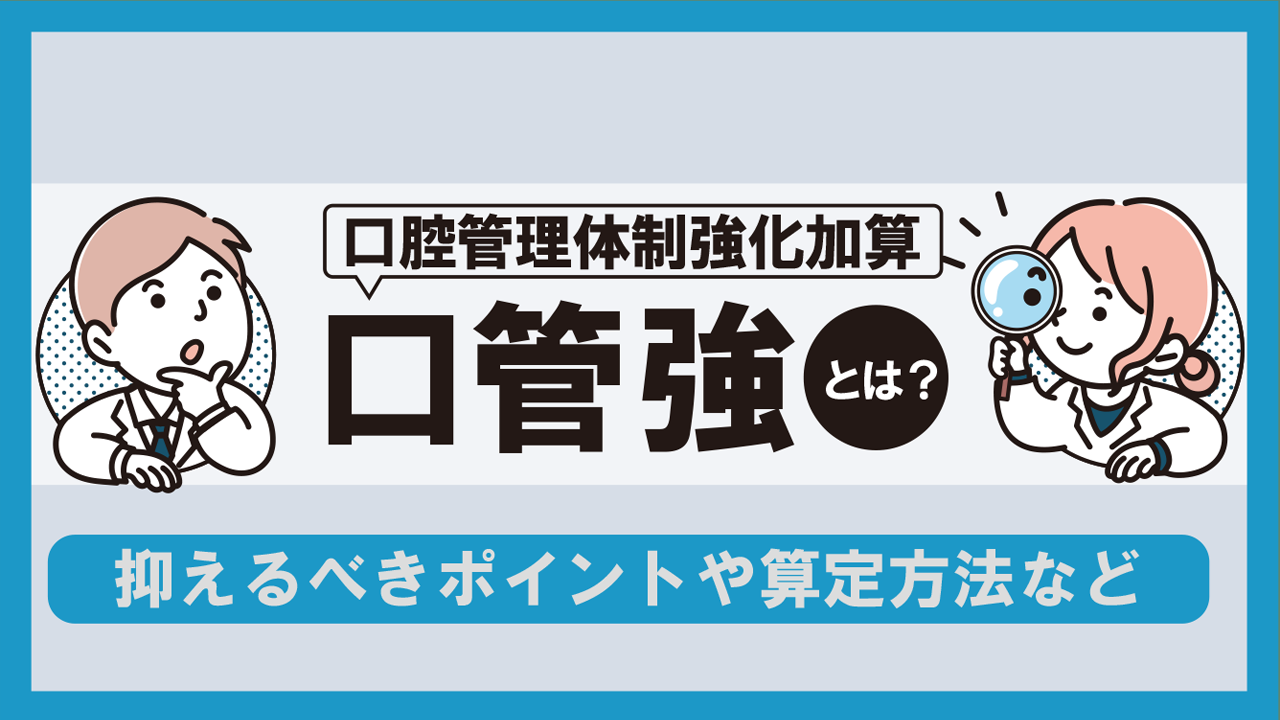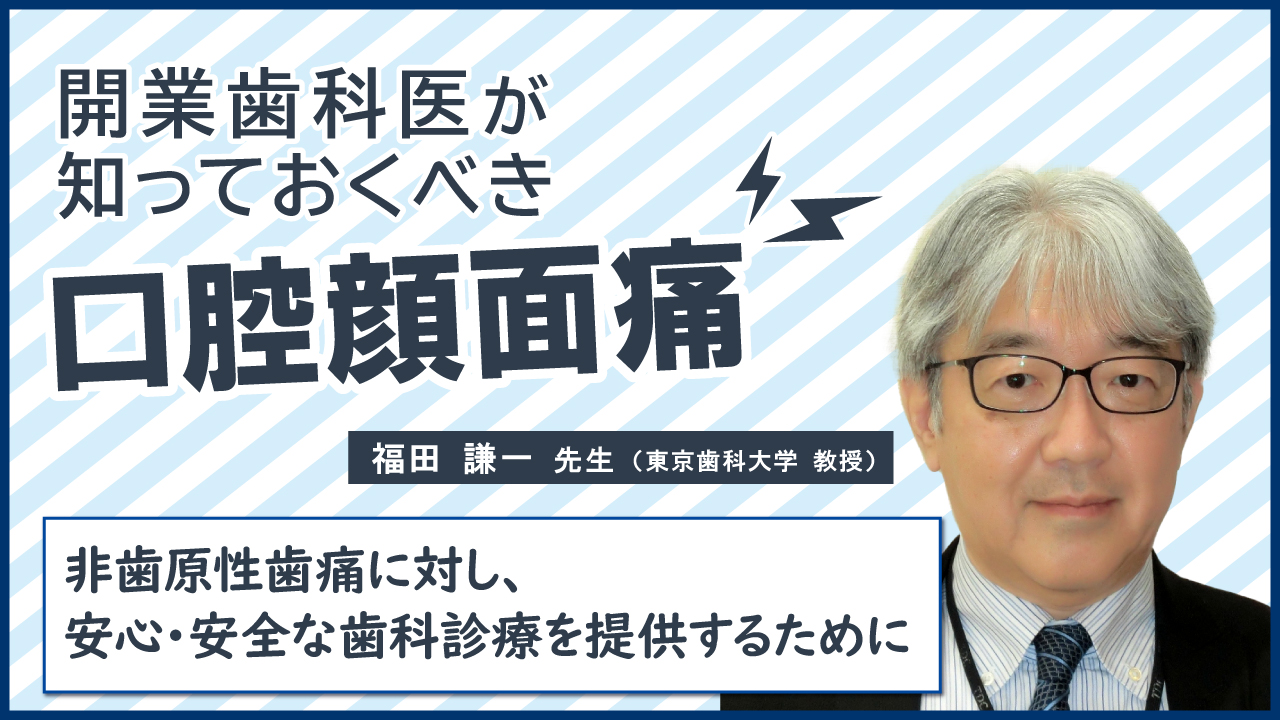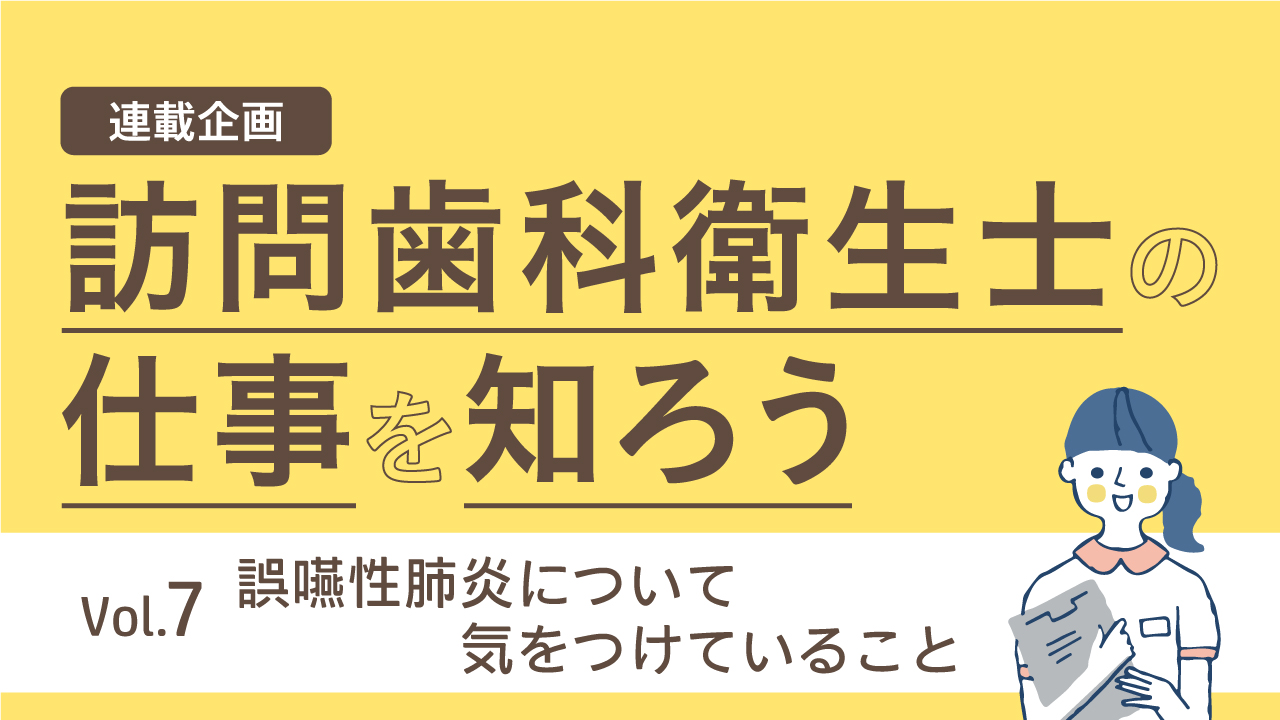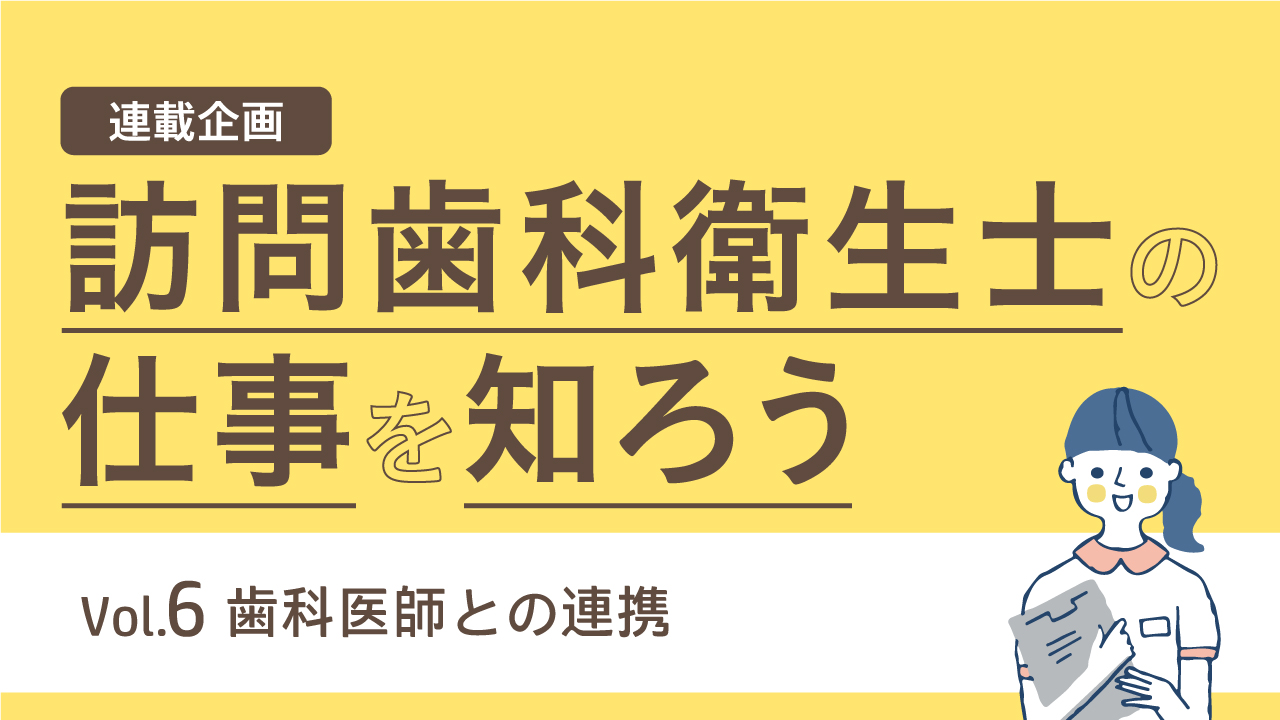【インタビュー】根拠ある感染対策を目指す 何を継続し、何をなくすか
インタビュー
2022/11/14

大毛 宏喜 氏
広島大学病院感染症科教授
■感染者の存在を前提に
──コロナ感染対策では大学病院なみの取り組みをしている歯科医院も多々見られました。感染対策でのコロナとインフルエンザなどとの対策で違いはあるのですか。
基本は同じです。ただ、感染対策が算定可能な医科はスタッフや職員に対し、院内感染対策やトレーニング、研修会などを積極的に実施しましたが、医療機関においてクラスターが多く発生しました。 これに対し歯科は、患者さんが必ずマスクを外すという特殊な治療環境にあるため、医科よりもリスクの高い感染対策が求められましたが、歯科医療機関においてクラスターが発生したという事例報告はあまり聞かれませんでした。 その明確な理由を示唆せよといわれると難しい話になりますが、歯科の関係者の方はマスクの着用や個人防護具の適切な使い方について普段からよくトレーニングされていると推察されます。
──コロナ禍において国民の強い要求に応えるまで、歯科の感染対策への取り組みも希薄だったと思うのですが、科学的根拠のある感染対策というのはあるのですか。
予防という観点からいえば飛沫感染が中心になるので、不織布のマスクで鼻と口を正しく覆うというのはエビデンス的にとても大きな効果があったと言えます。そして、エアロゾルが充満する一定空間では感染リスクが上がるので、室内を換気するというのがとても大切です。科学的根拠のある感染対策といえるのはこの二つぐらいだといえます。
──確かに室内換気についての歯科医療機関の取り組みは神経質すぎると思えるほどに取り組むクリニックが多く見られました。
歯科はドリルを使用する医療行為です。エアロゾルが充満する空間というハイリスクの中なので換気には神経を使ったのではないでしょうか。それが要因かどうかはっきりしたことはいえませんが、歯科医院でのクラスターが少なかったのは良かったのではないでしょうか。
♦♦♦
──コロナの新規感染者数は減ったとはいえ、その数はいまだに万の数で推移しており、国民にコロナ感染での慣れを感じます。感染対策で継続すべきものと、縮小してもよいものがあるのでしょうか。
患者さんもそれぞれです。非常に神経質な人もいれば、楽観視している人もいます。最初は誰もがすごく心配していましたが、2年半の間にその幅は徐々に広がってきています。昨今は楽観視する傾向の人が増えつつありますが、逆にものすごくナーバスな人もいます。 医療機関もお客様商売です。その意味では非常にナーバスなところをカバーして取り組み、継続していくというのが、今の日本の文化だと思います。そうすると苦情の相手をするよりは入り口での検温やアルコール消毒などは、ポーズとして続けていくのも効率的な考えといえます。 クリニックの先生方は不要と思えるものを省いていけばいいのですが、そのスタンスとしては、世の中の空気を睨みながら縮小していくという考えが、これからは特に大事になってくると思います。
■医院機能維持の対策図る
──コロナ感染対策で不必要と考えられるものは。
入り口での検温、窓口のアクリル板、待合室の椅子に×印をつけて人と人の間隔を空ける、トレイを介してお金のやり取りをする、トイレのジェットタオルをストップするといった行為について、広大病院では2年半前から一つもやっていません。 それと入院患者さんとの面会について、いまだに多くの病院が止めているようですが、広大病院では患者さんとの面会は可能です。それらはコロナ感染対策において無意味だと分かっていたので、最初からやりませんでした。
──それが無意味だという科学的根拠はあるのですか。
それに意味があるという科学的根拠が全くなかったのでやらなかったわけです。
♦♦♦
──1月27日に行われるセミナーのタイトルは「根拠のある感染対策を目指して」とありますが、具体的にはどのような話になるのですか。
これからの感染対策で、「これはいる」「これはいらない」という話をしようと思っています。しかし、いらないからといって、すぐに止めていいというわけではありません。コロナ感染に対してナーバスな患者さんがいる限り、バッサリと変えていいというものではないからです。 要するに科学的根拠のある対策と、科学的根拠はないけれどもそれがないと心配という患者さんの「心配対策」としてやる二つの対策に分けて考えましょうという話です。 医療従事者はそれを把握しておき、自分なりに問題を整理しておき、表面的には継続しながら、社会の空気を睨んでいつなくしていいのかを判断する必要があります。
──海外ではマスクをしている人が少ないのですが、日本人はほぼ全てといっていいほどマスクをしています。
狭い空間でマスクを外して飲食をすると、陽性患者が一人いれば他の人に感染しますが、屋外でのマスクは必要ありません。 屋外でバーベキューでもしながら皆でコンロを囲んでワイワイガヤガヤ飲食をしていれば、そこに一人でも陽性者がいれば感染のリスクは高くなりますが、そうした特殊な事情でもない限り、屋外での感染リスクはゼロではないけれども低いと言えます。 インフルエンザでゼロというのを聞いたことがないのと同じで、新規感染者がゼロになるとは国も言っていません。
──ゼロ政策は、国民としては当然のような気がしますが。
感染症でゼロはないです。患者さんもスタッフも、歯科医師の方々も感染しているかもしれないとの前提で業務をし、陽性者が混じっていても大丈夫という対応の発想が大事なのです。 広大病院では職員にも患者さんにも陽性者がいるとの前提で、陽性者を院内に広げないため、医師にもスタッフにもどういう体制を取って業務にあたるかを考えてくれと話しています。 入院患者さんだけで広大病院には毎日新たに80~100人がきます。他の大学では陽性者は一人たりとも入れないぞとの意気込みで正面玄関に関所を設けて100人全員を検査していますが、バックドアからは無検査で広大職員3千人がフリーで入ってきています。100人だけを一生懸命検査することに意味があるとは思えません。一人たりとも入れないということが本当に可能なのかという話です。
──「根拠ある感染対策を目指して」というのは、新規感染者がゼロにならないとの前提に立った上で、さて、どうするかという話と捉えて良いのでしょうか。
そうです。ゼロにならない前提で歯科クリニックの機能を確実に維持するかとということです。大学病院の場合は、大学病院が担うべき機能があります。クリニックも含めた医療機関は、他では替えがきかない機能を持っています。 これをどうやって維持するのかを考えると、今までのように絶対にゼロ・ゼロ・ゼロでは不可能です。考え方を180度変えていくしかないのです。 さらに、ゼロであるべきと考える患者さんもいるので、これからのコロナ感染対策はその前提に立って幅広く考えて取り組む必要があるのです。
根拠のある感染対策を目指して
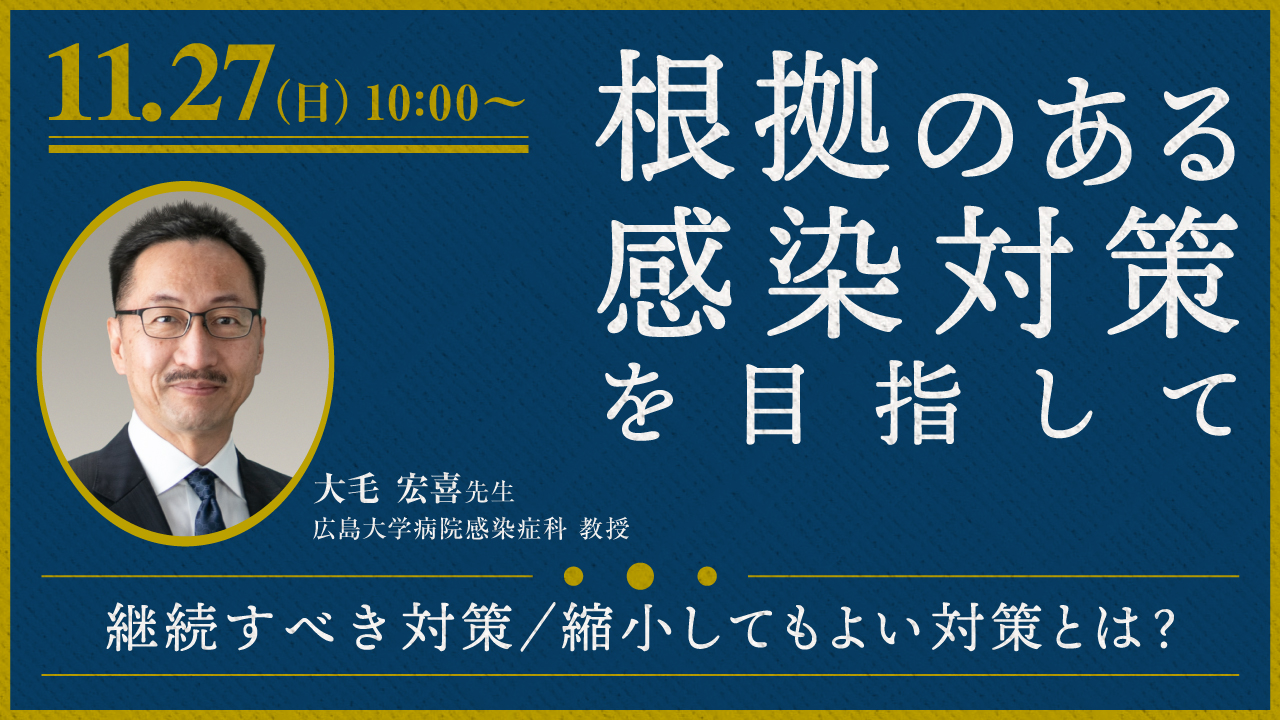
※日本歯科新聞2022年11月1日号掲載記事
この記事の関連記事

【インタビュー】根拠ある感染対策を目指す 何を継続し、何をなくすか
大毛 宏喜 氏 広島大学病院感染症科教授 新型コロナウイル…
大毛 宏喜 氏 広島大学病院感染症科教授 新型コロナウイル…
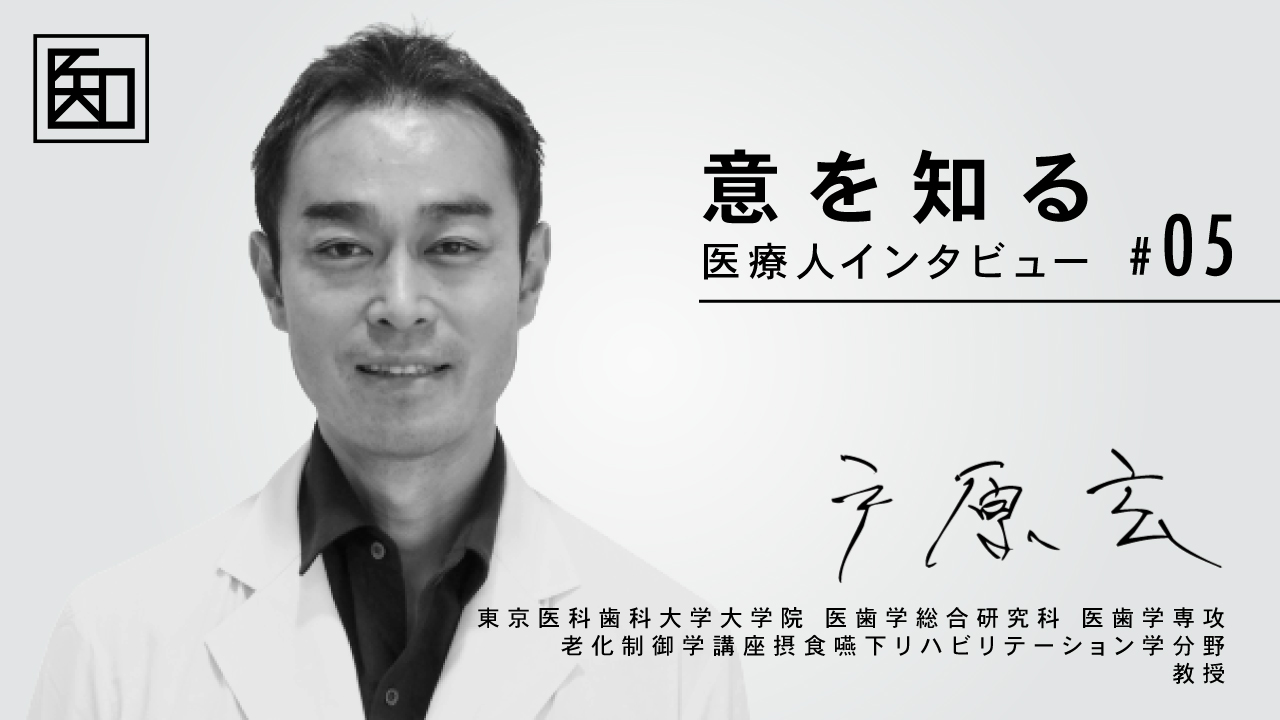
【インタビュー】問われる摂食嚥下障害への対応 /「人生100年時代」の歯科医療
戸原 玄 氏 東京医科歯科大学大学院 教授 「人生100年…
戸原 玄 氏 東京医科歯科大学大学院 教授 「人生100年…
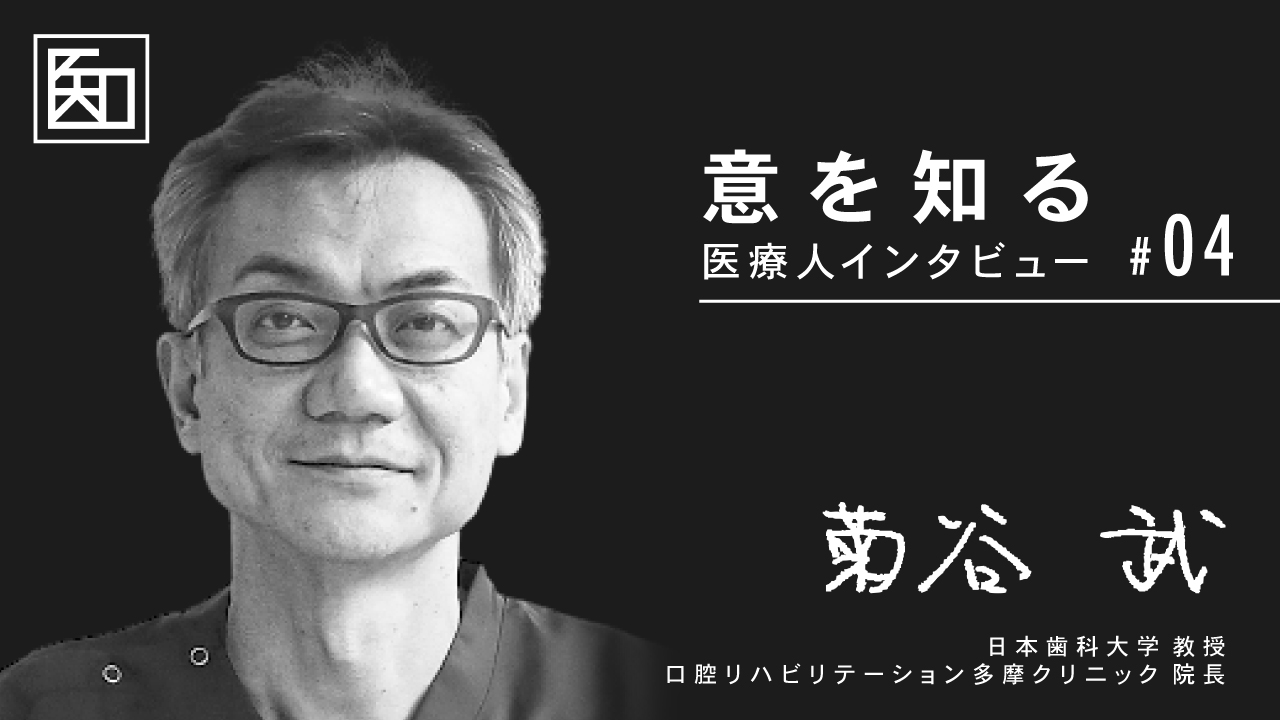
【インタビュー】避けられぬ歯科訪問診療(第2回)
歯科医師 菊谷 武 先生・日本歯科大学 教授・口腔リハビリテ…
歯科医師 菊谷 武 先生・日本歯科大学 教授・口腔リハビリテ…
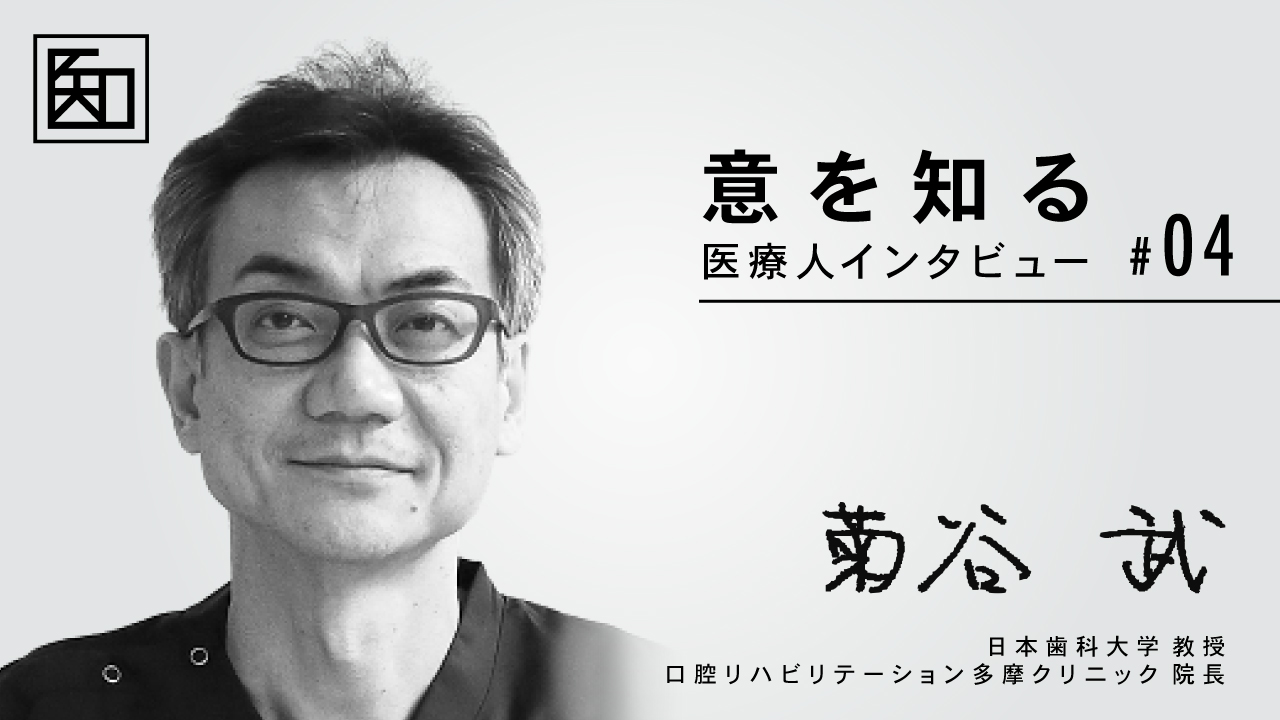
【インタビュー】避けられぬ歯科訪問診療(第1回)
歯科医師 菊谷 武 先生・日本歯科大学 教授・口腔リハビリテ…
歯科医師 菊谷 武 先生・日本歯科大学 教授・口腔リハビリテ…
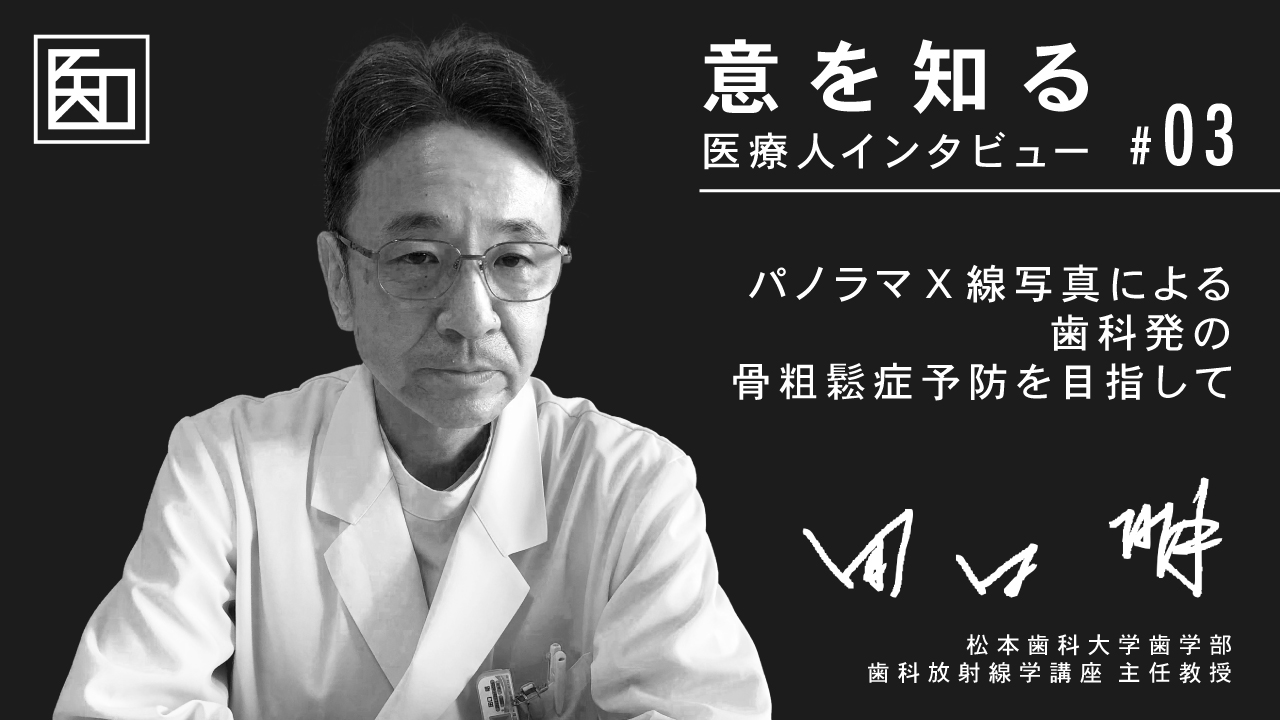
【インタビュー】骨粗鬆症と歯科との関係(第2回)
歯科医師 田口明 先生・松本歯科大学歯学部歯科放射線学講座 …
歯科医師 田口明 先生・松本歯科大学歯学部歯科放射線学講座 …
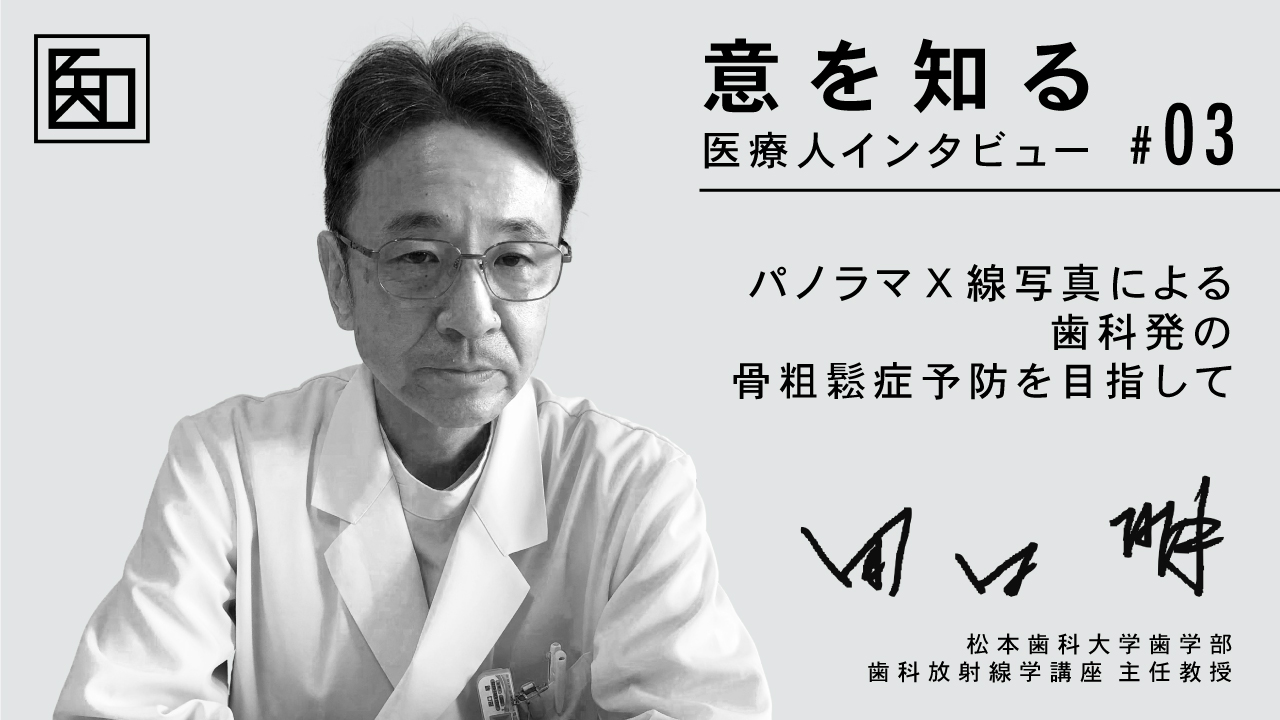
【インタビュー】骨粗鬆症と歯科との関係(第1回)
歯科医師 田口明 先生・松本歯科大学歯学部歯科放射線学講座 …
歯科医師 田口明 先生・松本歯科大学歯学部歯科放射線学講座 …
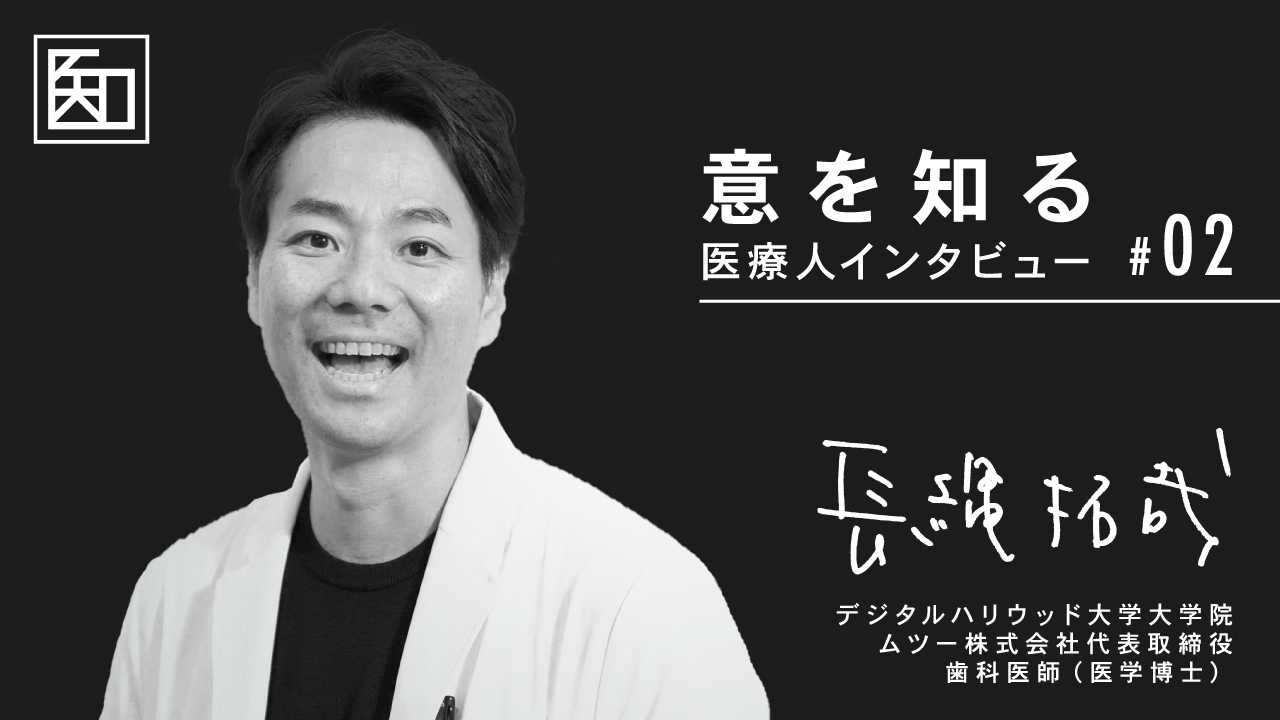
【インタビュー】現代美術、オンライン診療、BOC 医療/+αで社会課題の解決を目指す(第2回)
歯科医師 長縄拓哉 先生 歯科医師(医学博士) デジタルハリ…
歯科医師 長縄拓哉 先生 歯科医師(医学博士) デジタルハリ…
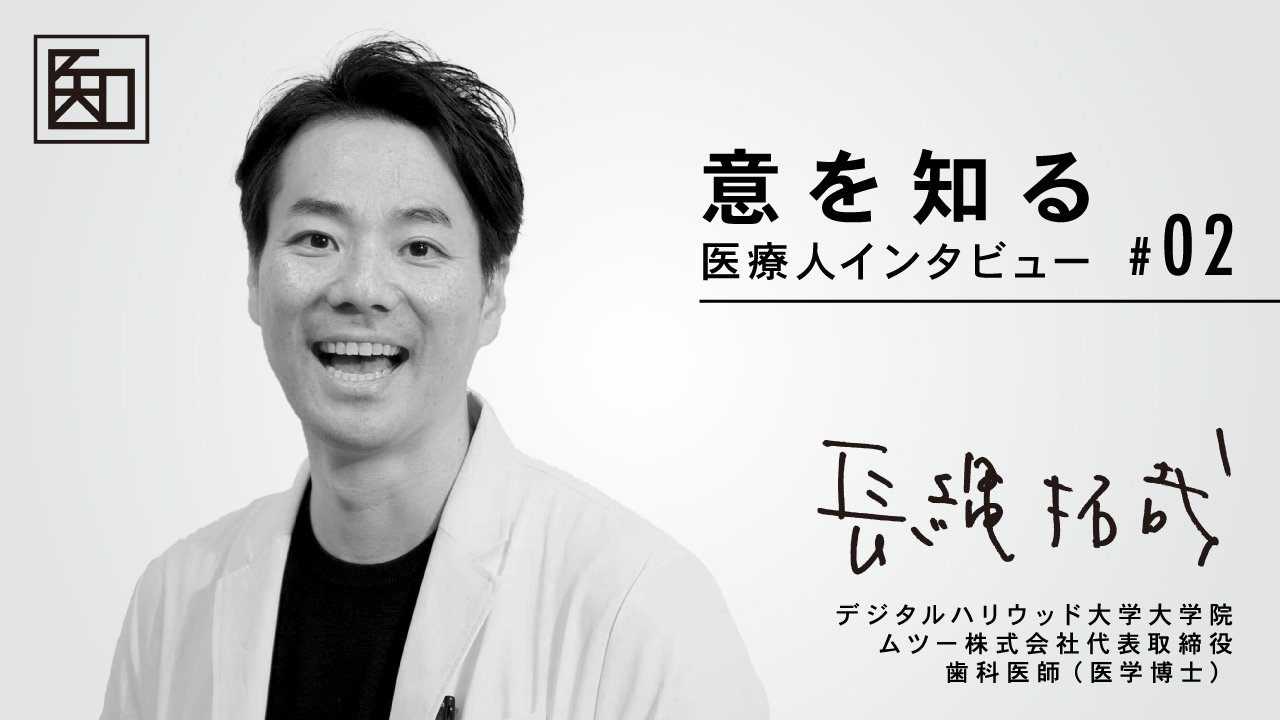
【インタビュー】現代美術、オンライン診療、BOC 医療/+αで社会課題の解決を目指す(第1回)
歯科医師 長縄拓哉 先生 歯科医師(医学博士) デジタルハリ…
歯科医師 長縄拓哉 先生 歯科医師(医学博士) デジタルハリ…