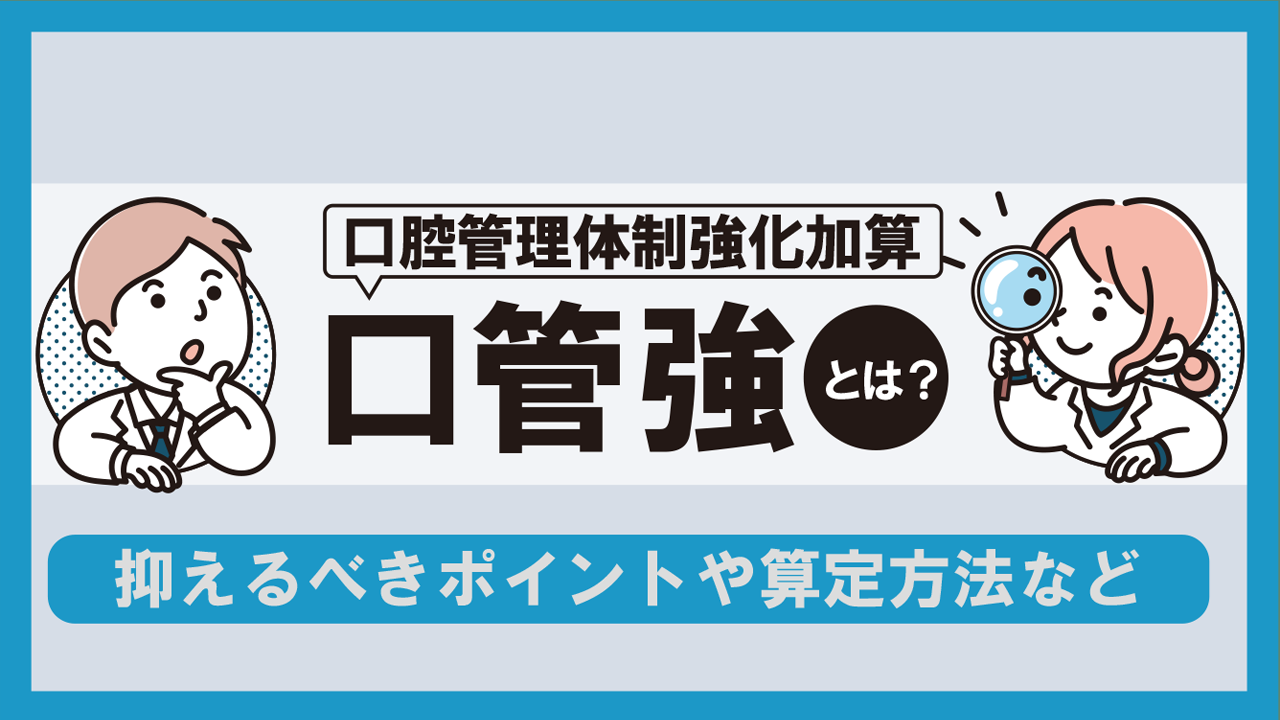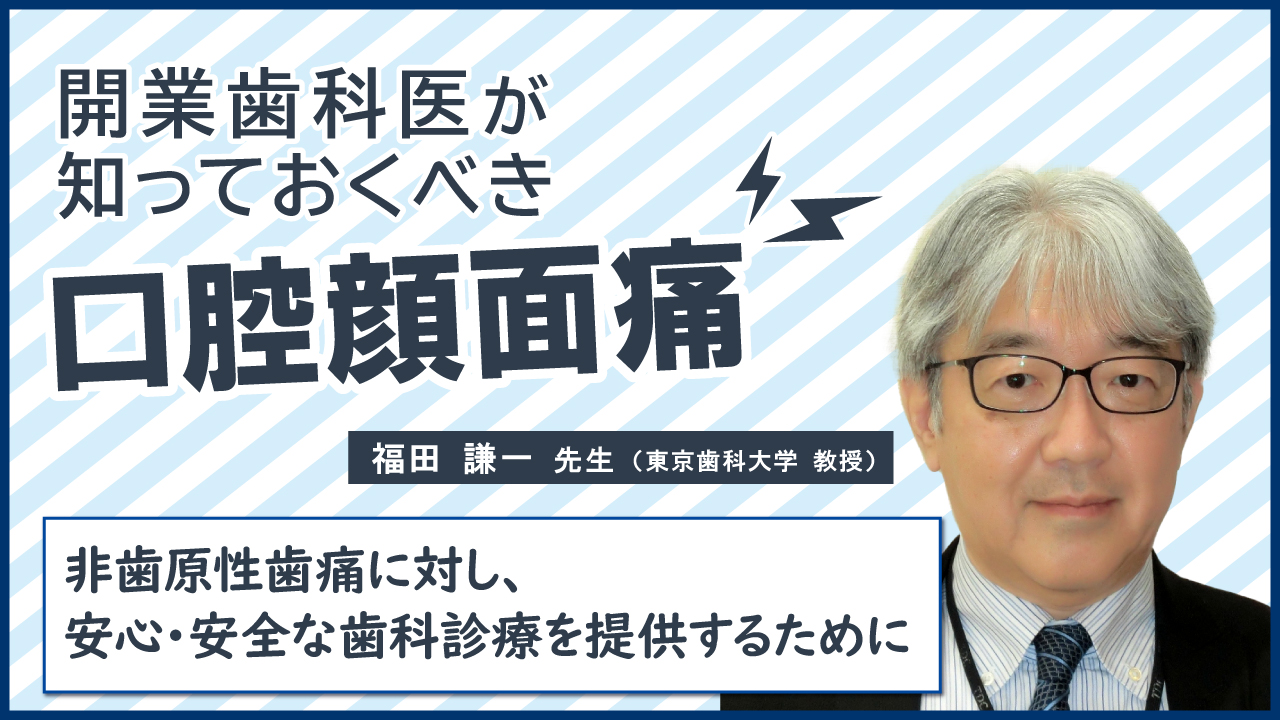訪問歯科衛生士の仕事を知ろう ~Vol.7 誤嚥性肺炎について気を付けていること ~
歯科訪問診療
2023/11/30
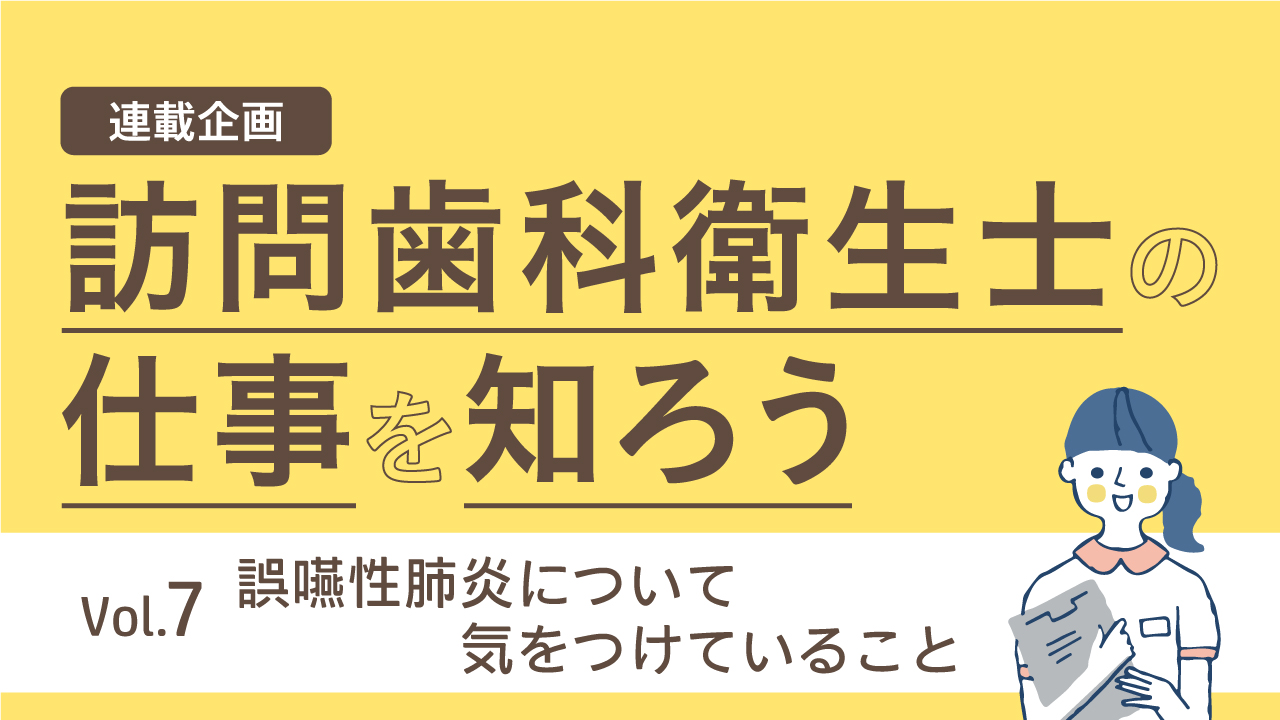
Vol.7 誤嚥性肺炎について気を付けていること
歯科衛生士16年目、歯科訪問診療7年目のSATOです。歯科訪問診療の現場では、外来診療と異なる部分がたくさんあります。これから訪問診療に取り組まれる歯科衛生士さんや、新たに訪問診療の扉を叩こうと考えている歯科衛生士のみなさまに、実際の訪問診療の業務はどのようなものなのかをお伝えいたします。
口腔ケアの目的のひとつに、誤嚥性肺炎防止
私が患者さんのところにお伺いする時は「歯科衛生士の単独訪問」という形でお伺いしています。歯科医師が訪問する場合と違い、歯科衛生士は治療行為はできません。そのため、ほとんどの時間を、口腔ケアに当てています。もちろん、歯の脱落や義歯の破損などがないかをチェックし、歯科医師に繋げるという役割もあります。そして、歯科衛生士が口腔ケアを行う目的のひとつに、誤嚥性肺炎の防止があります。
こんな方は注意と感じるケース
口腔ケアを行う上で「あ、この方は今、誤嚥性肺炎に注意だな」と思うケースがあります。 もちろん、どの患者さんも注意が必要であることに変わりはないのですが、かかりやすくなっている状態として、気を付けているケースがいくつかあります。
◆歯肉付近に食物残渣が多くなってきた方
歯肉と口腔粘膜の間に食物残渣が増えて来たという方には注意が必要です。元々たまりやすい方も注意が必要ですが、「最近増えたな」と感じる方は、特に注意しています。何らかの理由で感覚が鈍っている、筋力が衰えているなどの理由が考えられます。患者さん自身で清掃しきれない場合は、ご家族の助けが必要と感じるケースもあります。
◆初めてケアをする方
特にエビデンスはありませんが、私の経験則上、初めてケアに入る方も注意が必要だと思うことが多いです。 口腔内にたまっていた汚れが、ブラッシングなどを行うことによって口腔内に再度散るためです。二、三回お伺いして「きれいな状態が保ててるな」と確認できるまでは油断しないようにしています。うがいができない方は特に注意しています。これは訪問歯科を始めた際に先輩歯科衛生士よりアドバイスしてもらったものです。先輩も自分の経験からそのように感じていたようでした。
◆眠っている時間が突然増えた方
特にご家族にお伝えした方が良いと考える注意点は、眠っている時間が突然増えた方です。 お伺いしている患者さんの中にも「あれっ、いつもこの時間は起きていらっしゃるはずなのに……」と思うことが二週ほど続き、誤嚥性肺炎で入院されたという方が何名かいらっしゃいました。細菌が発熱に至らない程度の炎症を起こし体が疲れていたのか、免疫力が何らかの理由で低下したことで不調をきたし、眠っている時間が増えるのか、原因ははっきりとは分かりません。もちろんご家族を不安にさせたくはないのですが、気を付けて体温を計っていた結果、早く変化に気づけたということもあるので「あまりご不安に思うことはないのですが」と前置きしてからお伝えするようにしています。
◆梅雨の時期
夏や冬の方が体力を使いそうに思いますが、患者さんのところにお伺いしていると、とにかく注意すべきは梅雨!!と感じることが多くあります。湿気が出始めることによって痰が絡み、喀出できないことから風邪のような症状になるのか、湿気自体が何らかの全身状態に影響を及ぼしているのかは分かりませんが、この時期は不調になる方が非常に多い印象です。あくまで私の経験則に過ぎませんが、梅雨の時期は拝見している患者さんが全員不調というケースまでありました。ご家族も痰の吸引の回数が増えてお疲れのことが多いため、気を付けてフォローするようにしています。
ケアをしても誤嚥性肺炎を防げなかった時
ケアをしていても患者さんが誤嚥性肺炎にかかってしまうことはあります。これにはかなりショックを受けます。しかし、口腔内の細菌を0にすることはできないため、誤嚥性肺炎を0にすることもできません。また、お伺いの回数は保険診療の範囲内では、歯科衛生士の口腔ケアは月4回までと決められています。もう少し伺えればいいなと思うことがあっても、自費診療をご希望されなければそれ以上増やせないのも実情です。患者さんが誤嚥性肺炎にかかってしまった時は、まずは先輩歯科衛生士に相談するようにしています。
歯科衛生士が単独でお伺いする場合、メインの診療内容は口腔ケアになります。訪問歯科診療における口腔ケアの目的のひとつに、誤嚥性肺炎の防止があると私は考えています。誤嚥性肺炎のリスクが上がっているケースは、エビデンスのない経験則も含めて、いくつかのパターンに分けられると感じています。その方の変化、口腔内の状態、全身状態、気候なども含めて考え、より患者さんの生活に密着した誤嚥性肺炎の防止に努めています。
この記事の関連記事
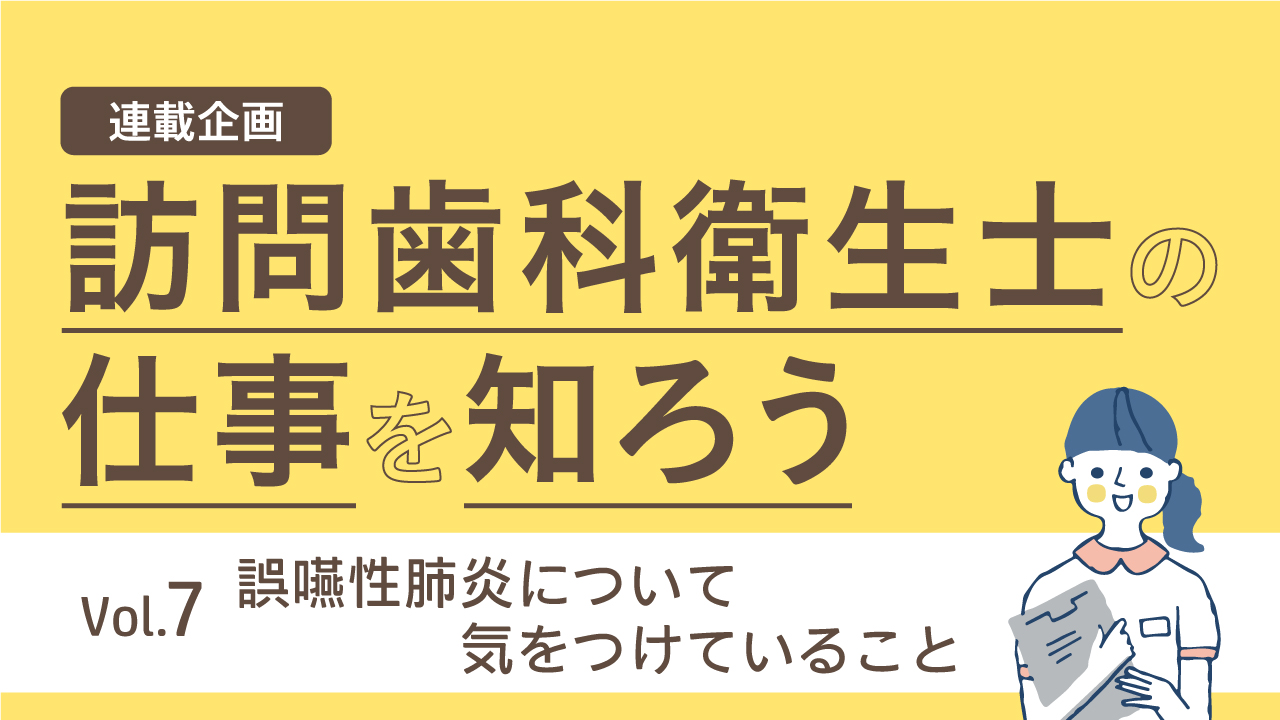
訪問歯科衛生士の仕事を知ろう ~Vol.7 誤嚥性肺炎について気を付けていること ~
Vol.7 誤嚥性肺炎について気を付けていること 歯科衛生…
Vol.7 誤嚥性肺炎について気を付けていること 歯科衛生…
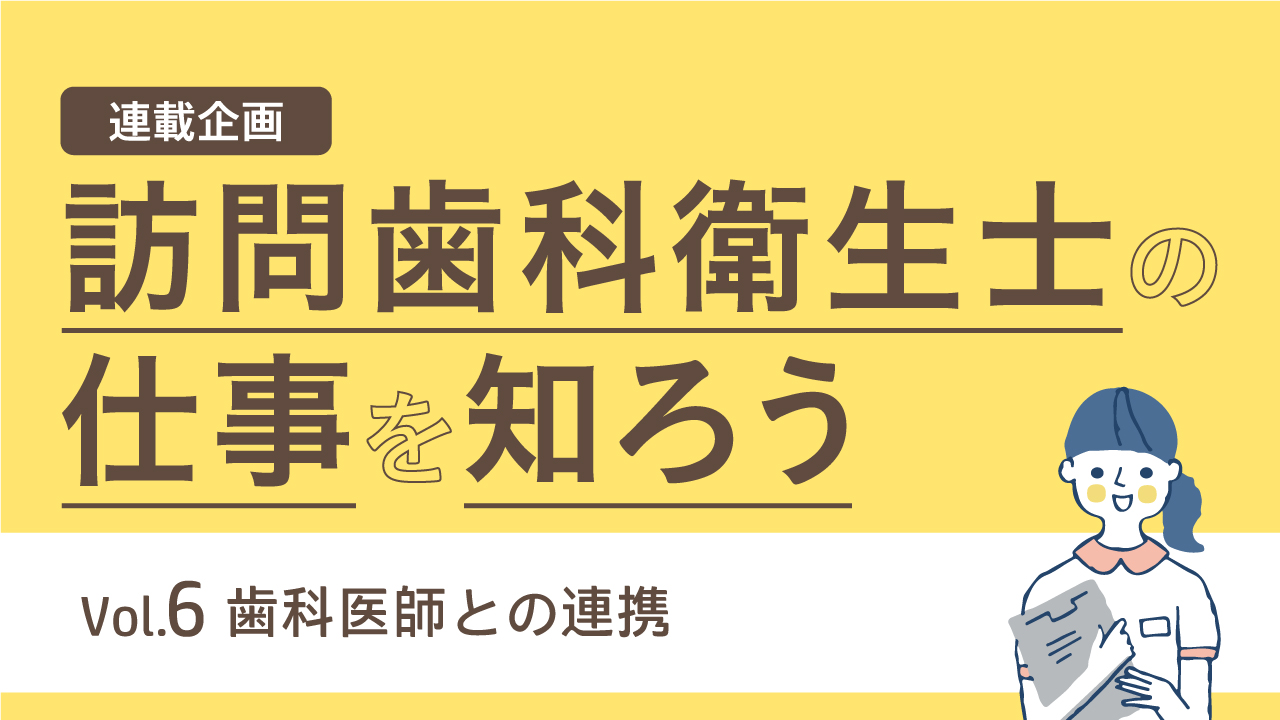
訪問歯科衛生士の仕事を知ろう ~Vol.6 歯科医師との連携 ~
Vol.6 歯科医師との連携 歯科衛生士16年目、歯科訪問…
Vol.6 歯科医師との連携 歯科衛生士16年目、歯科訪問…
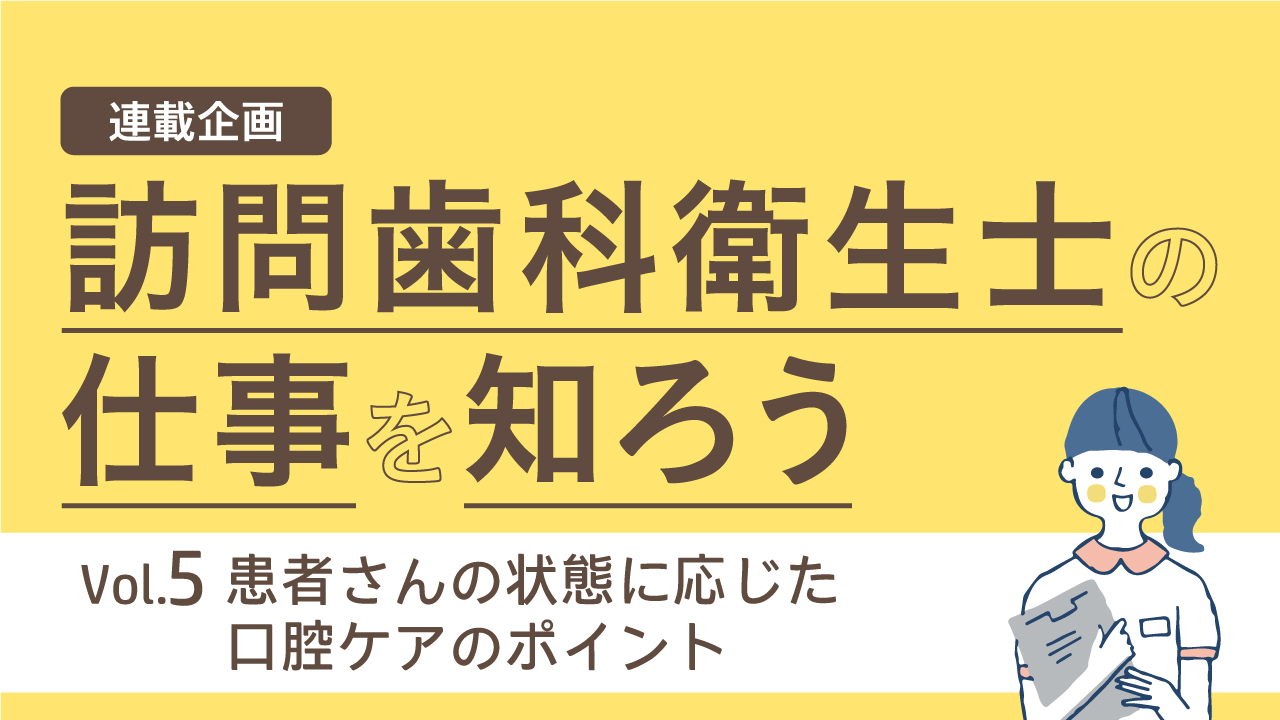
訪問歯科衛生士の仕事を知ろう ~Vol.5 患者さんの状態に応じた口腔ケアのポイント~
Vol.5 患者さんの状態に応じた口腔ケアのポイント 歯科…
Vol.5 患者さんの状態に応じた口腔ケアのポイント 歯科…
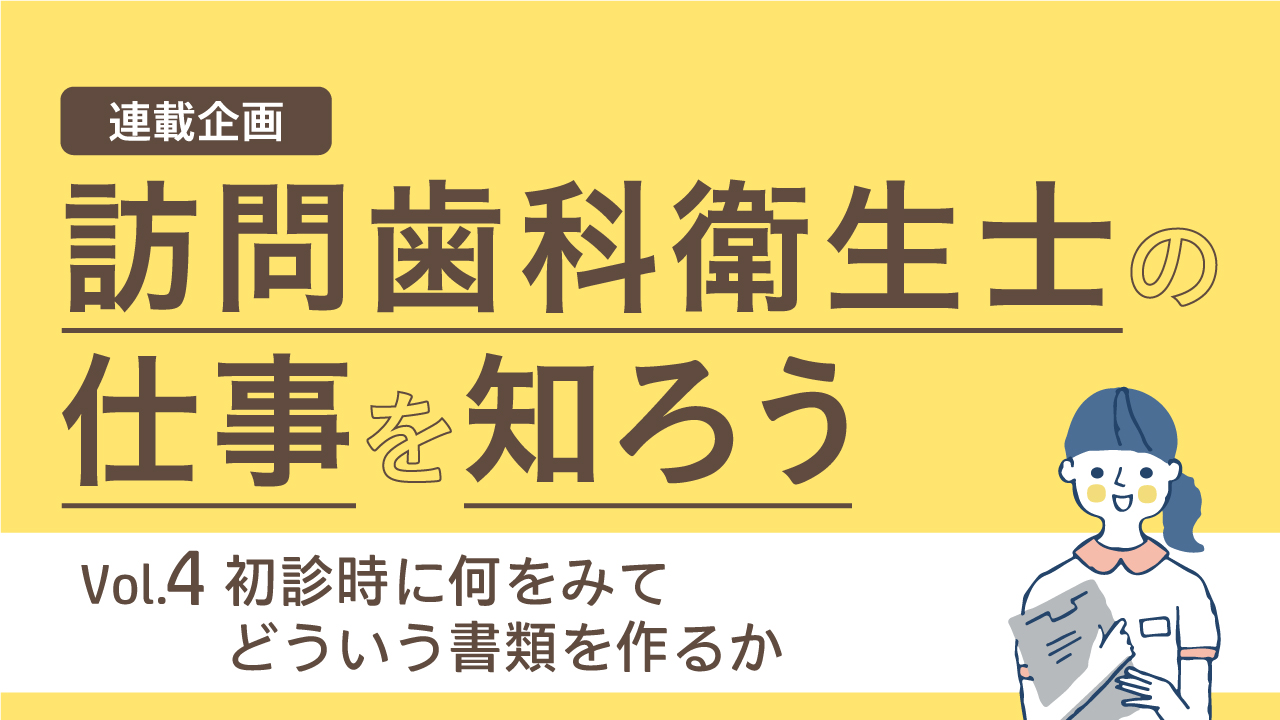
訪問歯科衛生士の仕事を知ろう ~Vol.4 初診時に何をみてどういう書類を作るか~
Vol.4 初診時に何をみてどういう書類を作るか 歯科衛生…
Vol.4 初診時に何をみてどういう書類を作るか 歯科衛生…
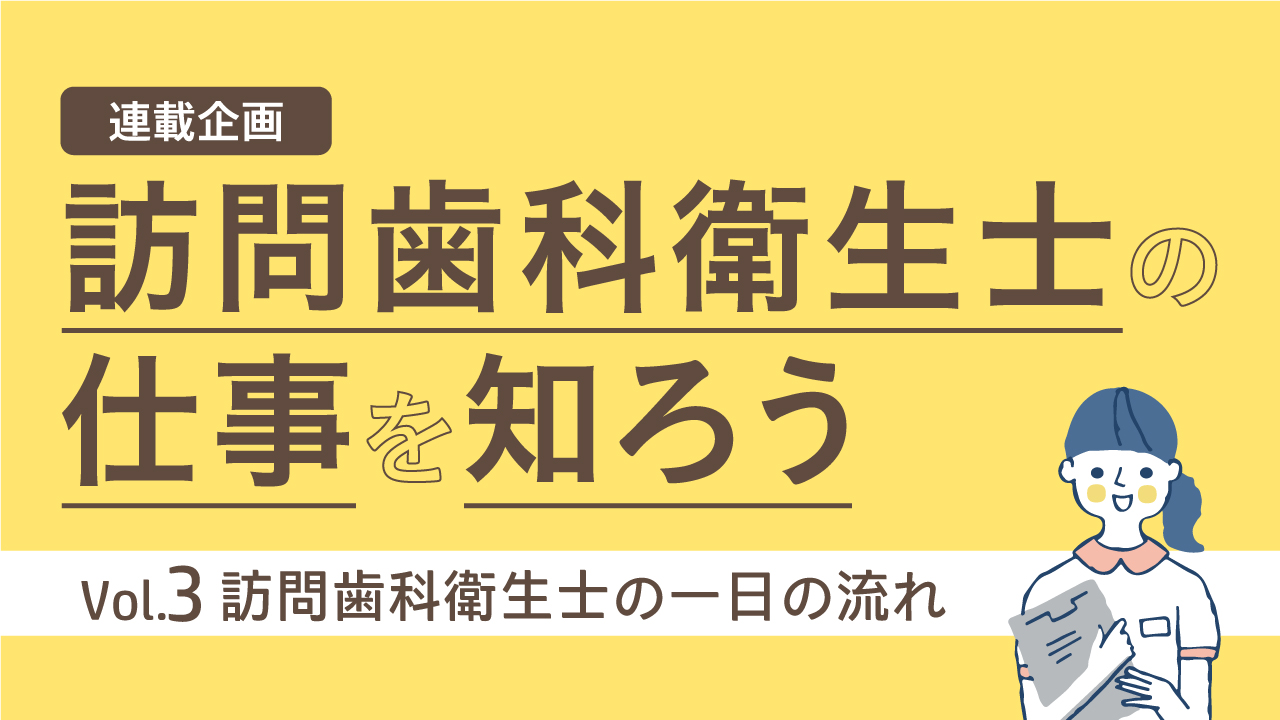
訪問歯科衛生士の仕事を知ろう ~Vol.3 訪問歯科衛生士の一日の流れ~
Vol.3 訪問歯科衛生士の一日の流れ 歯科衛生士16年目…
Vol.3 訪問歯科衛生士の一日の流れ 歯科衛生士16年目…
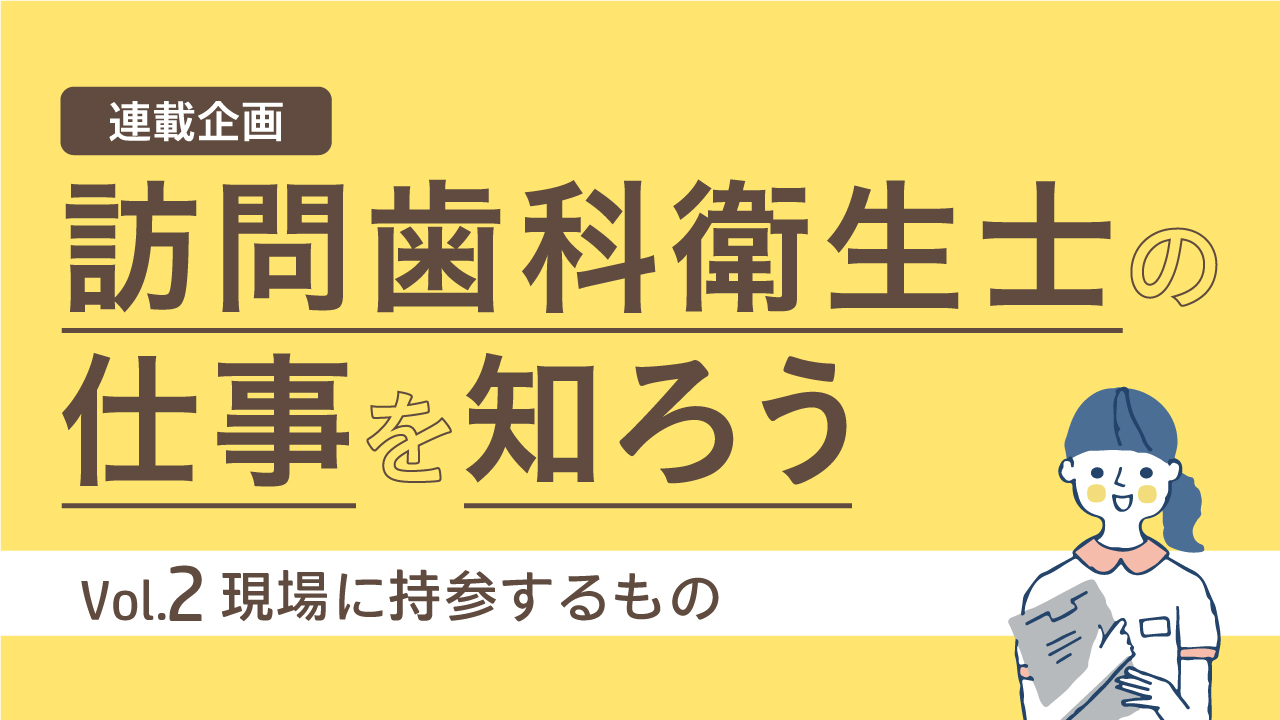
訪問歯科衛生士の仕事を知ろう ~Vol.2 現場に持参するもの ~
Vol.2 現場に持参するもの 歯科衛生士16年目、歯科訪…
Vol.2 現場に持参するもの 歯科衛生士16年目、歯科訪…
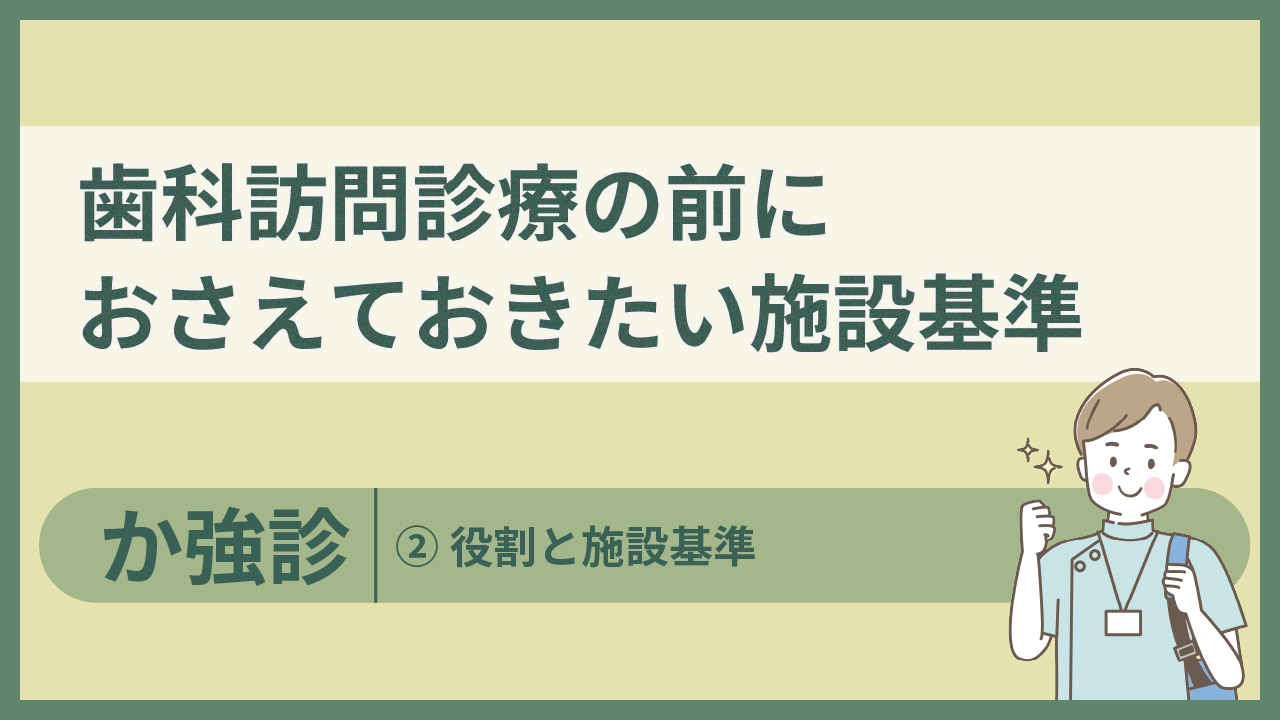
歯科訪問診療の前におさえておきたい施設基準(か強診編②役割と施設基準)
歯科訪問診療の前におさえておきたい施設基準 「…
歯科訪問診療の前におさえておきたい施設基準 「…
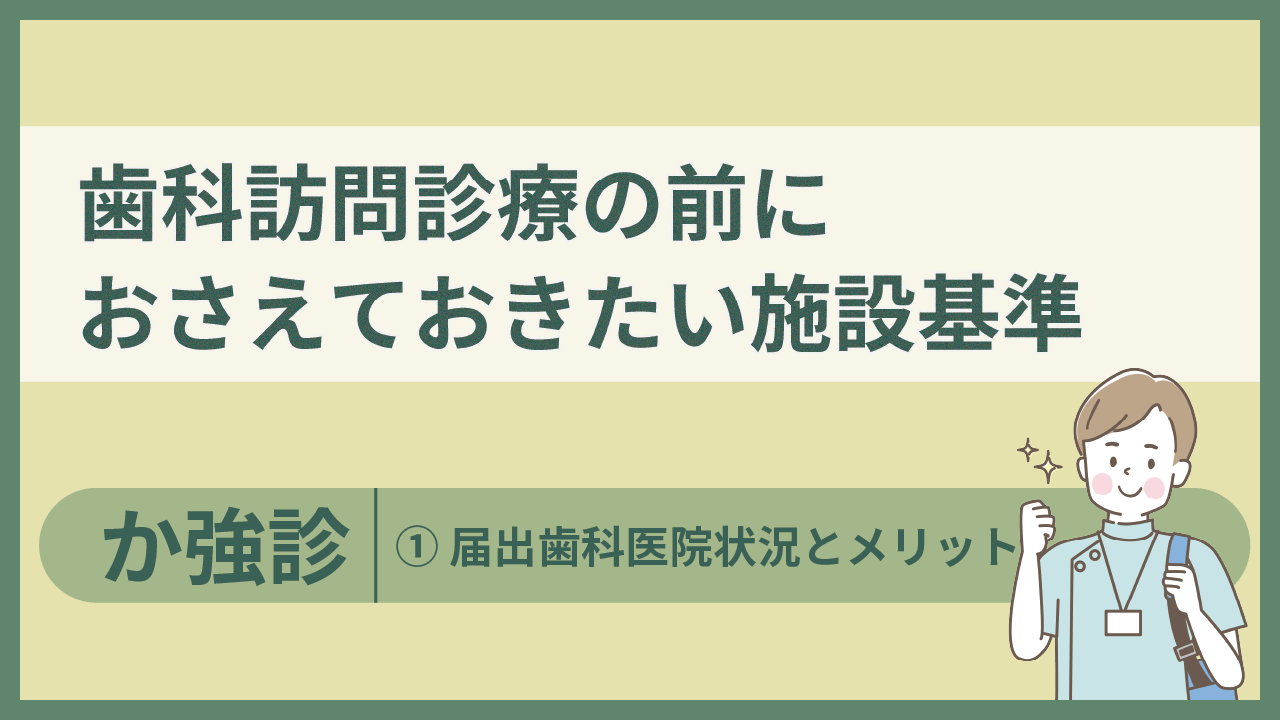
歯科訪問診療の前におさえておきたい施設基準(か強診編①届出歯科医院状況とメリット)
歯科訪問診療の前におさえておきたい施設基準 「…
歯科訪問診療の前におさえておきたい施設基準 「…