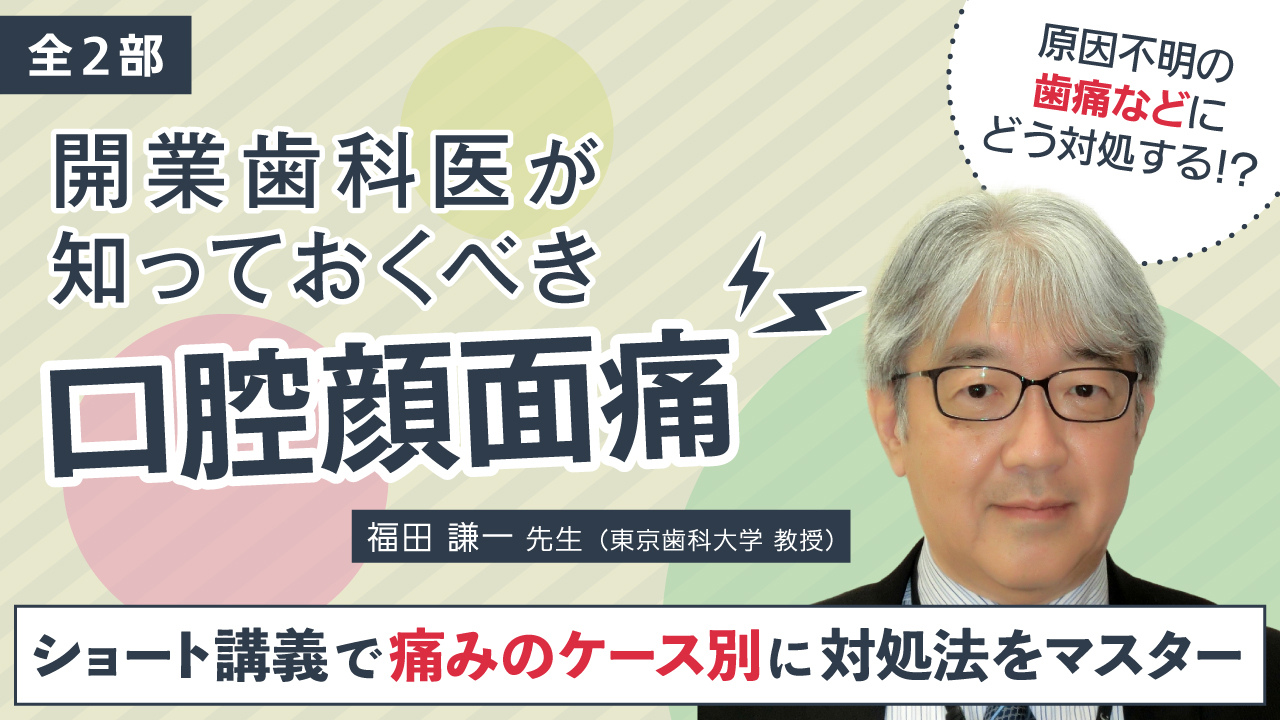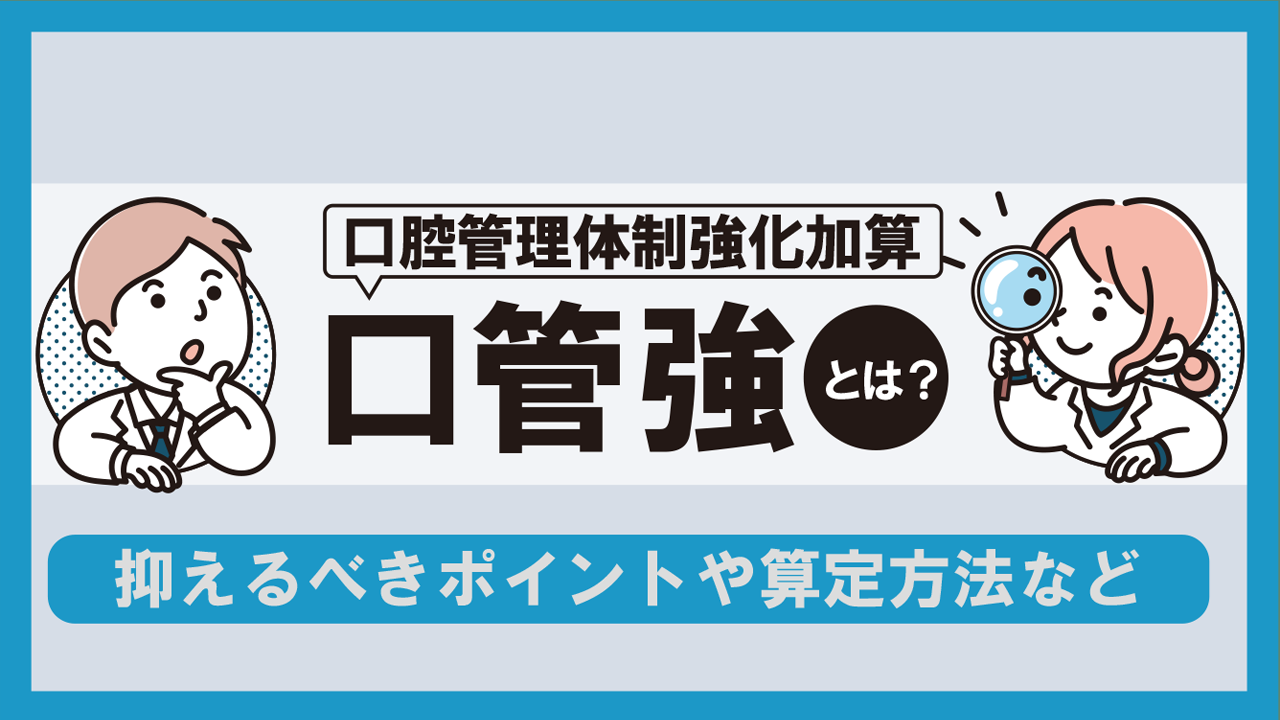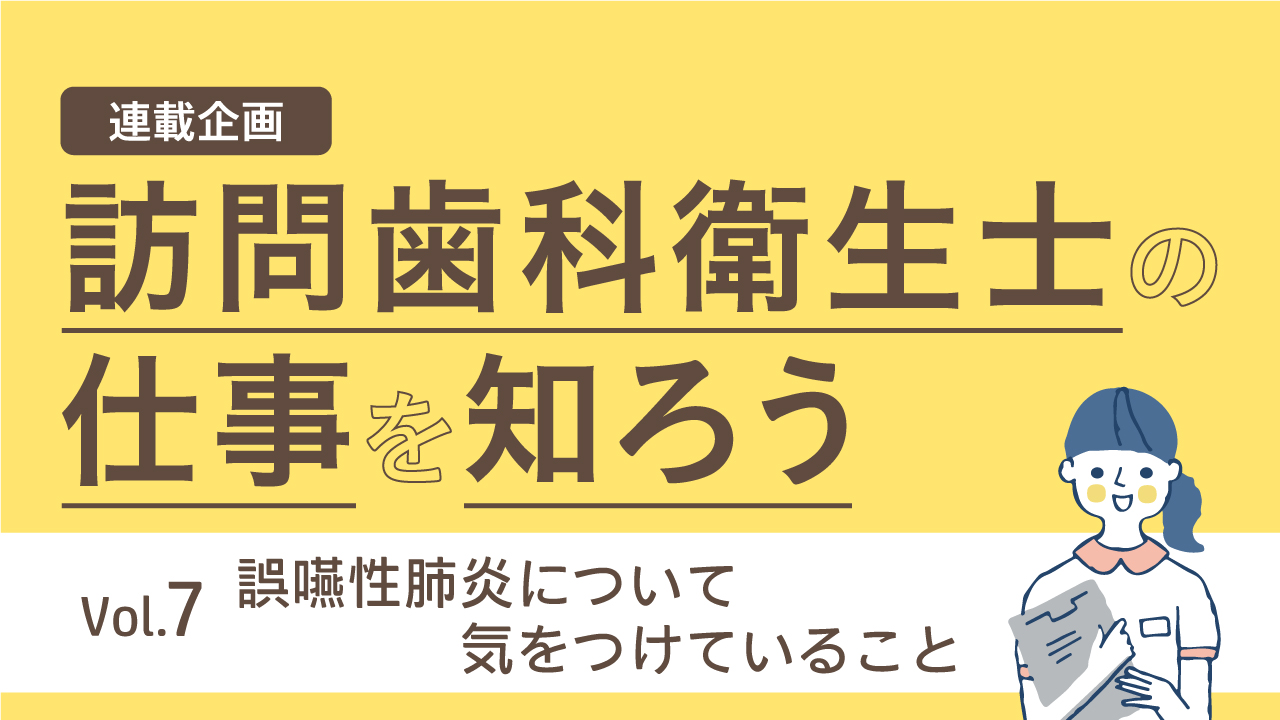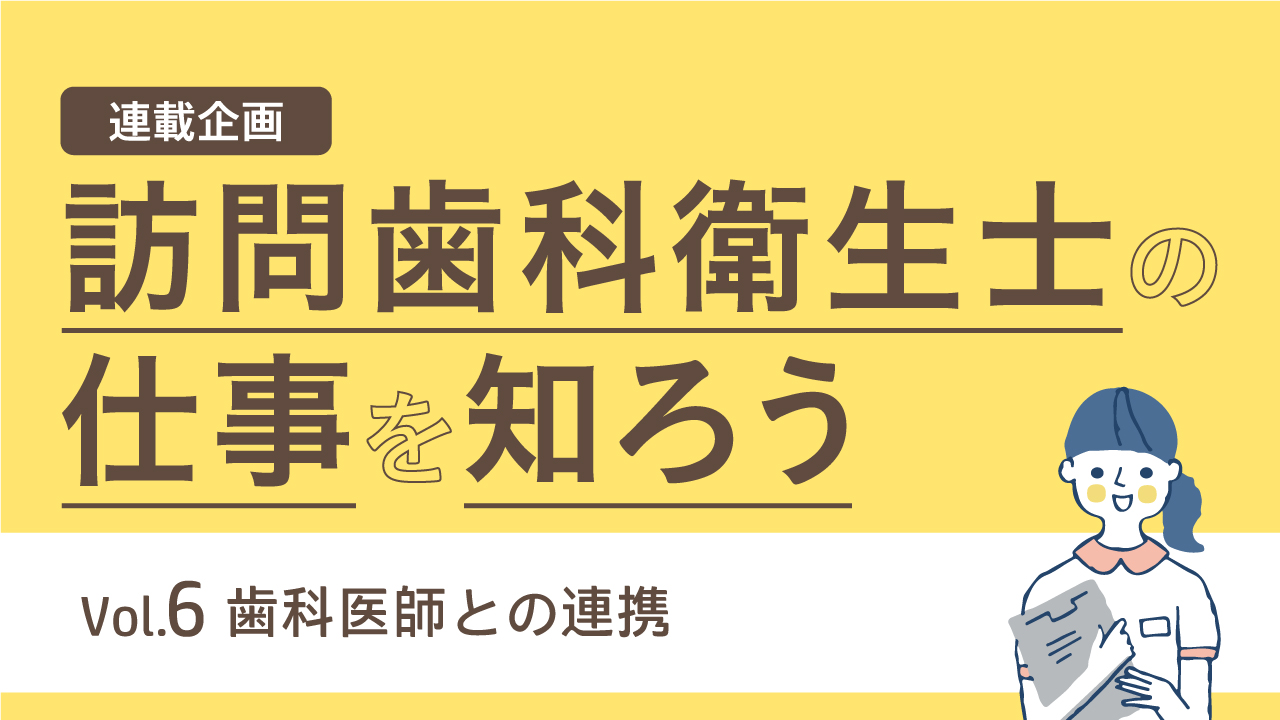開業歯科医が知っておくべき口腔顔面痛 -非歯原性歯痛に対し安心安全な歯科診療を提供する為に-
歯科臨床一般
2024/10/30
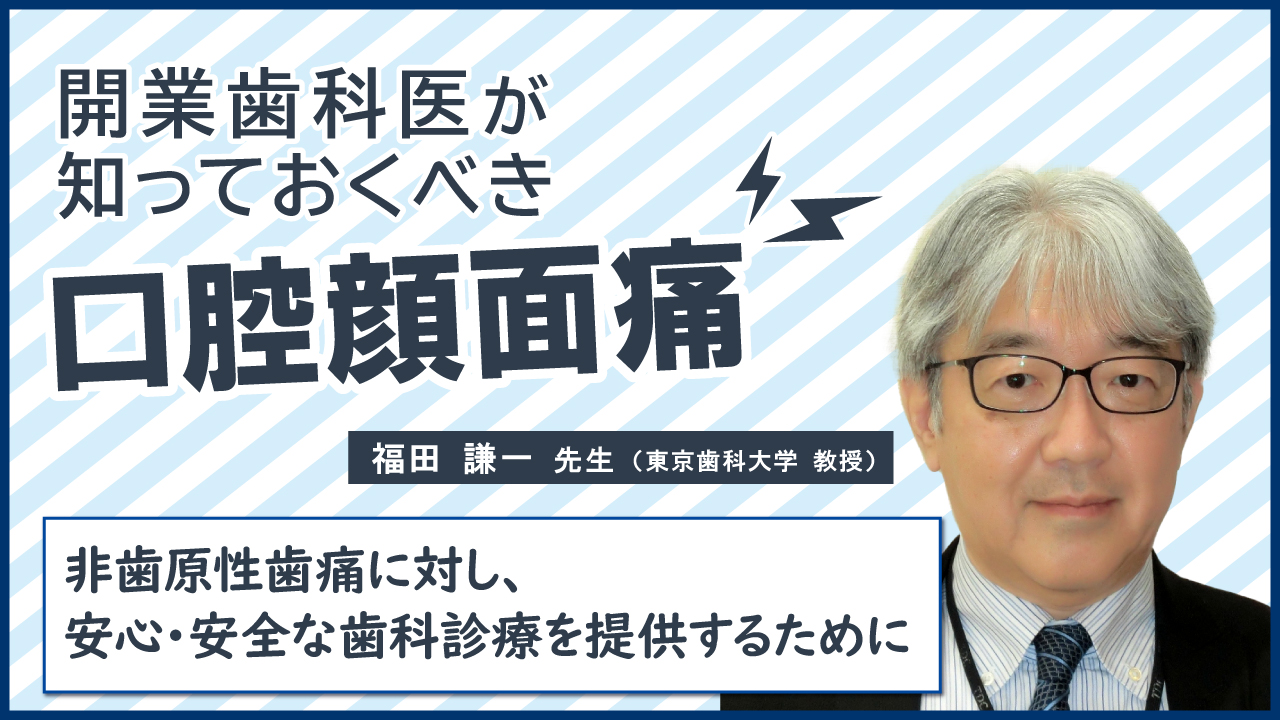
監修:福田謙一 先生
・東京歯科大学 口腔健康科学講座 障害者歯科・口腔顔面痛研究室 教授
・東京歯科大学水道橋病院スペシャルニーズ歯科・ペインクリニック科 科長
《目次》
1.非歯原性歯痛は、歯痛全体の2.1~9%を占めると推定
2.不要な抜髄や抜歯を行い、トラブルを招くケースも
3.非歯原性歯痛(筋・筋膜性歯痛)の診断ポイント
4.顎の痛みや舌痛など、近年問題視される口腔顔面痛
1.非歯原性歯痛は、歯痛全体の2.1%~9%を占めると推定
歯科を訪れる患者さんは、痛みを主訴とすることが多いと思います。その多くの痛みは、歯髄炎、歯周炎、歯牙破折などの器質的疾患が起因しており、部位さえ特定できれば、その診断は比較的容易です。また、その原因を除去することによって容易に除痛することができます。
しかしながら、視覚的にもX線的にも痛みの原因を認識できず、困惑したという御経験がおありではないでしょうか。また、「抜髄後、患者さんが執拗な痛みを訴えているにもかかわらず、原因がよくわからない」「抜歯後の抜歯窩の治癒は良好にもかかわらず、患者さんが痛みを訴える」「補綴物を入れたらよくわからない痛みを訴え始めた」といった御経験がおありではないでしょうか。
このような痛みの多くが、歯そのものに原因が存在しない非歯原性歯痛と呼ばれる病態です。病名ではありませんが、口腔顔面痛の代表的な病態用語として、近年広く知られるようになってきました。ある統計によると、非歯原性歯痛は歯痛全体の2.1~9%を占めると推定されています(※1-2)。
2.不要な抜髄や抜歯を行い、トラブルを招くケースも
非歯原性歯痛に代表される口腔顔面痛は、従来の大学教育では言及されることがなかった新しい領域です。開業歯科医師にとっては、診断・対応が難しい疾患のひとつです。
例えば、視覚的にもエックス線的にも、痛みの原因が見当たらない歯痛症例の場合、原因が特定できないまま、不要な抜髄や抜歯をしてしまうことで、トラブルが起きてしまうケースも増えています。ある報告では、年間680,000本の歯が根管に原因のない歯科治療が行われてしまう傾向にあるとされています(※3)。
不要なトラブルを回避し、安心・安全な歯科治療を提供するためにも、口腔顔面痛に対する正しい知識を持ち、適切な対応法を知ることが不可欠です。非歯原性歯痛の診断にあたっては、まず下記の分類を念頭に置く必要があります。
【非歯原性歯痛の分類】
(1)筋・筋膜痛による歯痛
非歯原性歯痛のなかでも最も頻度が高い。まずは筋・筋膜性歯痛を疑うといっても過言ではない。必ず筋のトリガーポイントが存在するので探索して診断を下す。
(2)神経障害性疼痛による歯痛
歯に接続される神経を障害されることによって発現する痛みである。水痘帯状疱疹ウイルスによる神経障害や医原性の神経損傷、また神経が長期に圧迫されて起こる異常放電(三叉神経痛)によるものもある。日常臨床で頻繁に行われる抜髄や抜歯などの神経障害処置によって発生する場合も稀にある。
(3)神経血管性頭痛による歯痛(片頭痛、群発頭痛など)
片頭痛のような血管性由来の歯痛で、上下顎犬歯と小臼歯部に多い。片頭痛と同時に出現することが多い。また、群発頭痛由来の歯痛もあり、上顎の大臼歯部に多い。その多くが、自律神経症状をともなう。
(4)上顎洞疾患による歯痛
上顎洞炎などの上顎洞の疾患が、関連性を確認できない別の歯に痛みを生じさせる場合がある。
(5)心臓疾患による歯痛(狭心症など)
虚血性心疾患などの痛みが歯に関連痛を出現させる痛みで、歯痛が先行して心疾患が発見されることもある。
(6)精神疾患または心理社会的要因による歯痛(身体表現性障害、統合失調症、大うつ病性障害など)
精神疾患や心理的ストレスなどの影響で、神経伝達に変調が起きて発現した歯痛である。
(7)特発性歯痛(非定型歯痛を含む)
突然、特発的に生じる痛みで、特発的に神経伝達に変調が起きて発現した歯痛である。
(8)その他のさまざまな疾患により生じる歯痛
癌性疾患や頸部、胃、食道などの疾患に起源がある歯痛が出現することがある。
※参照元:非歯原性歯痛の診療ガイドライン改訂版 日本口腔顔面痛学会
3.非歯原性歯痛(筋・筋膜性歯痛)の診断ポイント
視覚的にもエックス線的にも、痛みの原因が見当たらない歯痛症例の場合、どのように診断すべきか。圧倒的に多いのは、筋・筋膜性歯痛です。したがって、まずはこれを疑い、咀嚼筋を十分に診察し、圧痛点であり、関連痛を出現させるトリガーポイントを探索することが重要になります。
咀嚼筋にあるトリガーポイントを確認できない場合、まず激痛発作の有無を確認します。上顎臼歯部の歯痛と目をえぐられたような激痛発作があれば群発頭痛であり、きわめて短時間の電撃痛発作であれば三叉神経痛由来の歯痛を疑います。
次に局所麻酔による除痛効果の有無を調べていきます。除痛効果があれば、その局所に原因が潜んでいる可能性が高いといえます。このように診断にあたっては手順に沿って行うことが基本になります。
非歯原性歯痛は、発生メカニズムの点から大きく分けると、関連痛(筋肉と血管)、神経障害性の歯痛、痛覚変調性の歯痛の3つに分けられます。このことを念頭に入れて、診断に困惑した場合には慎重に対応します。そして、一度「非歯原性歯痛」と診断しても、試験的局所麻酔、筋や神経系の診察、鎮痛薬の効果の確認など、順序を追って診断を進め、明確な最終診断や治療が困難であれば、高次医療機関に患者を紹介することが大切です。
4.顎の痛みや舌痛など、近年問題視される口腔顔面痛
国民の約13~25%が、身体のいずれかに慢性疼痛を抱え、中高年ではその割合が46.4%にのぼるといわれ、また歯科領域の慢性疼痛(非歯原性歯痛を含む)は、国民の1~6%程度と推測されており、近年、問題視されています(※4-8)。
歯科領域では、非歯原性歯痛以外に、顎や顔面の痛み、舌痛(口腔カンジダ症や口腔乾燥症、舌痛症など)も口腔顔面痛に分類されます。口腔顔面痛は会話や摂食にかかわり、患者さんのQOL(Quality of Life)に大きな影響を与えます。そのことを考えると、歯科医師として決して無視することはできません。
開業歯科医師として、患者さんにより安心・安全な歯科診療を提供していくうえで、このような口腔顔面痛に対する基本的な知識と対応法を習得することは、今後ますます重要性を高めていくと考えています。
<参考文献>
※1:坂本英治,石井健太郎,江崎加奈子,塚本真規,横山武志.【口腔顔面領域の慢性痛の診断と治療】 非歯原性歯痛の診断と治療.ペインクリニック.36(7):907-917,2015.
※2:Nixdorf D, Moana-Filho E. Persistent dento-alveolar pain disorder (PDAP): Working towards a better understanding. Rev Pain. 5(4):18-27, 2011.
※3 Benjamin P. Pain after routine endodontic therapy may not have originated from the treated tooth. J Am Dent Assoc. 142(12):1383-1384, 2011.
※4:服部政治, 日本における慢性疼痛保有率,日薬理誌 127: 176-180,2006
※5:松平浩, 竹下克志, 久野木順一, 山崎隆志, 原慶宏, 山田浩司, 高木安雄, 日本における慢性疼痛の実態-Pain Asspciated Cross-sectional Epidemiological(PACE) survery 2009 JP-, ペインクリニック32(9):1345-1356,2011
※6:Nakamura M, Nishiwaki Y, Ushida T, Toyama Y, Prevalence and characteristics of chronic musculoskeletal pain in Japan, J Orthop Sci 16(4): 424- 432, 2011. doi: 10.1007/s00776-011-0102-y. Epub 2011 Jun 16.
※7:Anno K, Shibata M, Ninomiya T, Iwaki R, Kawata H, Sawamoto R, Kubo C, Kiyohara Y, Sudo N, Hosoi M, Paternal and maternal bonding styles in childhood are associated with the prevalence of chronic pain in a general adult population: the Hisayama Study, BMC Psychiatry 15: 181, 2015.doi: 10.1186/s12888-015-0574-y.
※8:和嶋浩一, 矢谷博文, 井川雅子, 小宮山道, 坂本英治, 松香芳三, 松岡渡, 非歯原性歯痛診療ガイドライン, 日口腔顔面痛会誌 4(2): 1-88,2011
ショート講義で「痛みのケース別に対処法」をマスター!
開業歯科医必見の「口腔顔面痛」セミナー配信中!
この記事の関連記事