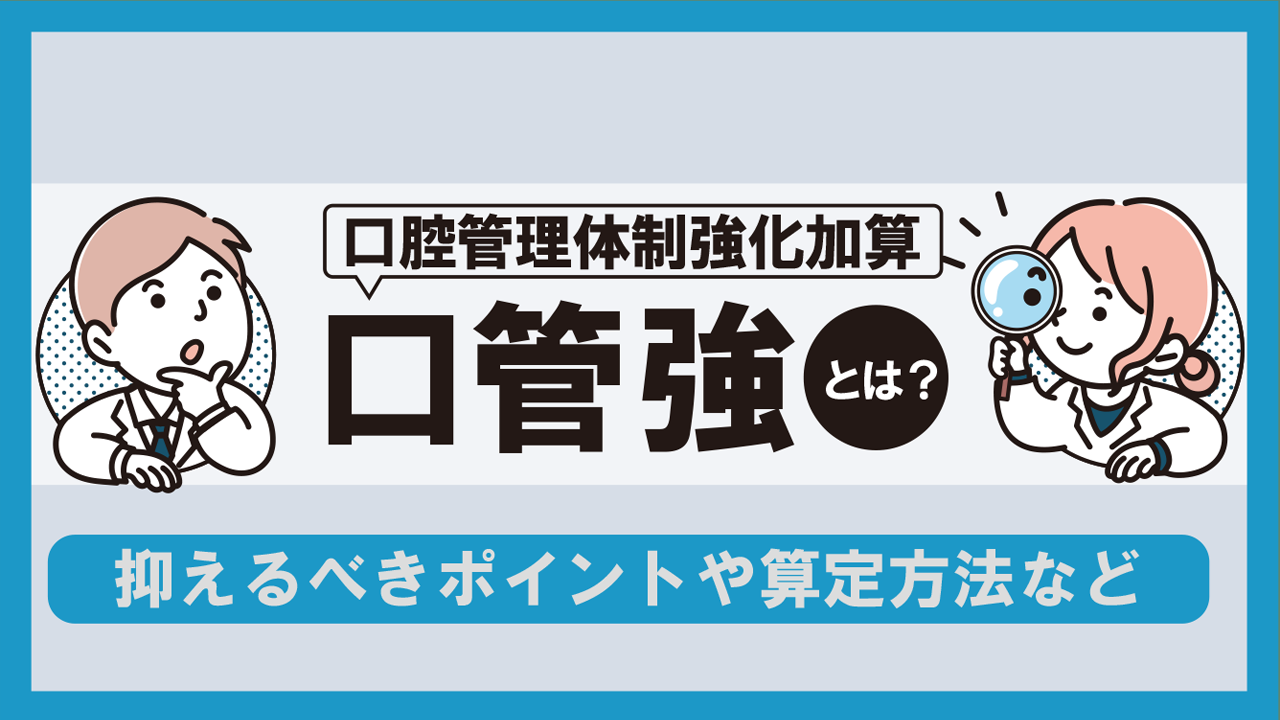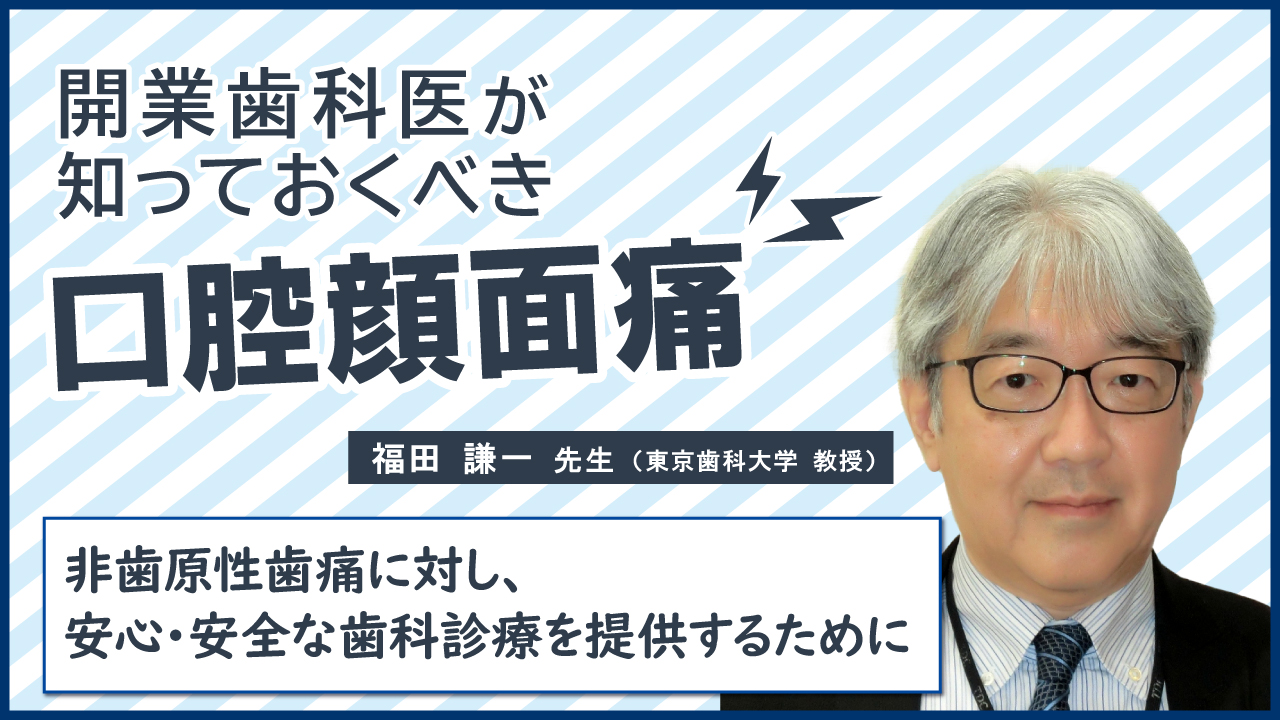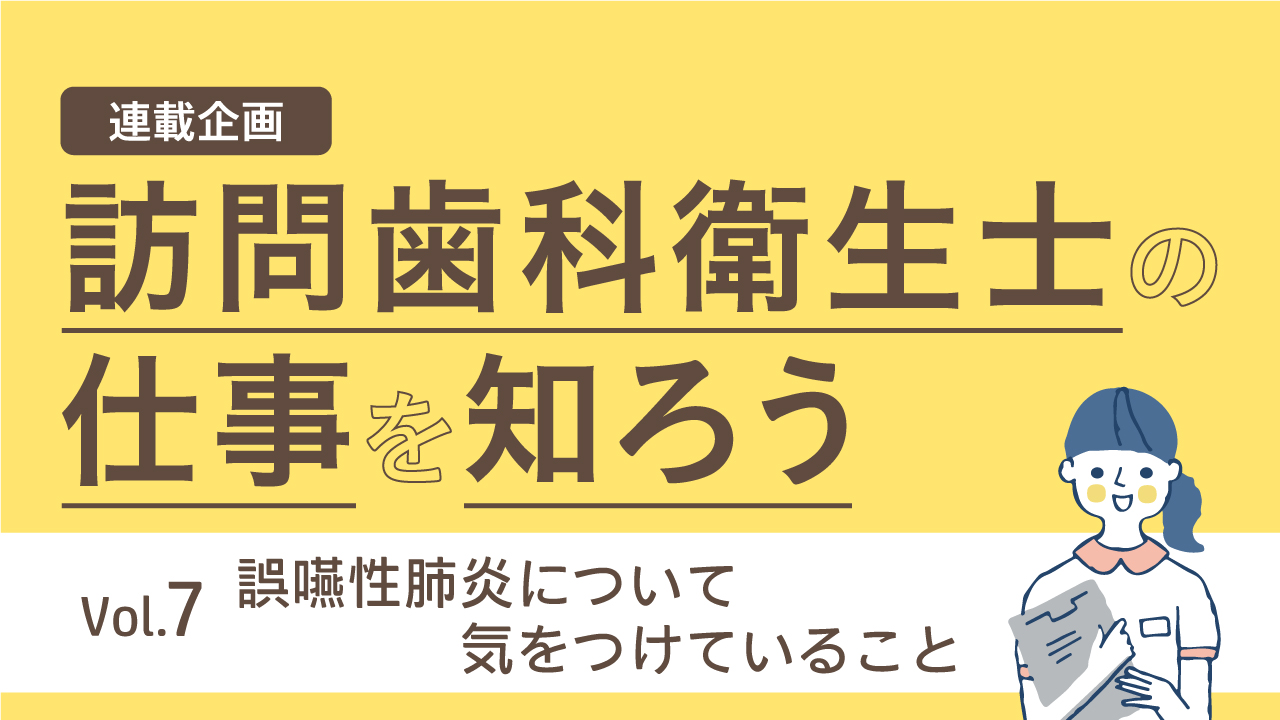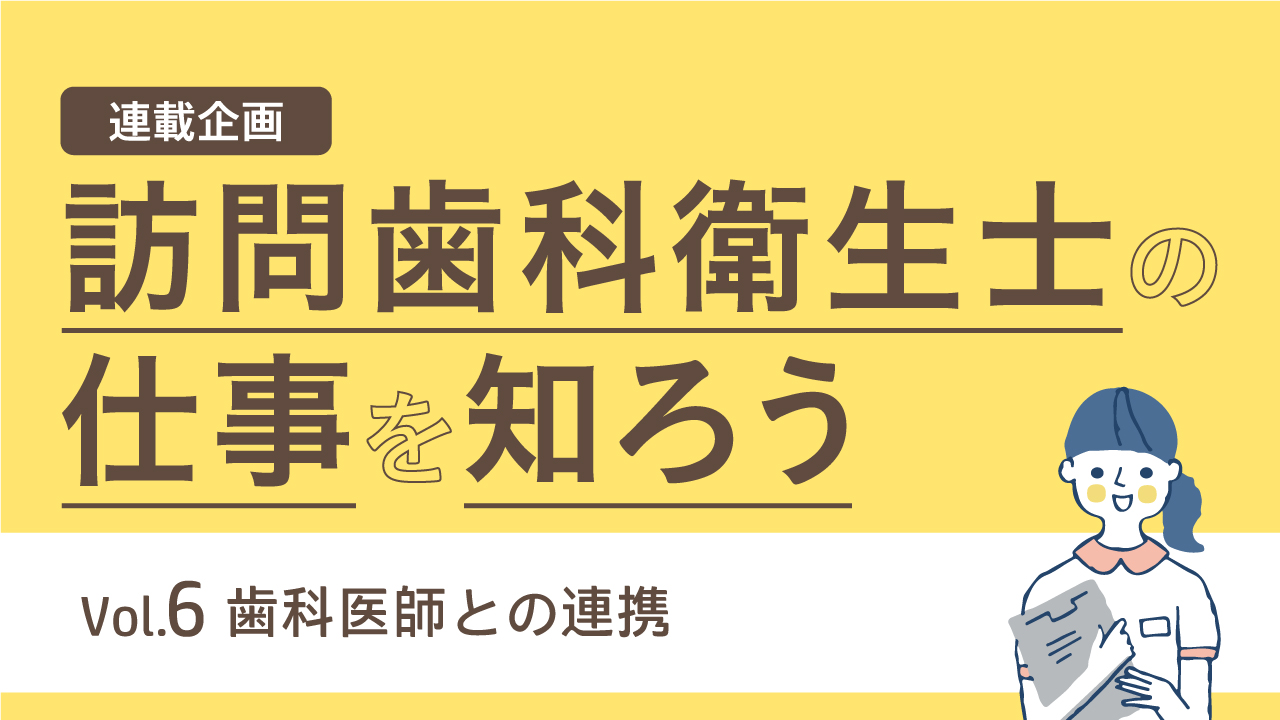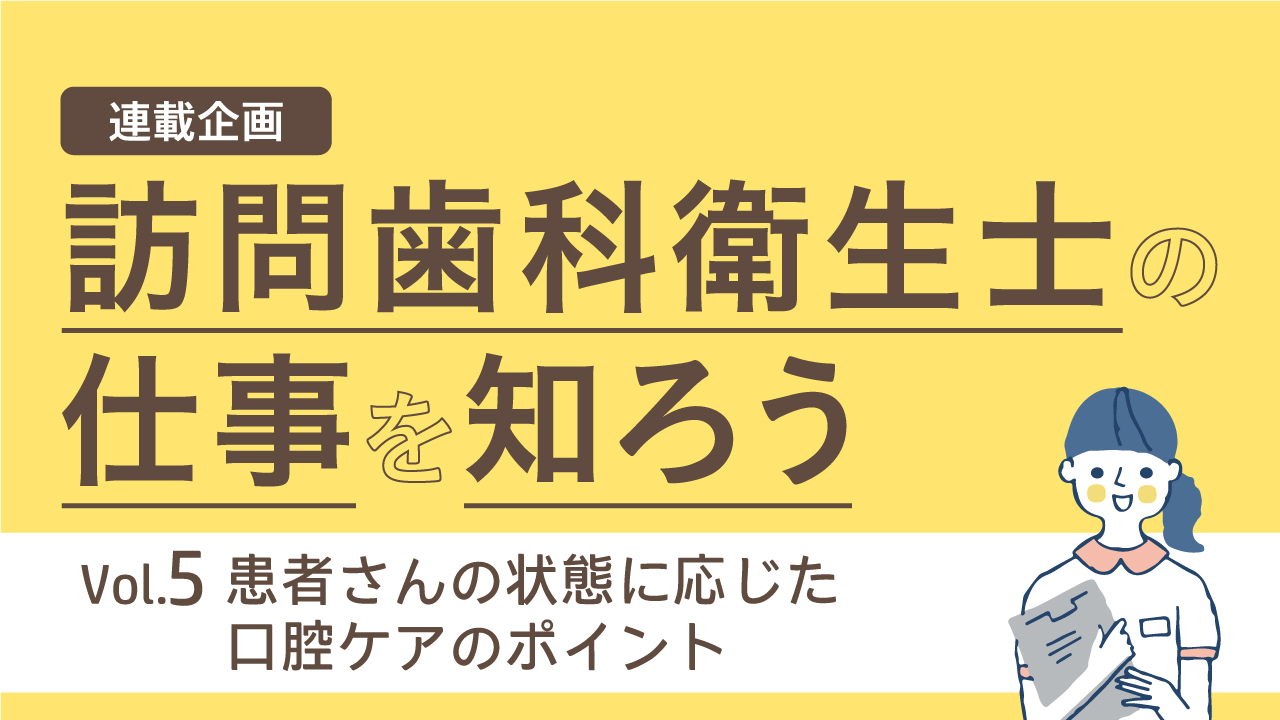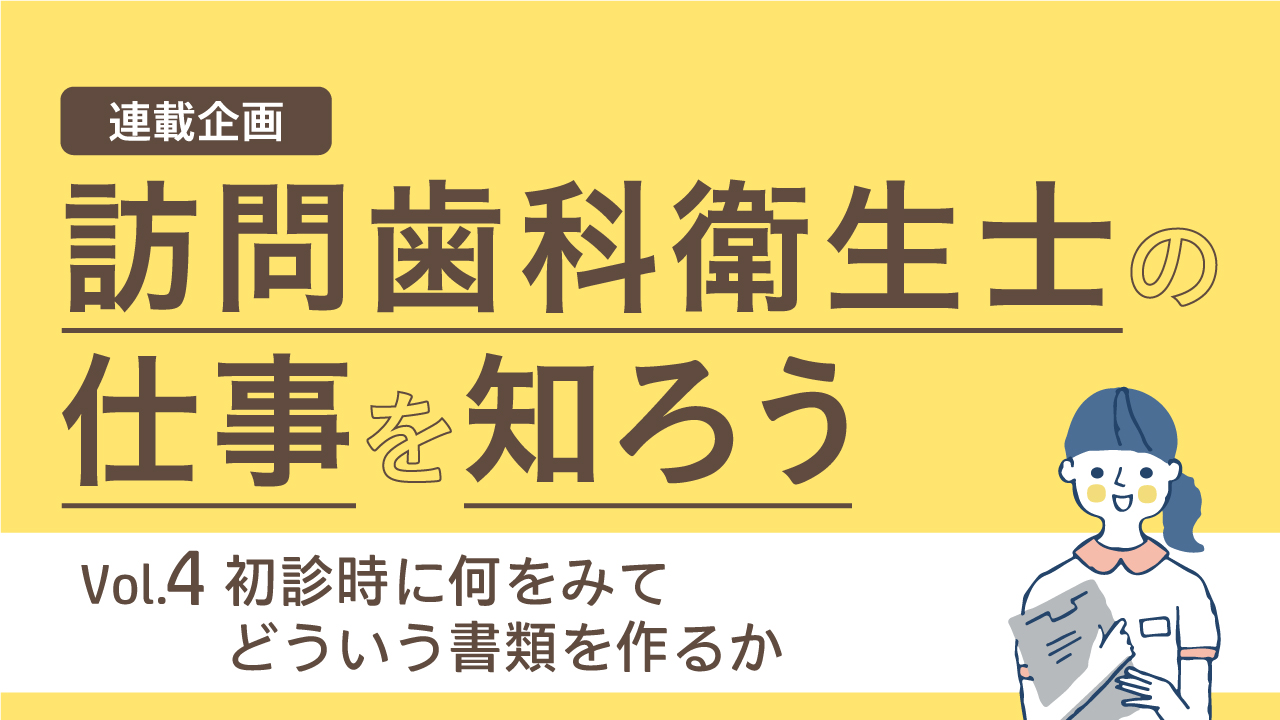【インタビュー】現代美術、オンライン診療、BOC 医療/+αで社会課題の解決を目指す(第1回)
インタビュー
2021/03/31
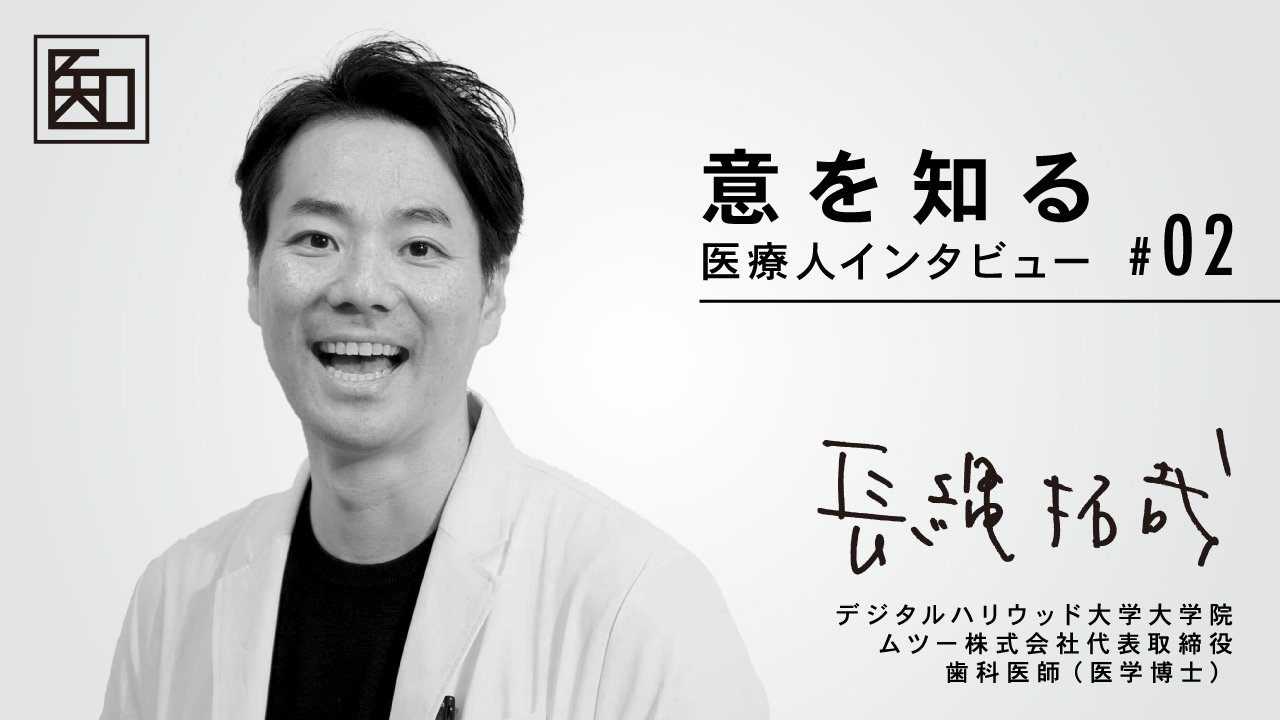
歯科医師 長縄拓哉 先生 歯科医師(医学博士) デジタルハリウッド大学大学院 ムツー株式会社代表取締役
東京歯科大学卒業。都内大学病院で口腔腫瘍、顎顔面外傷、口腔感染症治療に従事。デンマーク・オーフス大学に留学し、口腔顔面領域の難治性疼痛(OFP)について研究。口腔顔面領域の感覚検査器を開発し、国際歯科研究学会議(IADR2015、ボストン)ニューロサイエンスアワードを受賞。デンマークと日本の研究活動推進プロジェクトJD-Teletech日本代表。(一社)訪問看護支援協会BOCプロバイダー認定資格講座総括医師。 * 日本遠隔医療学会・歯科遠隔医療分科会長。 * 日本口腔顔面痛学会評議員、同学会診療ガイドライン作成委員。 * 日本口腔内科学会代議員。 * 厚生労働省教育訓練プログラム開発事業 メディカルイノベーション戦略プログラム委員。 * 千葉大学遠隔医療マネジメントプログラム委員。
長縄拓哉 - 歯科臨床に携わりながらも、医療・介護従事者向けのオーラルケア資格講座「BOCプロバイダー」グループを立ち上げ、「がんと言われても動揺しない社会」をめざす「CancerX」の運営にも関与、さらに医療の枠を超え「現代美術」の要素を取り入れて医療に新たな価値を与え続けている歯科医師である。
「実はその全てがある考えに基づいている。」 サラっと語る長縄拓哉先生の「真意」を深掘りする。
■競争を避け、医療の枠にこだわらない 僕はもともと歯科や医療に強い思いはありませんでしたが、両親の勧めでなんとなく医療の道を目指しました。父は、リゲインのCMで歌われていたような24時間働き続けるいわゆる「昭和の商社マン」でした。残業や接待で夜遅くに帰宅し、僕が起床する前には既に出社している、ワークライフバランスなんてものはない。心身ともに非常に大変で、自身の経験から僕にそのような苦労はさせたくなかったんじゃないかと思います。やはり手に職をつけたほうがいい、資格を持っていたほうがいいという考えから、「医者」を目指してはどうかと勧められました。 正直、医者や歯医者になりたいモチベーションは一切ありませんでした(笑)。さらにあまり成績が良くなかった(笑)。結果的に、医学部に合格することはなく、歯学部(東京歯科大学)にはなんとか補欠合格することができました。 もともと医学に興味はありませんので、学生時代は、基本的に決められたカリキュラムを淡々とこなしているだけで、ここでも成績はあまり良くなかったです。再試験や補習にはならないギリギリンのラインでした。
ただ、成績が悪くても、できが悪くても生き延びねばなりませんので、「どうすれば楽して結果を出せるか」を真剣に考えていました。楽をするためにめちゃくちゃ努力しました(笑)。そのために当時から今もずっと一貫しているのは、「人と違うことをする」ことです。闘ったら絶対に勝てないことが多いので「競争を避ける」という言い方をしていますが(笑)。 また、上述の経緯の通り、医療という枠へのこだわりもないですね。医学で解決できない問題は、それ以外のアプローチを考えれば良いと思っています。 この二点は一貫して変わらないですね。
学生時代は、普通に勉強していても理解が遅く苦手意識の強かった生化学を克服するために「生化学教室」に入り浸りました。教科書を読んでも分からないので、実際に実験をしたり先生に直接聞いたり、論文を書いたりしていました。ちょうど大学の生化学教室で先生方が研究されている分野が「がん」だったので、興味を持つきっかけになりました。昔から、「医学の力を駆使しても治すのが難しい病気」には凄い興味があり、後述しますが、口腔顔面痛も同じようにマネジメントが難しい病気です。
「競争を避ける」ということはつまり、「プレーヤーが少ない領域を選択する」ということ。プレーヤーが少ない領域は、発展が遅れがちですが患者さんはいる。進歩を加速させたくてもそもそも研究者が少ないので人任せにはできません。徐々に「自分がやらなきゃ」という強い使命感みたいなものが芽生え、結果的にのめり込んでいきます。 プレーヤーが少ないニッチな領域なんていくらでもありますが、その中で何を選択するのか。取り組みを継続するためにも、選択する際の理由付けは明確にしています。具体的には、なぜ自分がやるのか、社会的な貢献性・意義があるのか、自分がやることで世界は変わるのか、を意識して選択しています。このような判断基準があるので、今の僕の取り組みは全て「社会課題の解決」に向いています。
僕が取り組んでいる「口腔顔面痛」(口腔顔面領域の慢性疼痛)もまさにこの考えに基づきます。 口腔顔面痛は完治が難しい病気です。今の医学の技術を集結しても治せないことがあります。認知度は低く、誤解もあり、プレーヤーも少ない、でも患者さんはいる。 この問題に正面から取り組むために、痛みの研究で有名なオーフス大学(デンマーク)に留学しました。帰国後は勤めていた大学病院内に「口腔顔面痛み外来」を立ち上げました。


■日本初の歯科オンライン診療
2017年に、日本では恐らく初めてと思われる「歯科オンライン診療」の取り組みを開始しました。
上述の通り口腔顔面痛というのは、診断・治療方法などが確立されていない病気です。投薬や運動療法を行いながらも、患者さんとお話をすることの割合が多く、精神科の外来のようなイメージです。 ただ、患者さんに痛いのを我慢しながらせっかく外来に足を運んでもらっても(神戸から新幹線で来られる患者さんもいらっしゃいました)、やっていることがお話しするだけというのはどうなんだろうと思ったりして。 ちょうどその頃、精神科の外来は遠隔診療に向いていると話題になっており、痛みのマネジメントも遠隔でできるかもと思いやってみました。 結果的には、症状の安定している患者さんには問題なく行うことができ、また患者さんにもとても喜んでいただきました。今後オンライン診療は間違いなく当たり前のものになる、と思いました。




【インタビュー】現代美術、オンライン診療、BOC 医療/+αで社会課題の解決を目指す(第2回)
【解説】歯科オンライン診療 スタートアップガイド(第1回)
※歯科オンライン診療の制度や導入事例については、下記Webセミナーにて詳しく解説いたします。 【特集】Webセミナー:歯科オンライン診療の今
この記事の関連記事

【インタビュー】根拠ある感染対策を目指す 何を継続し、何をなくすか
大毛 宏喜 氏 広島大学病院感染症科教授 新型コロナウイル…
大毛 宏喜 氏 広島大学病院感染症科教授 新型コロナウイル…
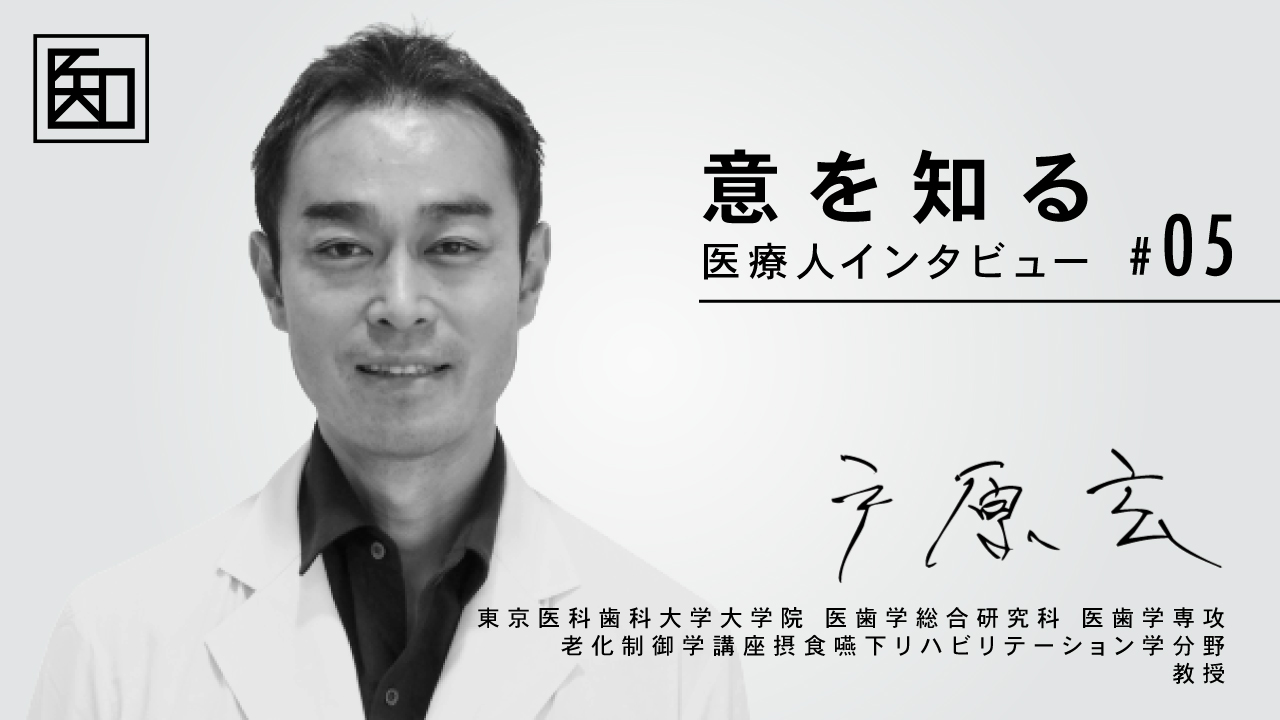
【インタビュー】問われる摂食嚥下障害への対応 /「人生100年時代」の歯科医療
戸原 玄 氏 東京医科歯科大学大学院 教授 「人生100年…
戸原 玄 氏 東京医科歯科大学大学院 教授 「人生100年…
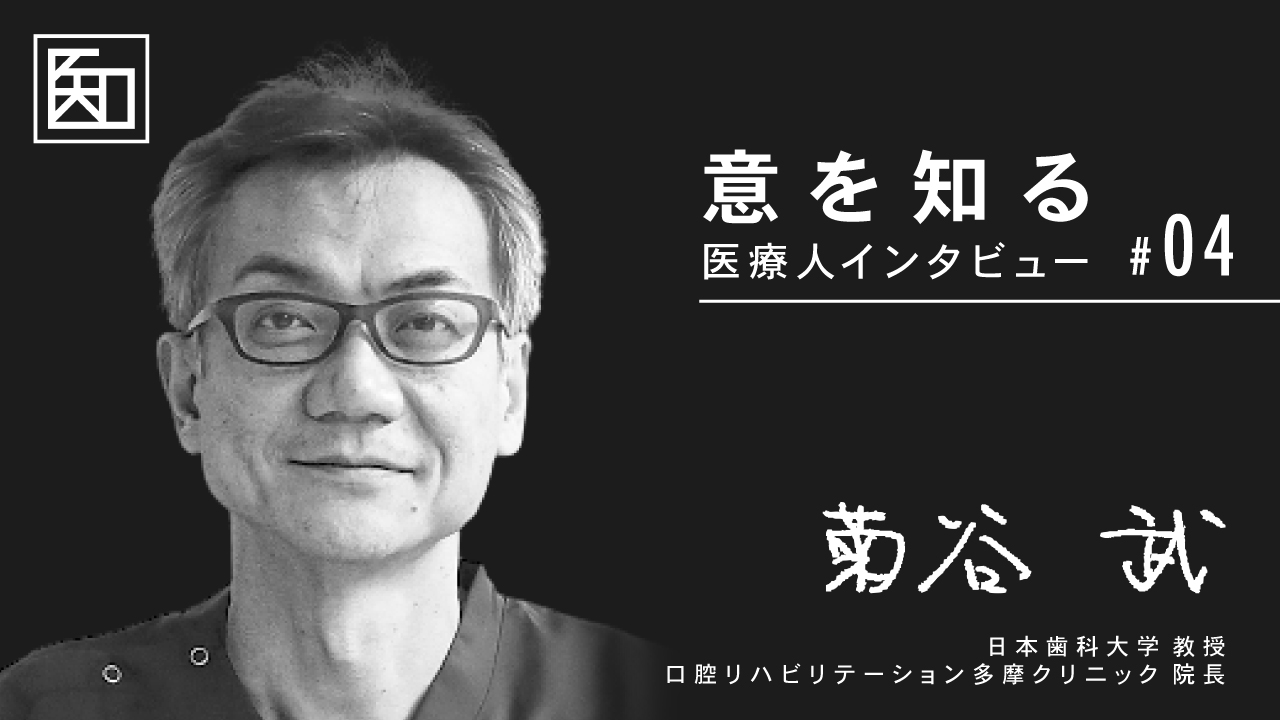
【インタビュー】避けられぬ歯科訪問診療(第2回)
歯科医師 菊谷 武 先生・日本歯科大学 教授・口腔リハビリテ…
歯科医師 菊谷 武 先生・日本歯科大学 教授・口腔リハビリテ…
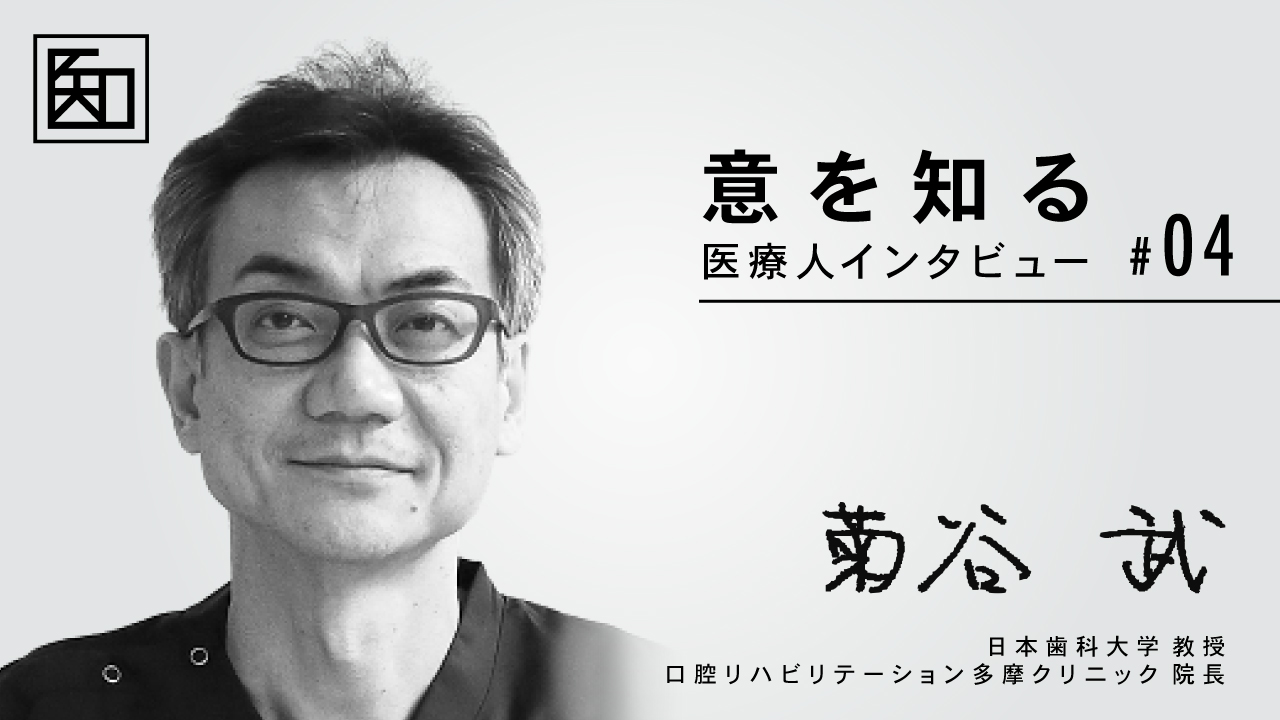
【インタビュー】避けられぬ歯科訪問診療(第1回)
歯科医師 菊谷 武 先生・日本歯科大学 教授・口腔リハビリテ…
歯科医師 菊谷 武 先生・日本歯科大学 教授・口腔リハビリテ…
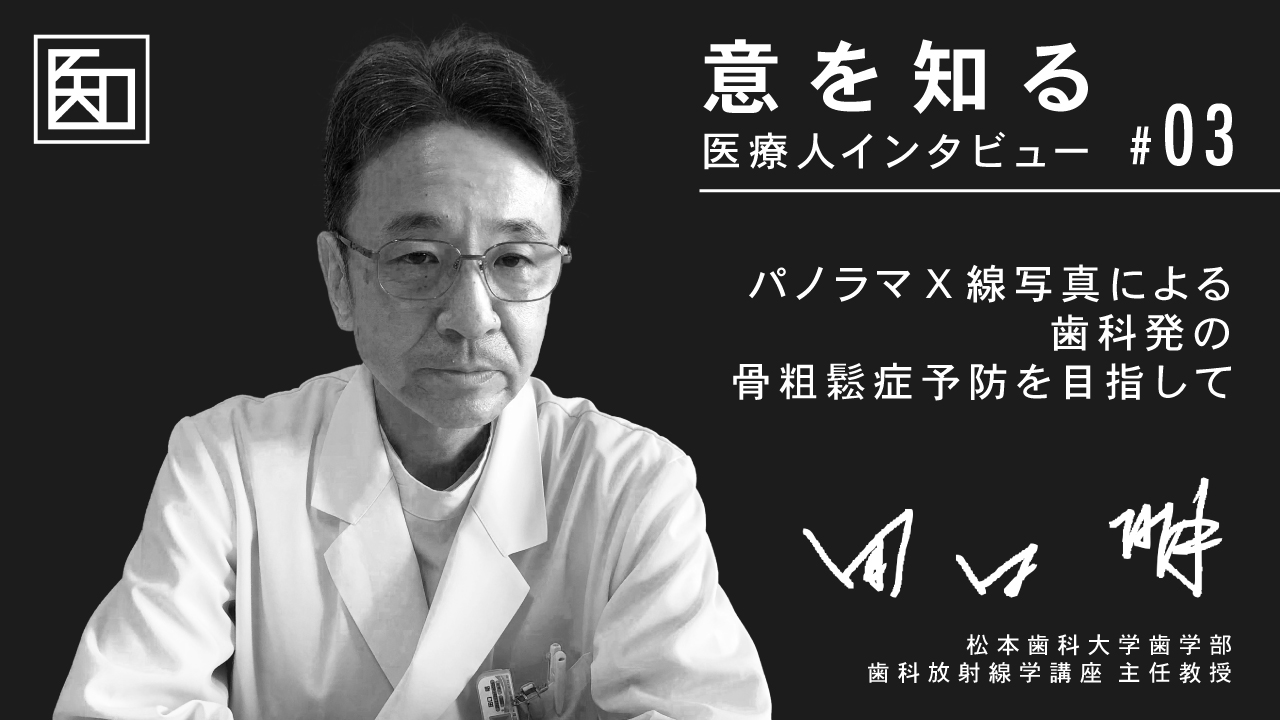
【インタビュー】骨粗鬆症と歯科との関係(第2回)
歯科医師 田口明 先生・松本歯科大学歯学部歯科放射線学講座 …
歯科医師 田口明 先生・松本歯科大学歯学部歯科放射線学講座 …
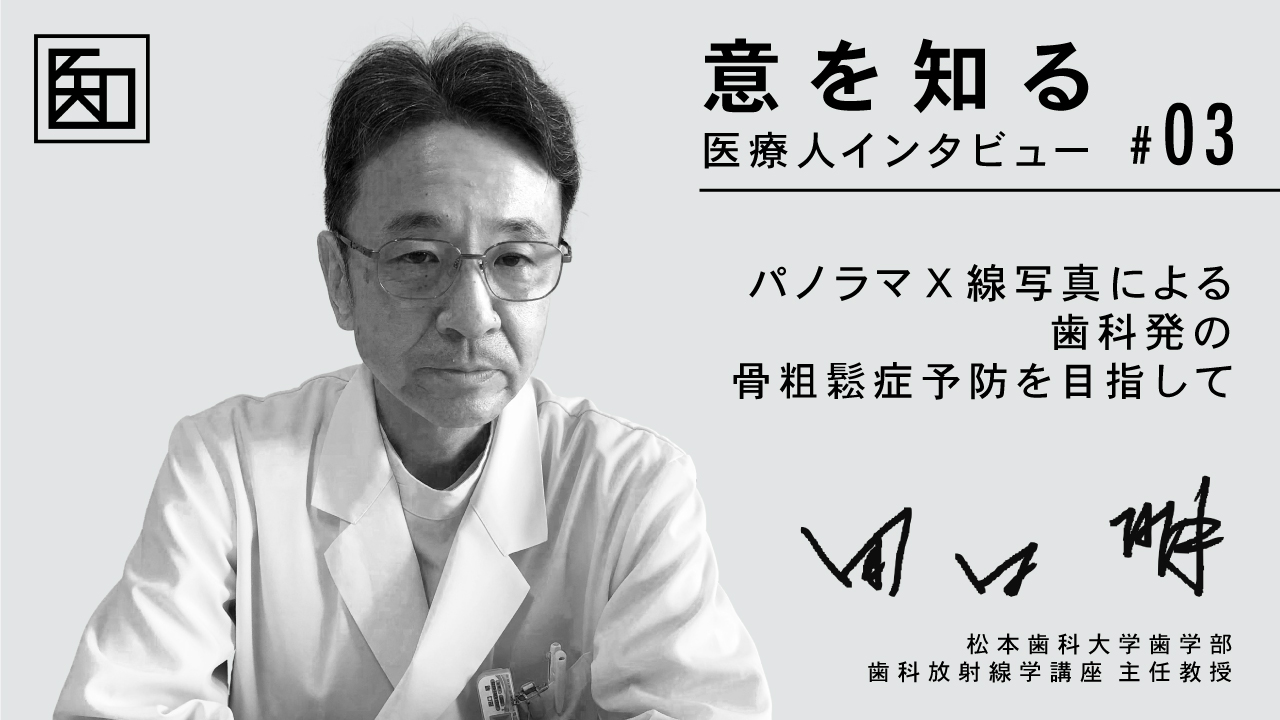
【インタビュー】骨粗鬆症と歯科との関係(第1回)
歯科医師 田口明 先生・松本歯科大学歯学部歯科放射線学講座 …
歯科医師 田口明 先生・松本歯科大学歯学部歯科放射線学講座 …
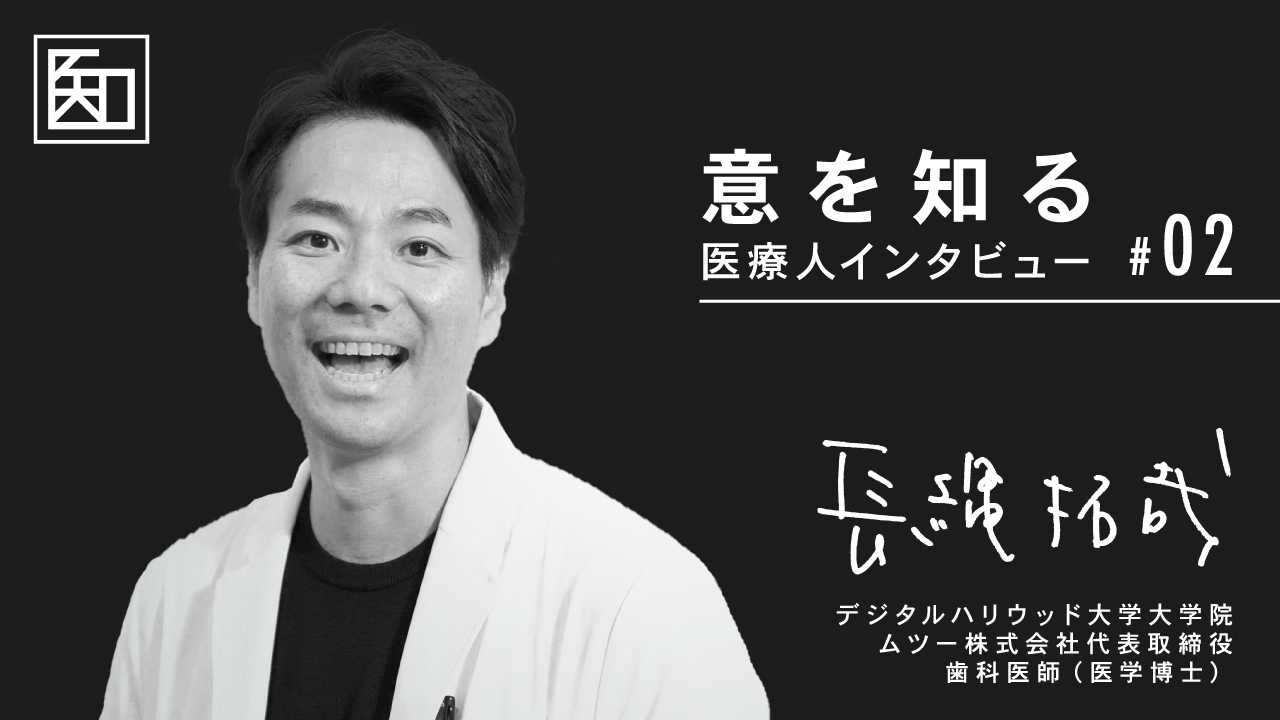
【インタビュー】現代美術、オンライン診療、BOC 医療/+αで社会課題の解決を目指す(第2回)
歯科医師 長縄拓哉 先生 歯科医師(医学博士) デジタルハリ…
歯科医師 長縄拓哉 先生 歯科医師(医学博士) デジタルハリ…
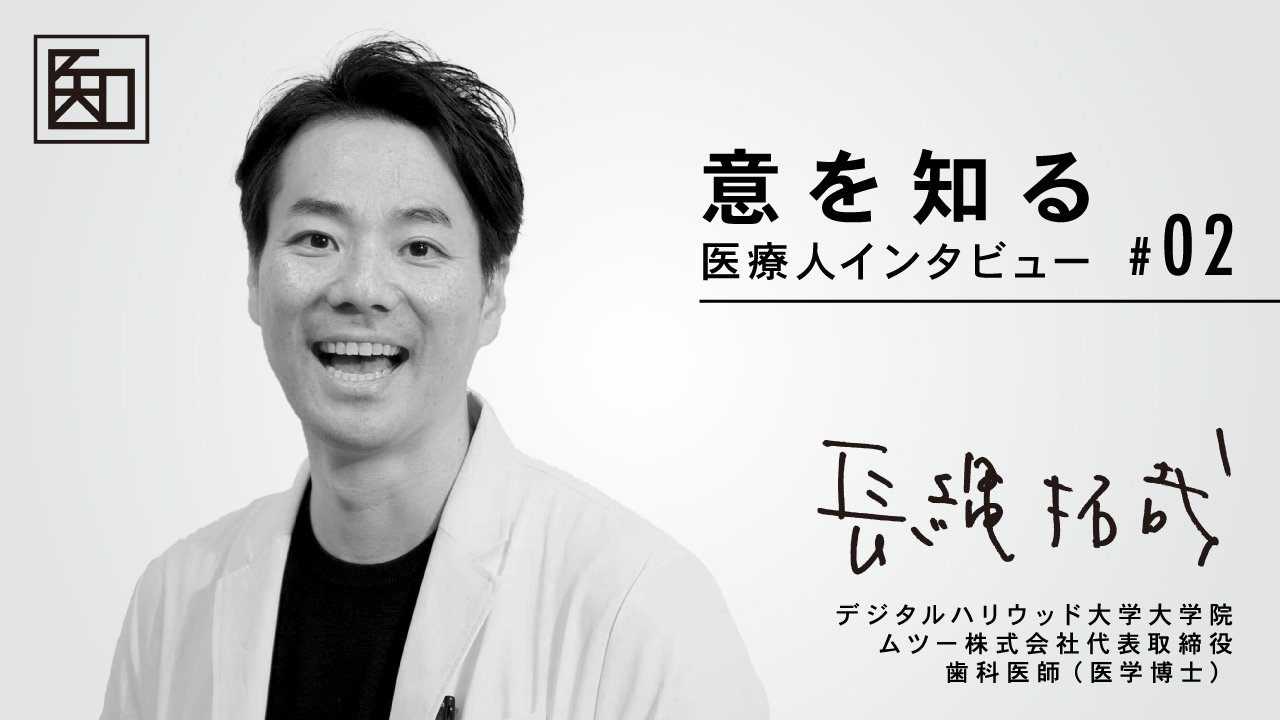
【インタビュー】現代美術、オンライン診療、BOC 医療/+αで社会課題の解決を目指す(第1回)
歯科医師 長縄拓哉 先生 歯科医師(医学博士) デジタルハリ…
歯科医師 長縄拓哉 先生 歯科医師(医学博士) デジタルハリ…