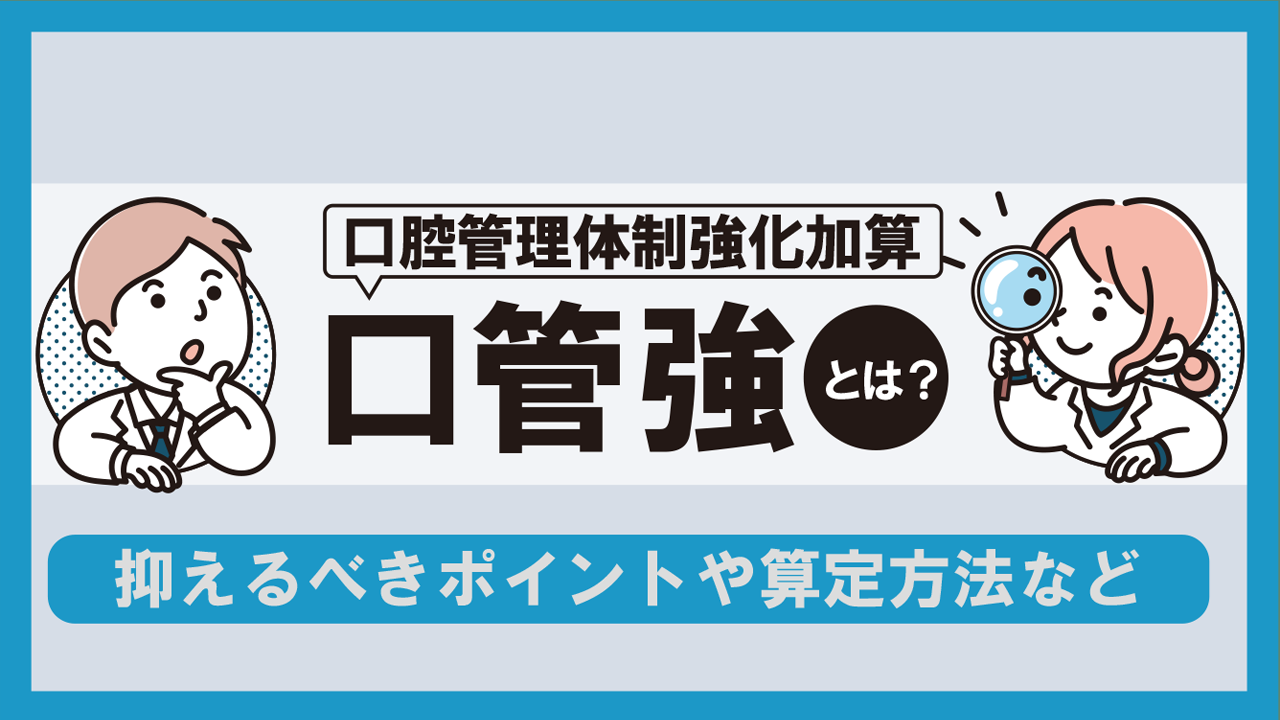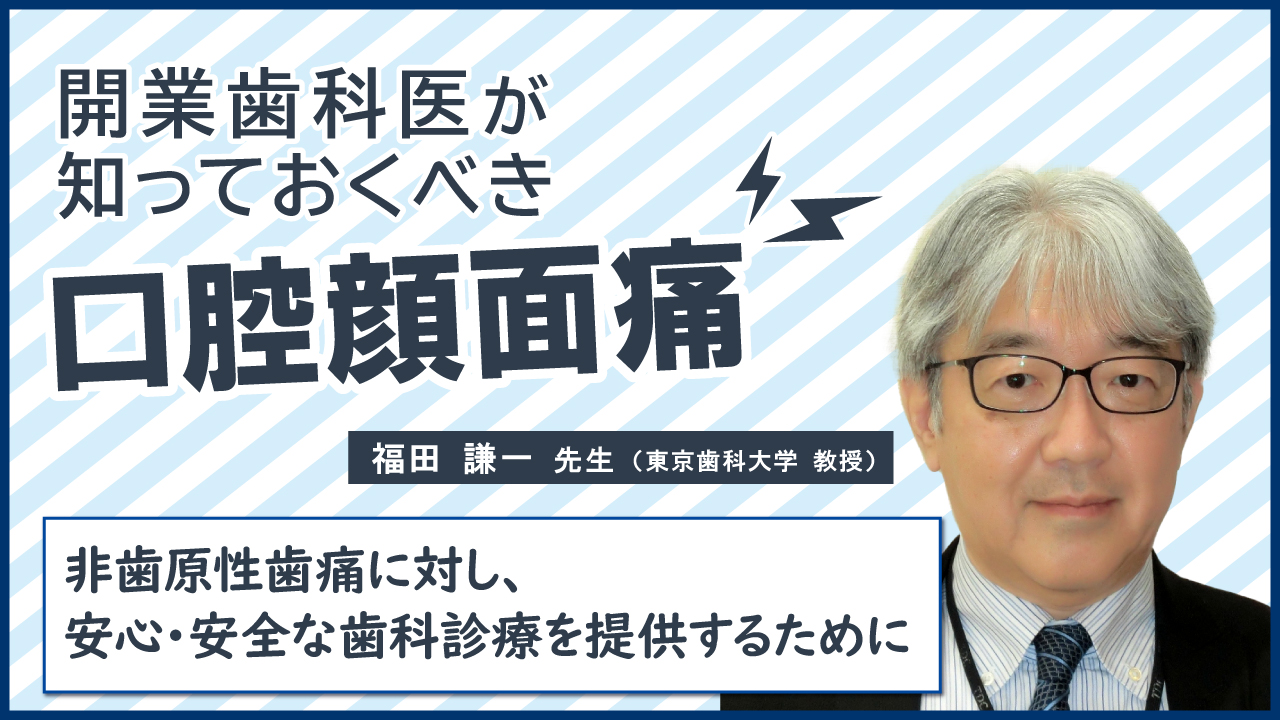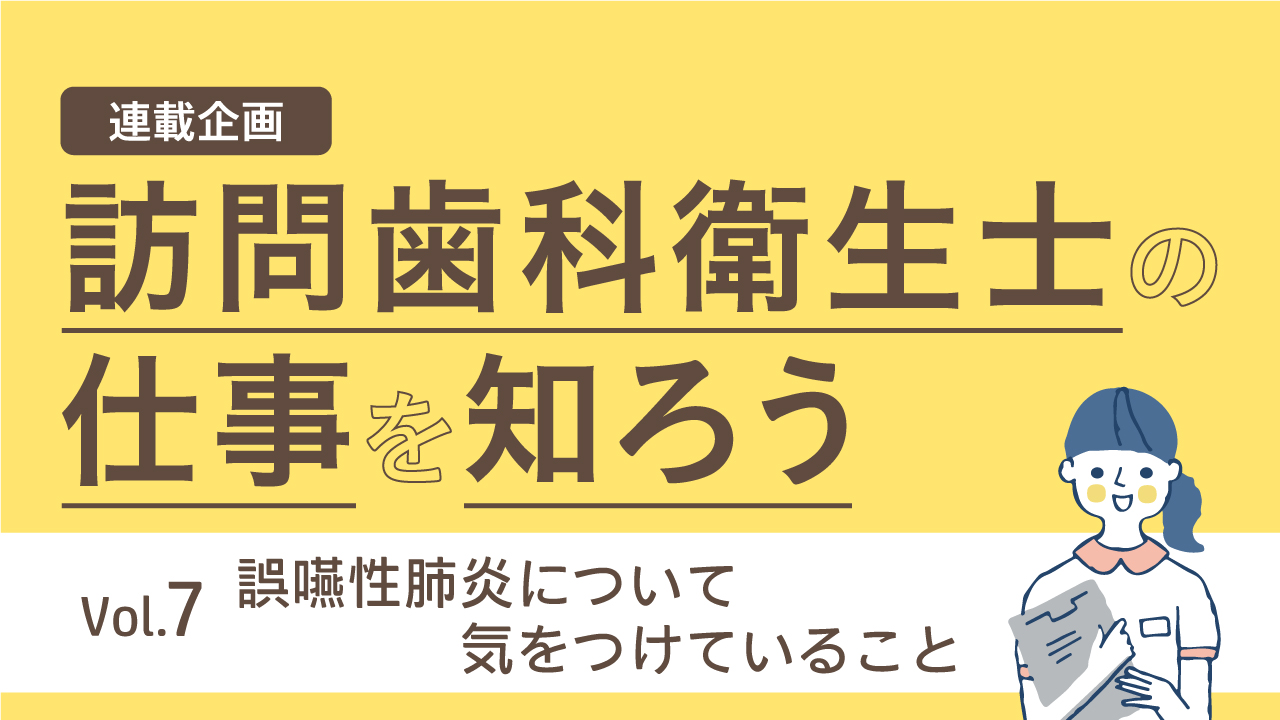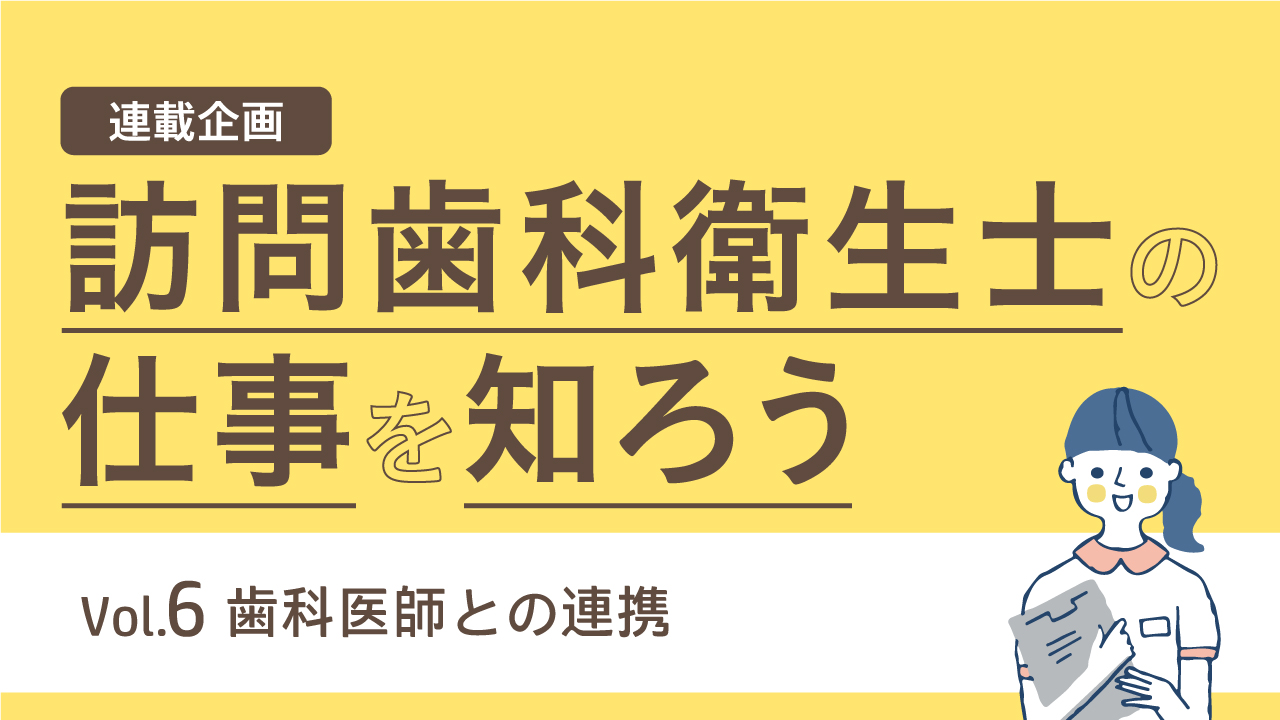【インタビュー】避けられぬ歯科訪問診療(第1回)
インタビュー
2022/06/27
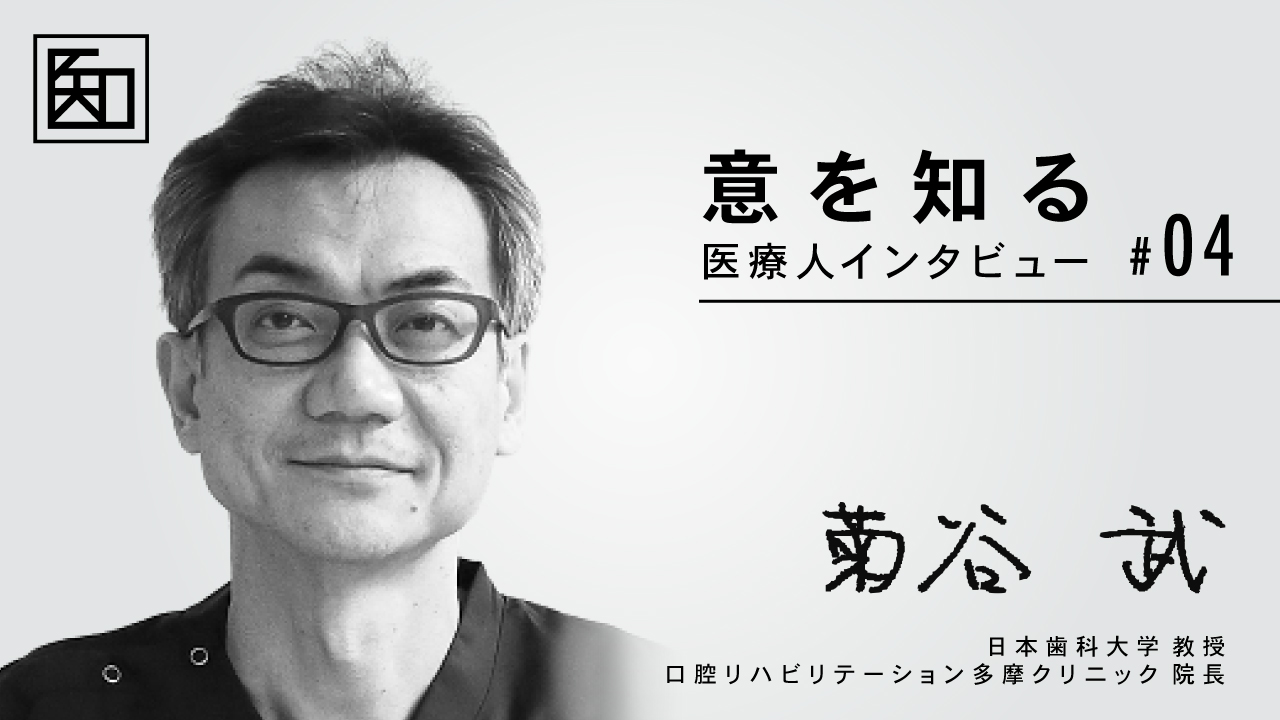
歯科医師 菊谷 武 先生
・日本歯科大学 教授
・口腔リハビリテーション多摩クリニック 院長
・大学院生命歯学研究科 臨床口腔機能学
――在宅療養者への歯科医療の問題点は
今の歯科医療は外来が途絶えるとそこで診療がストップします。歯科界で推奨される「かかりつけ歯科医」というのは、患者さんの口を最期まで管理することだと思います。であるなら、体調が悪くなって来院できなくなった患者さんに対し、訪問診療で最期まで口腔の管理をするべきと思います。一方、もし、 自らは歯科訪問診療が実施できないなら、それを地域で実施できる歯科医師にバトンタッチするというのが歯科医師としての絶対的な責任です。医科はそれがしっかりできているので、医科の先生方からすると歯科の取り組みの遅れは驚きと感じるようです。
このような状態ですから、歯科診療所に外来で通えなくなった期間が4、5年あいてから訪問診療になってもその間に口腔内は崩壊していて対応できない状態になっているケースが非常に多く見られます。また、半年、3カ月前まで外来に通っていたという患者さんでも違った問題も見られます。通院中に、在宅療養に適した口腔内への構築に向けた処置は何も講じられていないのです。訪問診療ではできることに制約があり、本来、通えなくなる可能性が高くなった時にしっかりとした対応をして、訪問診療でも対応できるように準備しておかないといけないのです。
そして、在宅療養者の訪問で挙げられる課題としては、口腔内が崩壊した状態で始めざるを得ない在宅診療です。この場合、多くは、X線撮影、高速切削機械が使えない、リスクが高いなど理由をつけて、やるべき診療がおざなりになっている状態が多く見られます。私は訪問診療において口腔ケアをするだけなら何もやらないに等しいと思っていて、咬合支持が維持されていない状態を放置しているとか、何を目的に行われているか理解ができない治療には警鐘を鳴らすべきだと考えています。
――歯科歯科連携がスムーズに運ばない理由はどのようなところにあるのでしょうか。
歯科は外来診療を基本として成り立ち発展してきた医療です。外来の患者さんは人生で一番輝いている状態で、頭もしっかりしているし、体も元気だし、お金もあるし、口も自由に動きます。日本のほぼ全ての歯科医師が診ているのはそうした外来の患者さんで、歯科医院に来なくなった患者さんにはあまり関心はありません。
しかし、歯科外来に通えなくなる期間は約10年あります。この10年間に口の状態がどう変わり、どう変化していくかを見ようともしないで、外来診療を語るのには違和感があります。
がんの終末期をきちんと知り、説明してくれない医師に、がんの治療をしてもらいたくないのと同じで、口の終末期が分かっていない歯科医師に口の診療をしてもらいたくないと患者さんは思うはずです。そのあたりを考えてほしいのです。
――在宅療養者への対応は日本の医療が避けて通れない課題です。歯科大学教育も変わる必要があると思うのですが。
日本は65歳以上の人口が4割を占め、厚労省の統計によれば歯科受診者の2人に1人は65歳以上で、そのうちの半数近くを75歳以上が占めています。そして、そのうちの多くは早々に、歯科医院に来院できなくなります。
そういう人たちを全部切り捨てていいのかという話です。われわれが守っていくべき現場は在宅であり、武器は訪問診療です。それを特定の人たちだけに押し付けてはいけないと思います。そして、適切な対応ができているのかどうかにも大きな疑問が残ります。
しかし、現状において在宅療養者の診療をやっている教員がいる大学は、ごく少数です。大学病院から患者宅に訪問診療に行くというのはさらにまれで、行っているとすれば施設とか大学併設の医科病院ではないでしょうか?つまり、学生たちが開業後、本当に取り組んでほしい地域包括ケアにおける歯科医療とか多職種連携を大学では学べないということです。
本校が口腔リハビリテーション多摩クリニックを設立した最大の理由は、学生のうちにきちんとした在宅診療を見せるためです。そして、そのためにはまず教員が経験しないといけないと考えたからです。大学附属病院ではそれができなかったからです。

――在宅療養者の歯科訪問診療を学ぶ上で大事なことは。
まず大前提として認識しておくことは、訪問で対応する患者さんは人生の最終段階を迎えている人たちだということです。外来の患者さんであれば、「あと何十年は大丈夫」といって治療がスタートしますが、訪問では歯を何カ月、何年持たせるかの目利きが大事になります。噛めるための良い義歯を作るという話ではなく、口腔内の状況や全身の健康状態を診て判断できなければいけないのですが、そのための教科書がないのです。
「高齢者歯科」というタイトルの本は、歯科医師国家試験の出題基準にこの分野が取り入れられたこともあって何冊か出ていますが、在宅歯科診療の教科書はまだないと言って良いでしょう。
【インタビュー】避けられぬ歯科訪問診療(第2回に続く)
【歯科訪問診療を総合的・体系的に学ぶ】歯科訪問診療総合研修講座 -導入コース-

※日本歯科新聞 2022年3月15日号掲載記事
この記事の関連記事

【インタビュー】根拠ある感染対策を目指す 何を継続し、何をなくすか
大毛 宏喜 氏 広島大学病院感染症科教授 新型コロナウイル…
大毛 宏喜 氏 広島大学病院感染症科教授 新型コロナウイル…
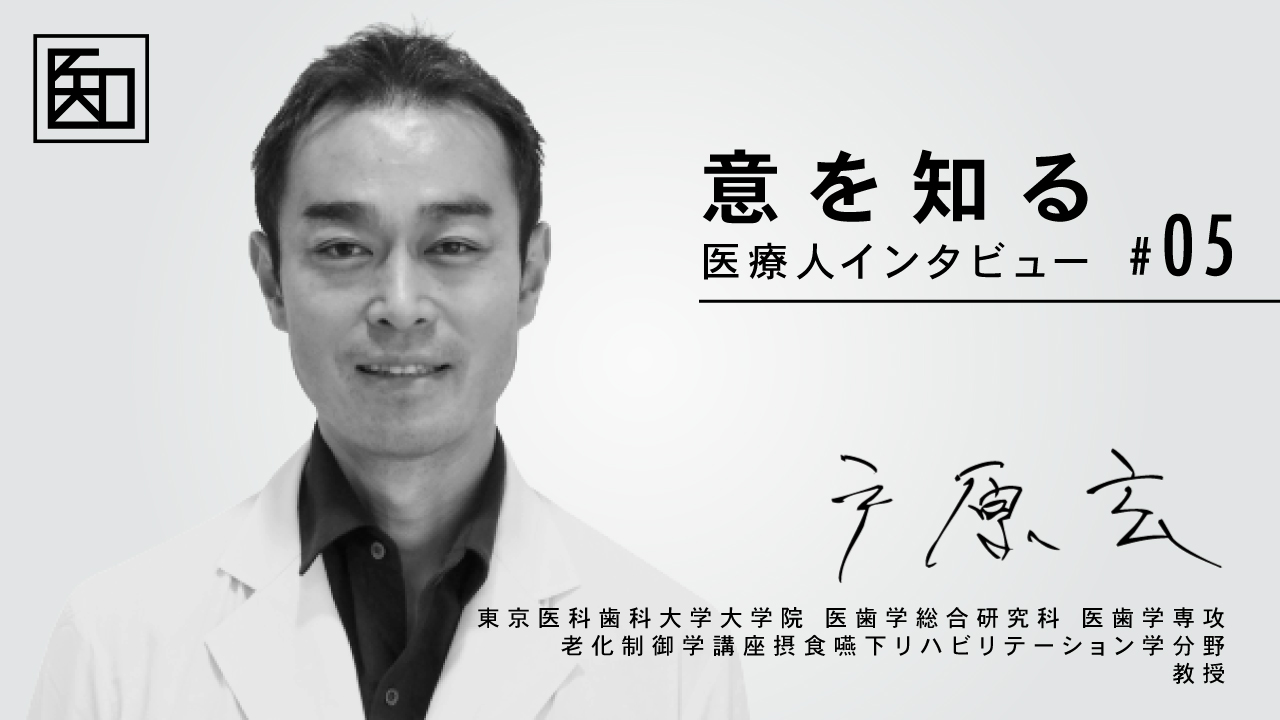
【インタビュー】問われる摂食嚥下障害への対応 /「人生100年時代」の歯科医療
戸原 玄 氏 東京医科歯科大学大学院 教授 「人生100年…
戸原 玄 氏 東京医科歯科大学大学院 教授 「人生100年…
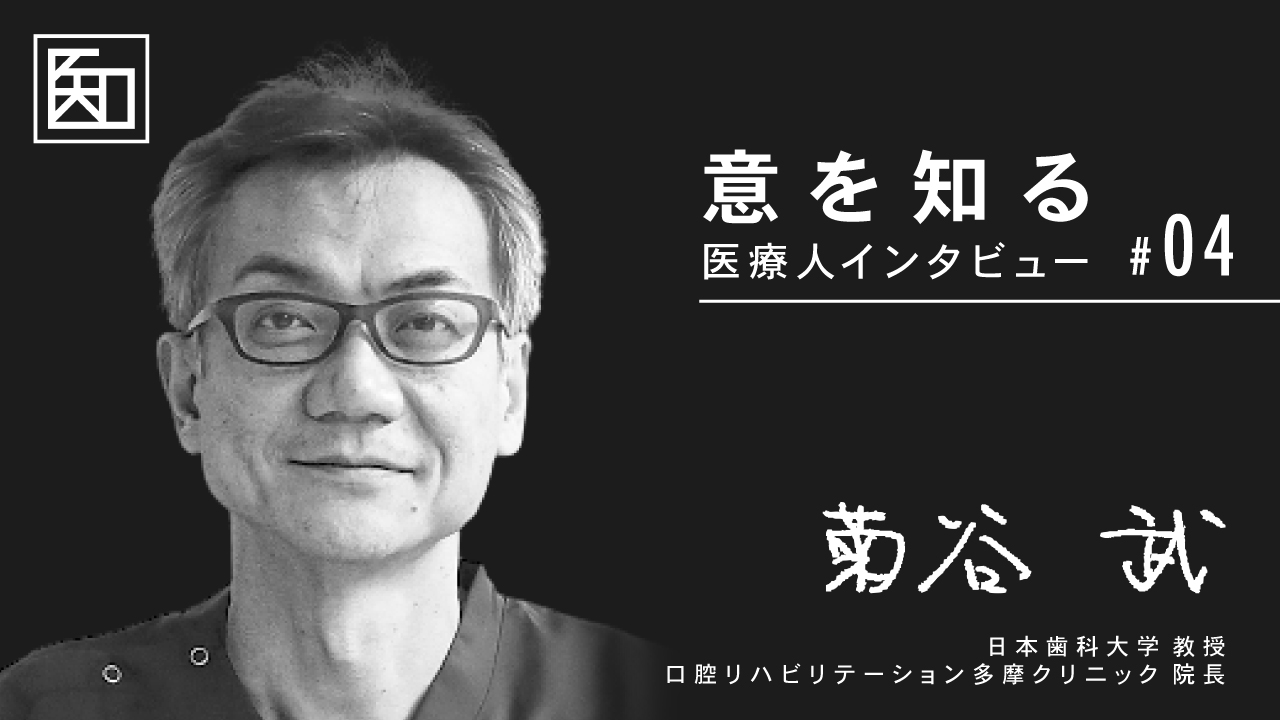
【インタビュー】避けられぬ歯科訪問診療(第2回)
歯科医師 菊谷 武 先生・日本歯科大学 教授・口腔リハビリテ…
歯科医師 菊谷 武 先生・日本歯科大学 教授・口腔リハビリテ…
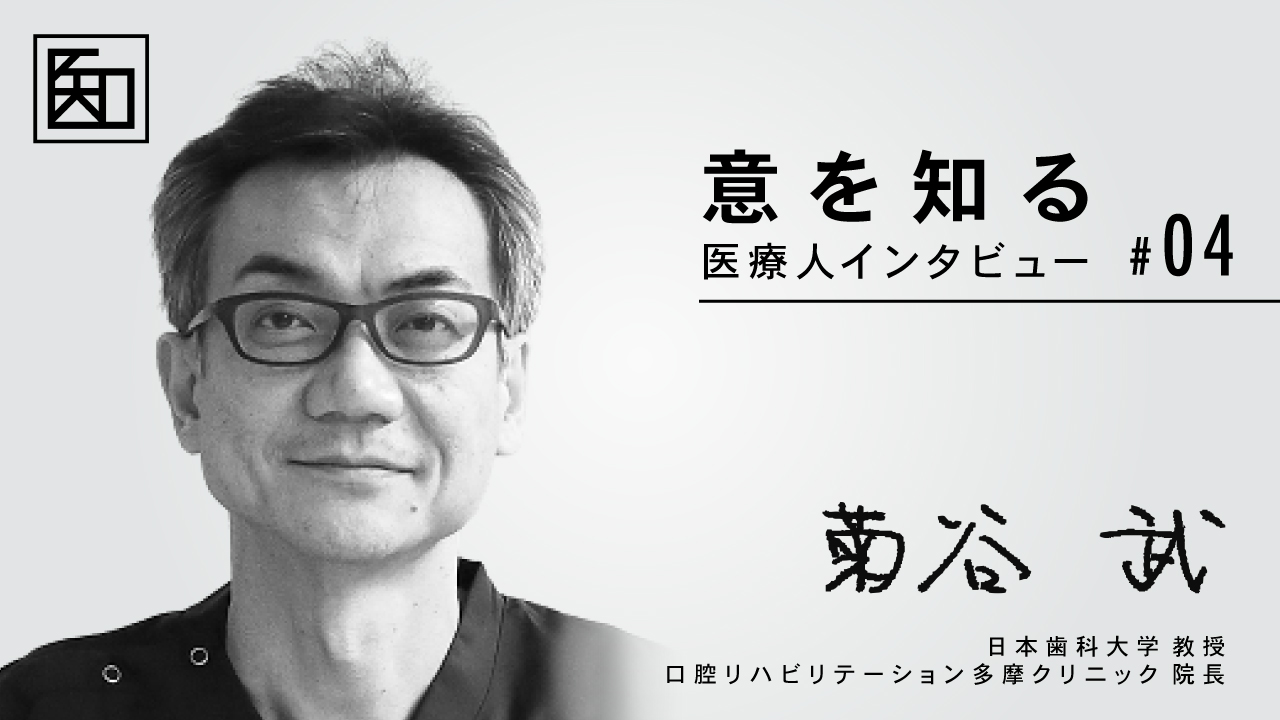
【インタビュー】避けられぬ歯科訪問診療(第1回)
歯科医師 菊谷 武 先生・日本歯科大学 教授・口腔リハビリテ…
歯科医師 菊谷 武 先生・日本歯科大学 教授・口腔リハビリテ…
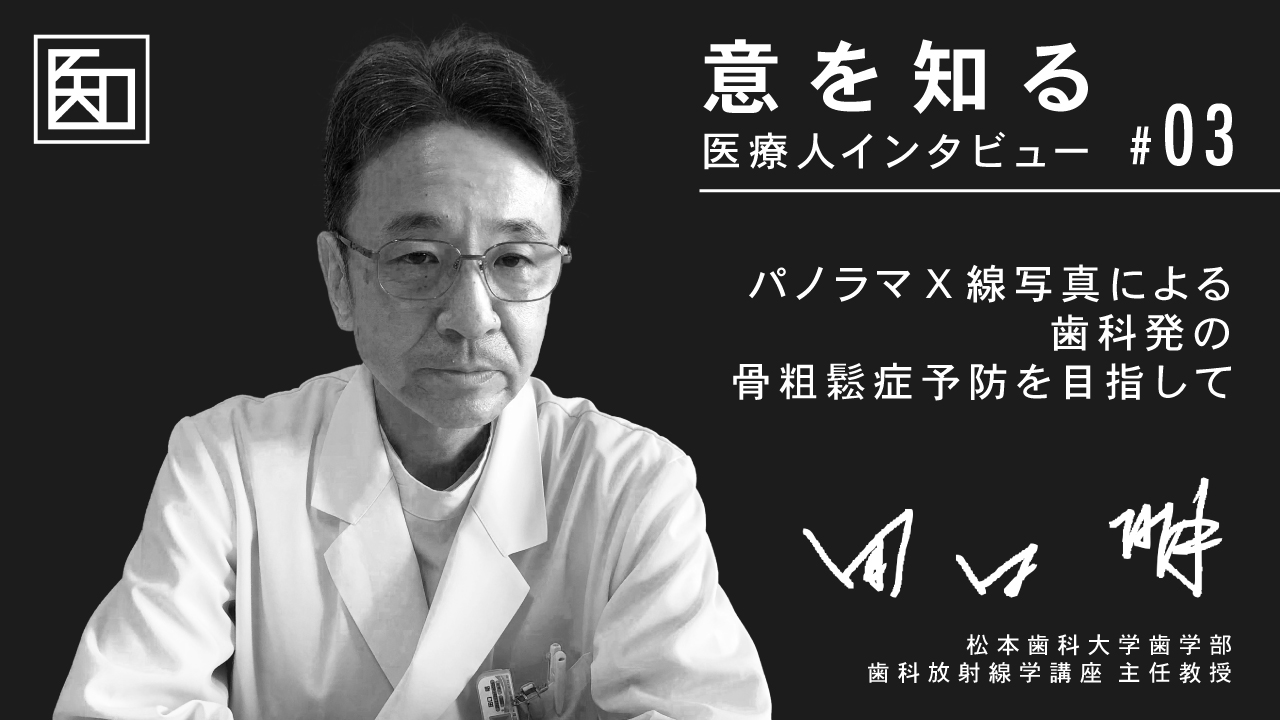
【インタビュー】骨粗鬆症と歯科との関係(第2回)
歯科医師 田口明 先生・松本歯科大学歯学部歯科放射線学講座 …
歯科医師 田口明 先生・松本歯科大学歯学部歯科放射線学講座 …
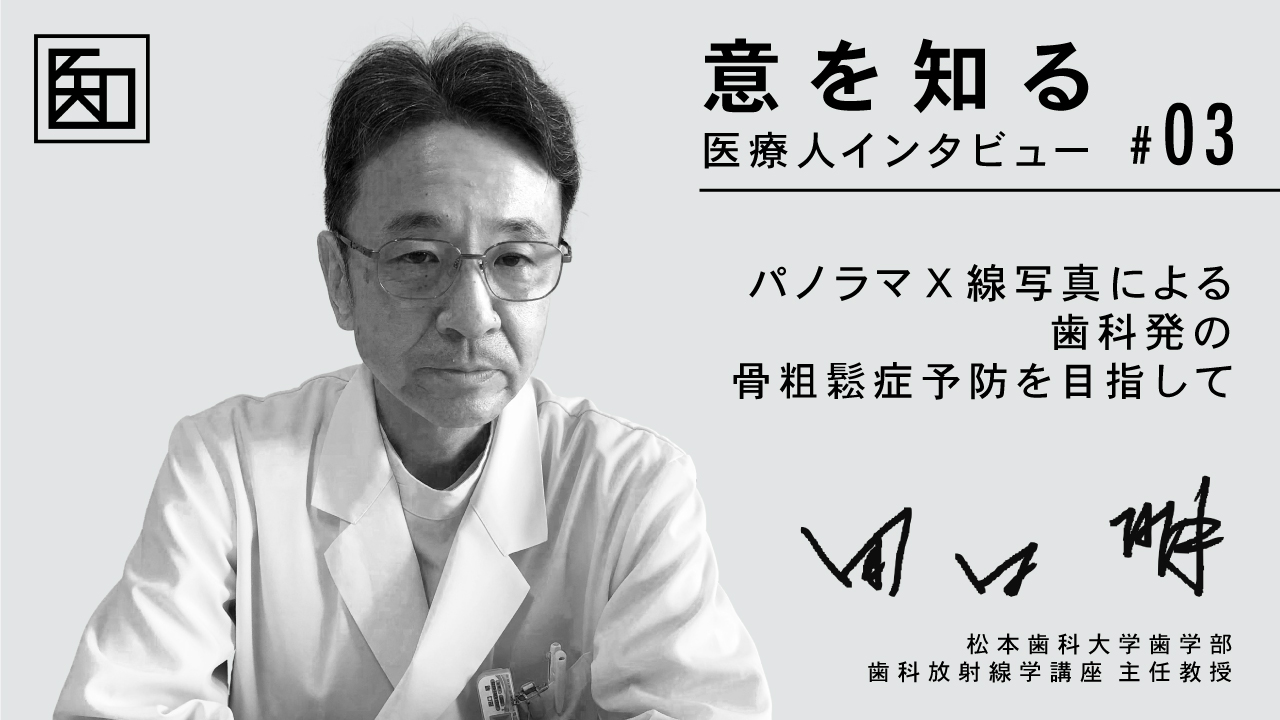
【インタビュー】骨粗鬆症と歯科との関係(第1回)
歯科医師 田口明 先生・松本歯科大学歯学部歯科放射線学講座 …
歯科医師 田口明 先生・松本歯科大学歯学部歯科放射線学講座 …
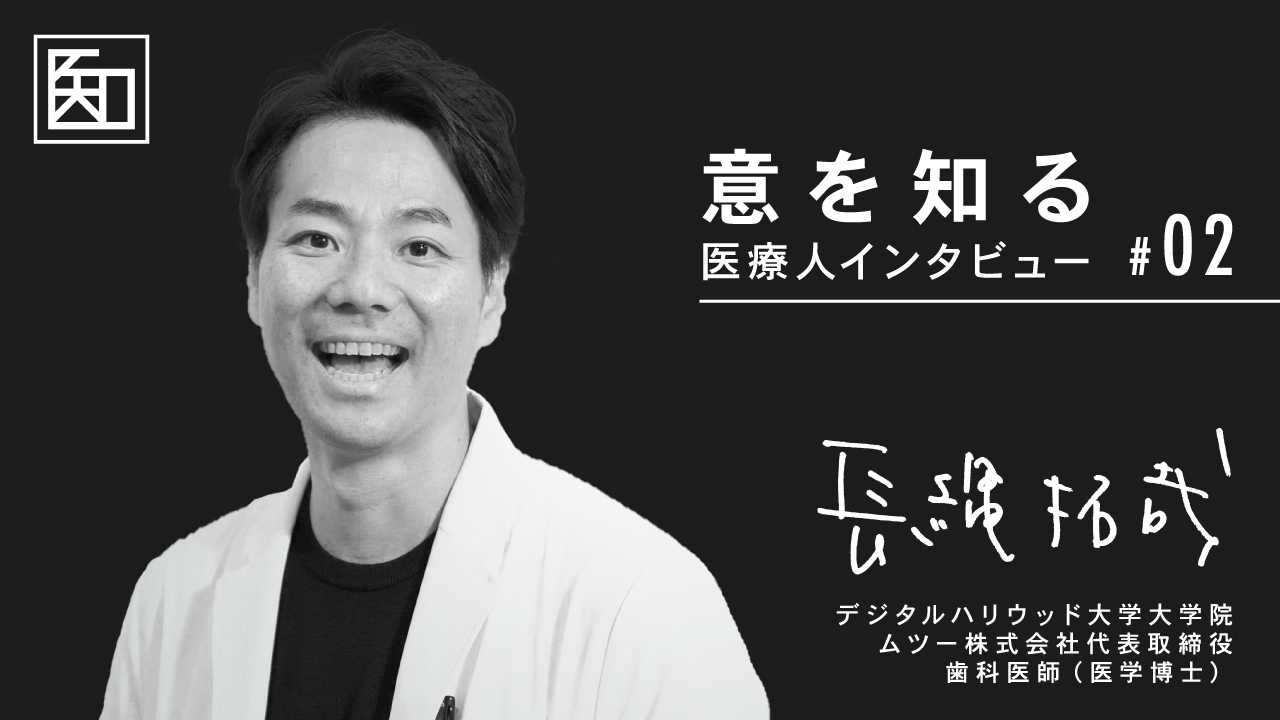
【インタビュー】現代美術、オンライン診療、BOC 医療/+αで社会課題の解決を目指す(第2回)
歯科医師 長縄拓哉 先生 歯科医師(医学博士) デジタルハリ…
歯科医師 長縄拓哉 先生 歯科医師(医学博士) デジタルハリ…
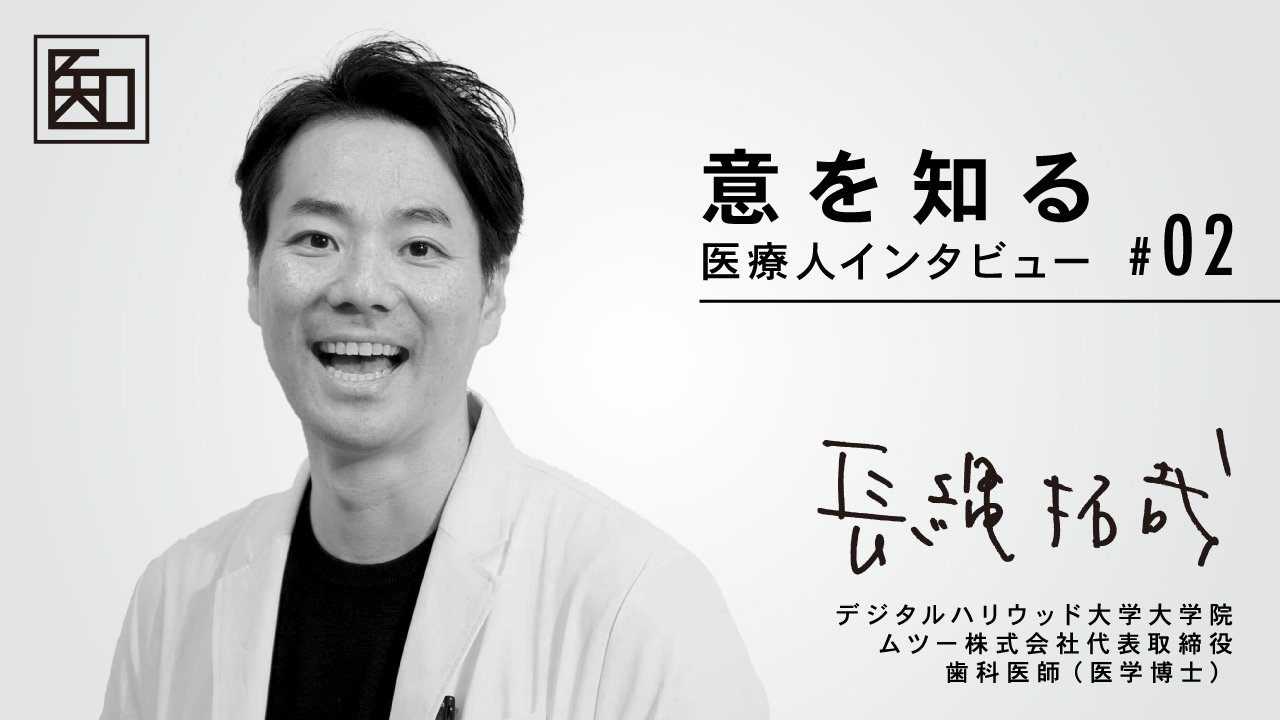
【インタビュー】現代美術、オンライン診療、BOC 医療/+αで社会課題の解決を目指す(第1回)
歯科医師 長縄拓哉 先生 歯科医師(医学博士) デジタルハリ…
歯科医師 長縄拓哉 先生 歯科医師(医学博士) デジタルハリ…