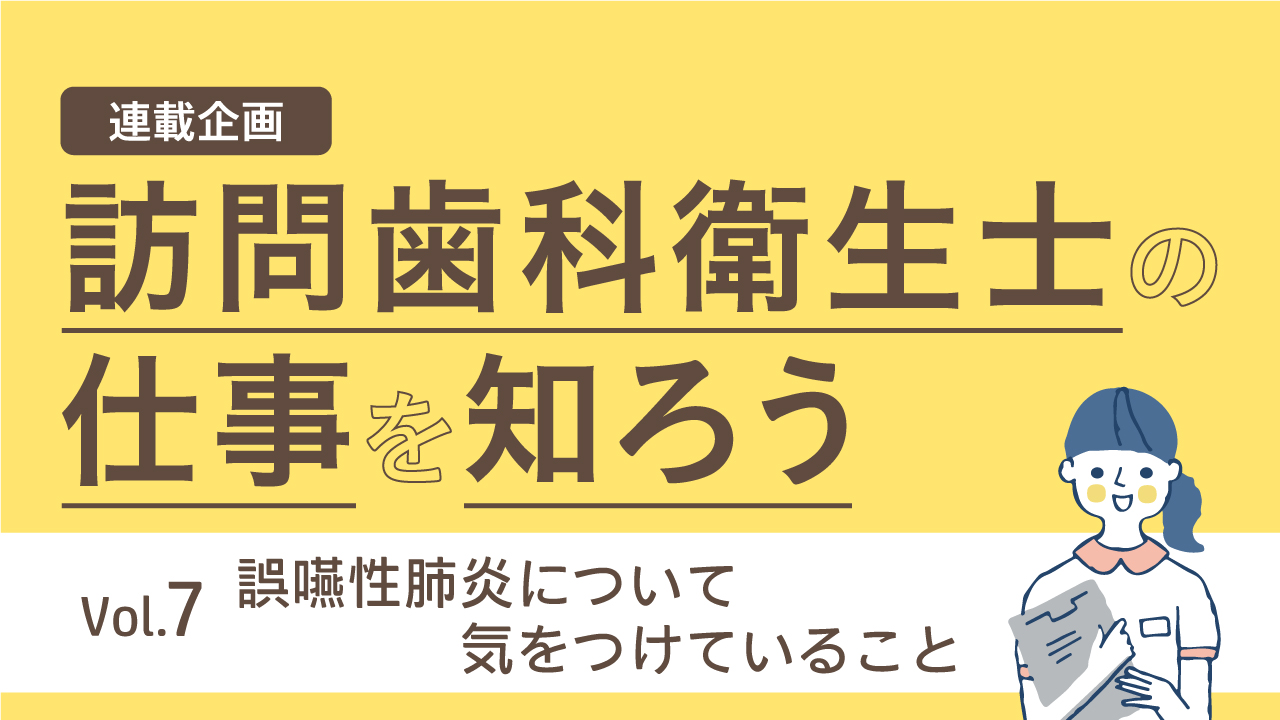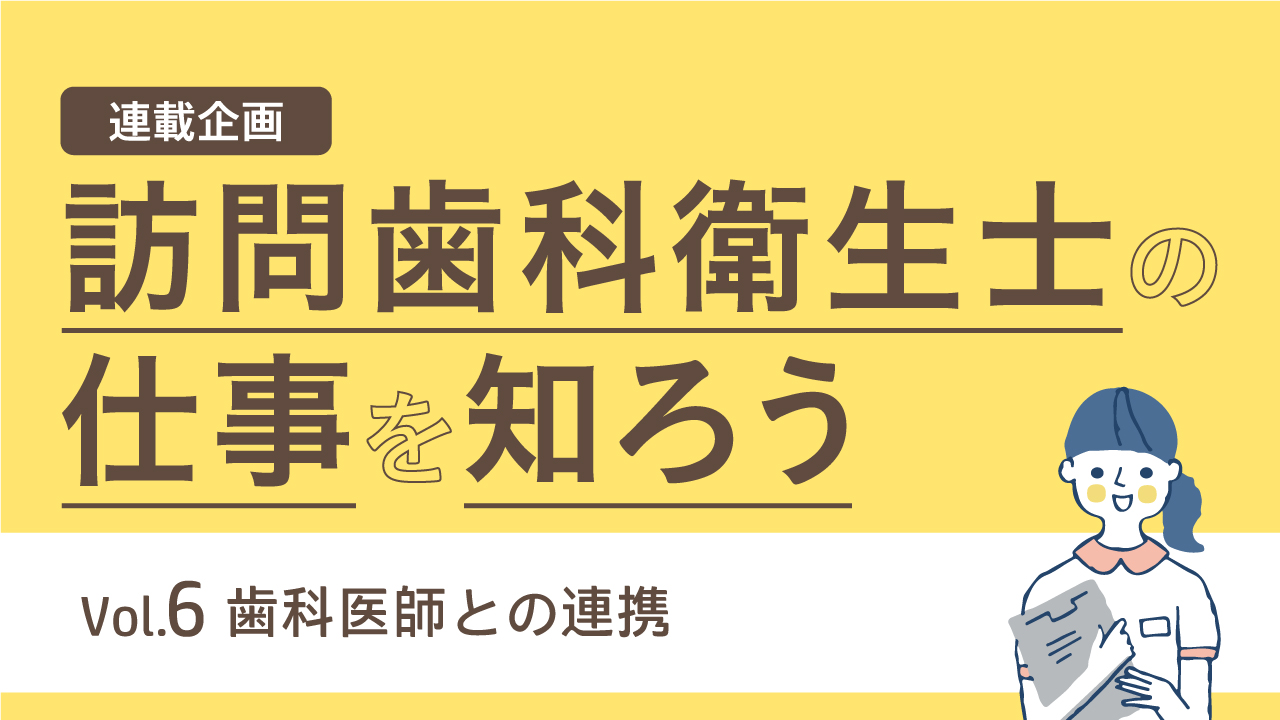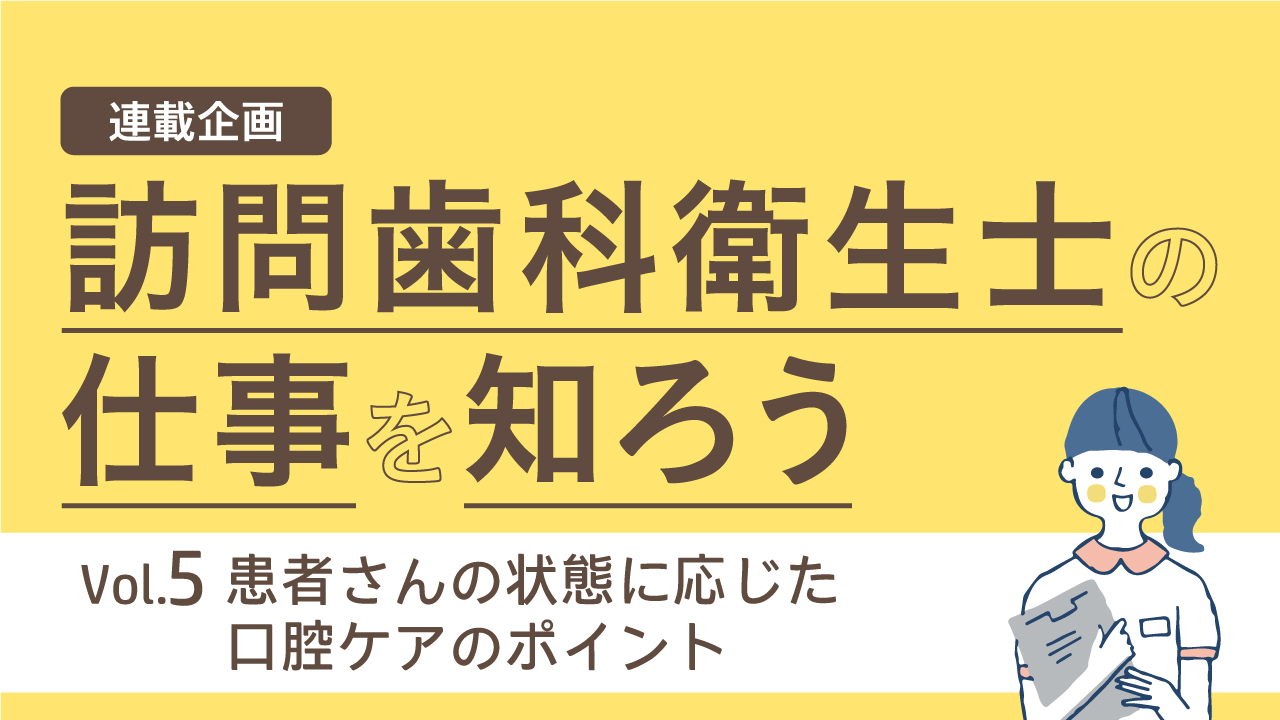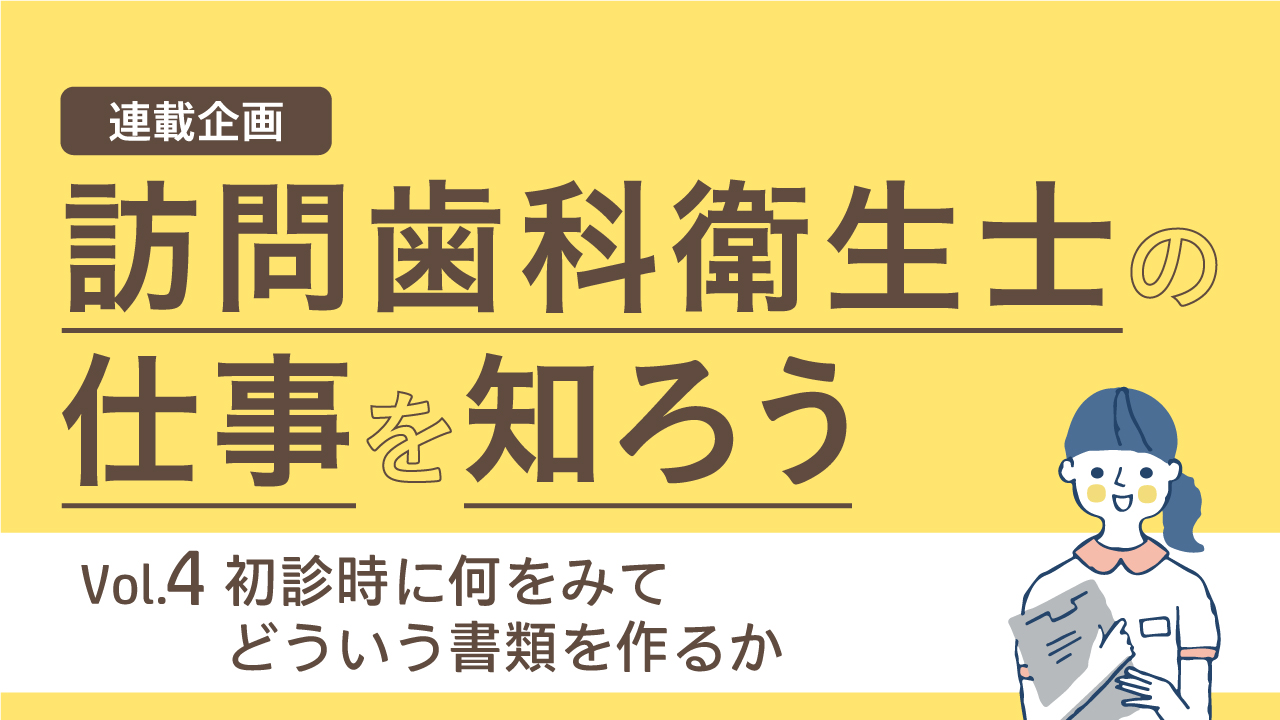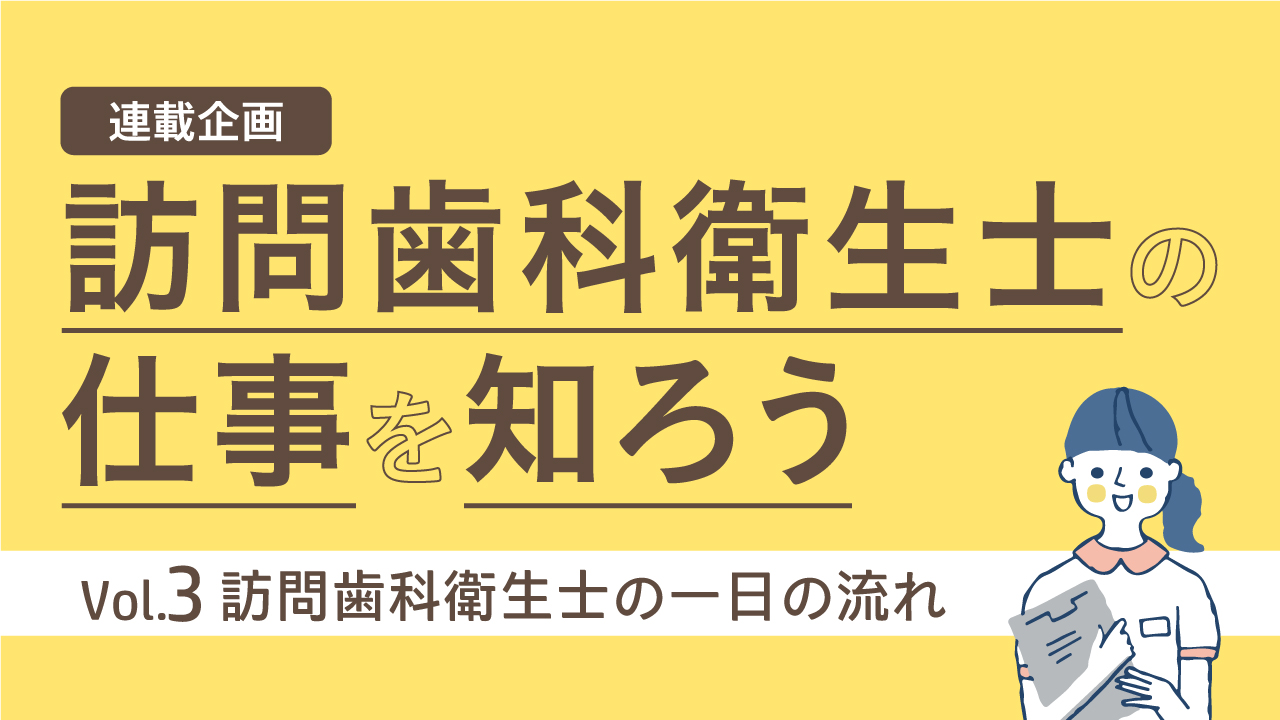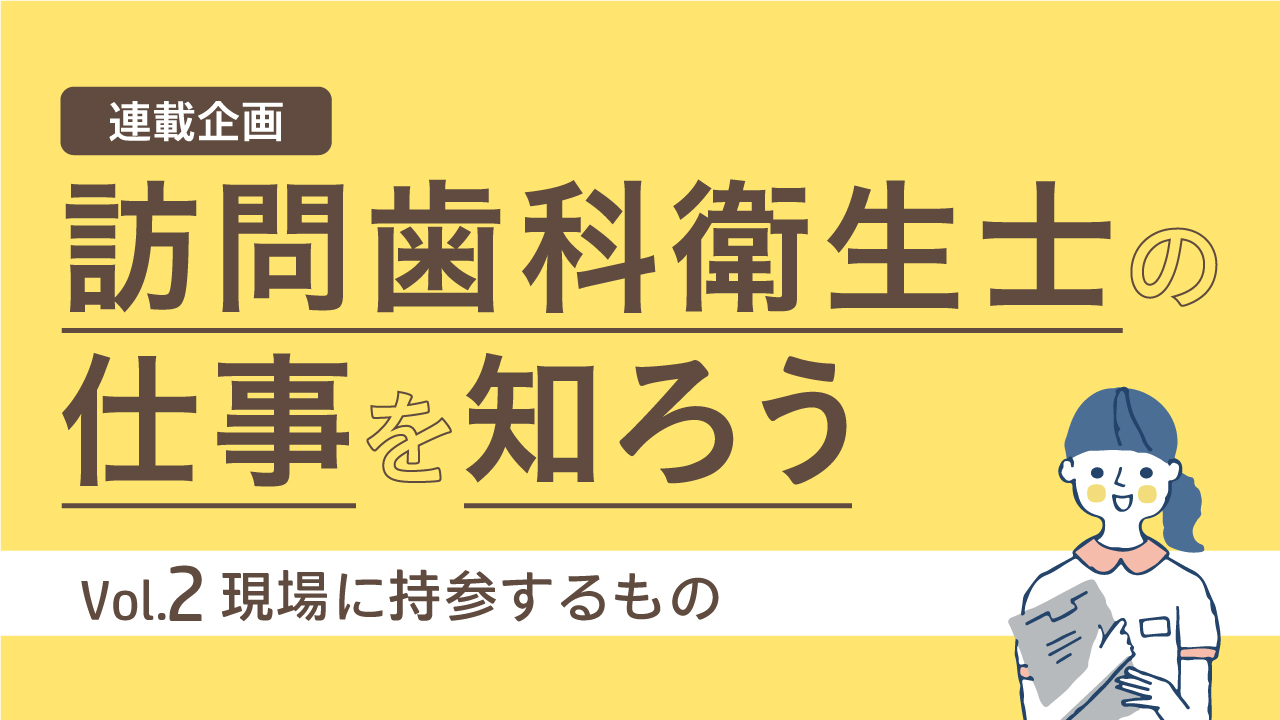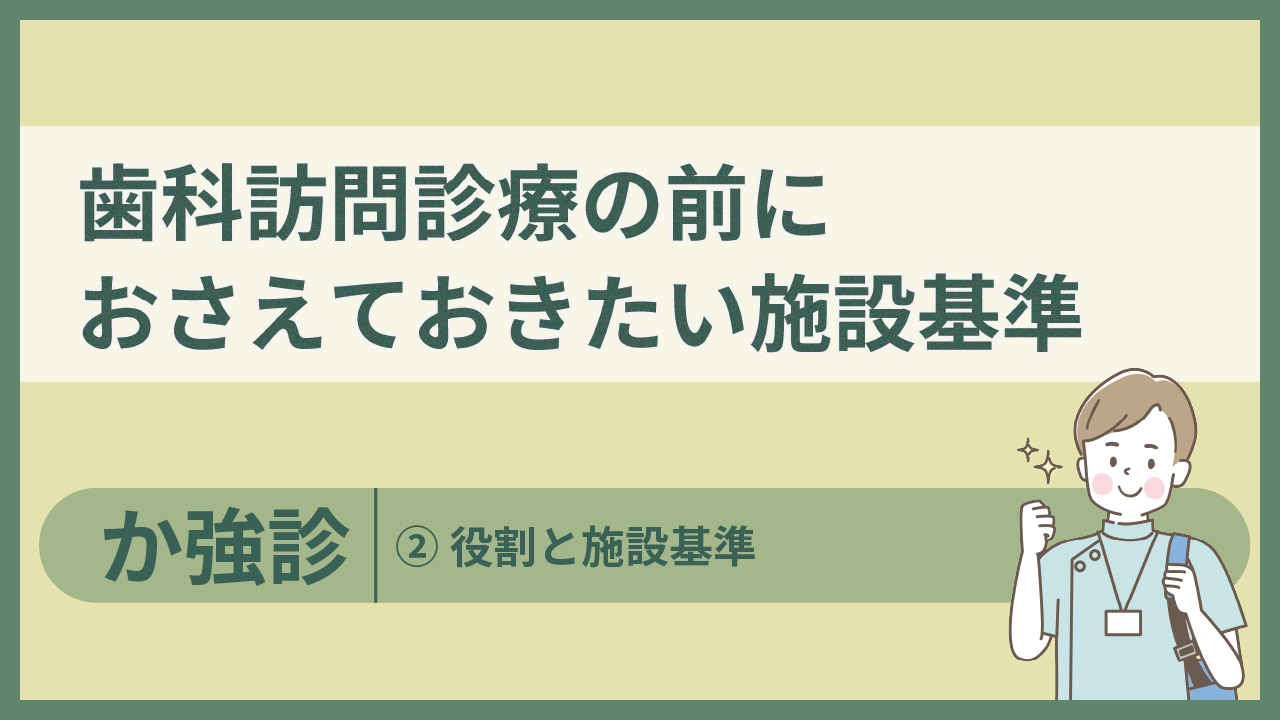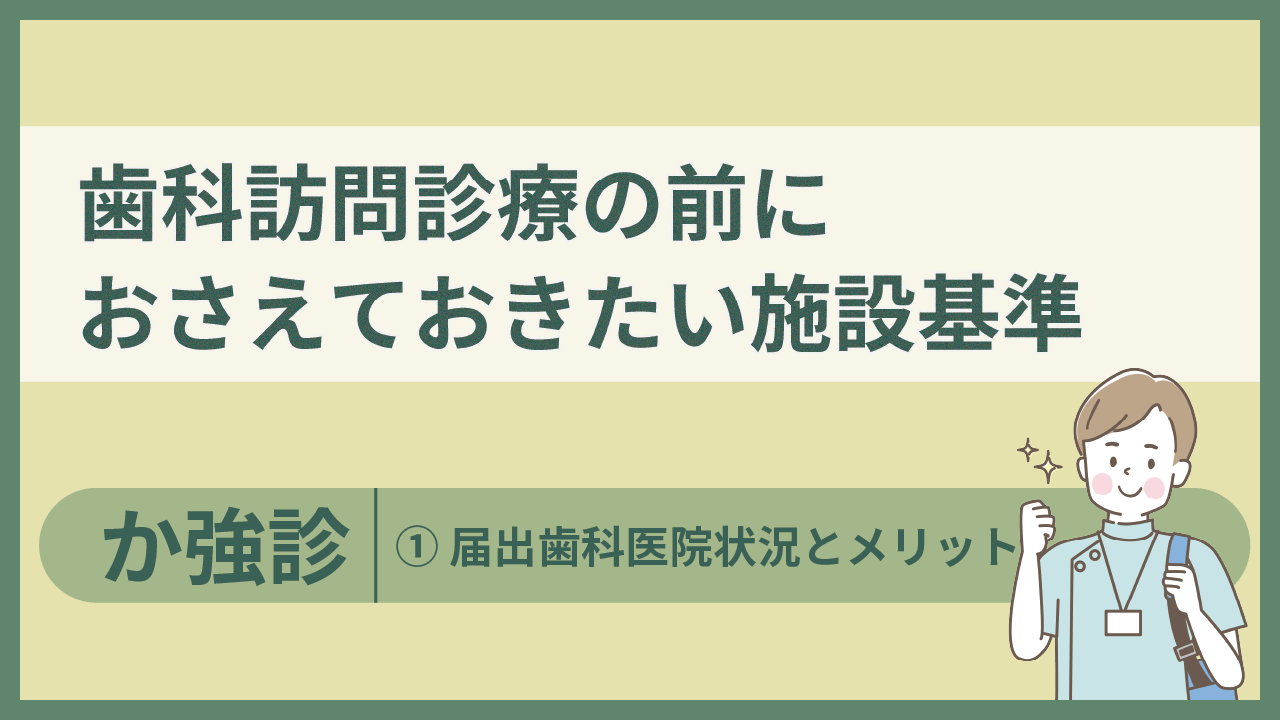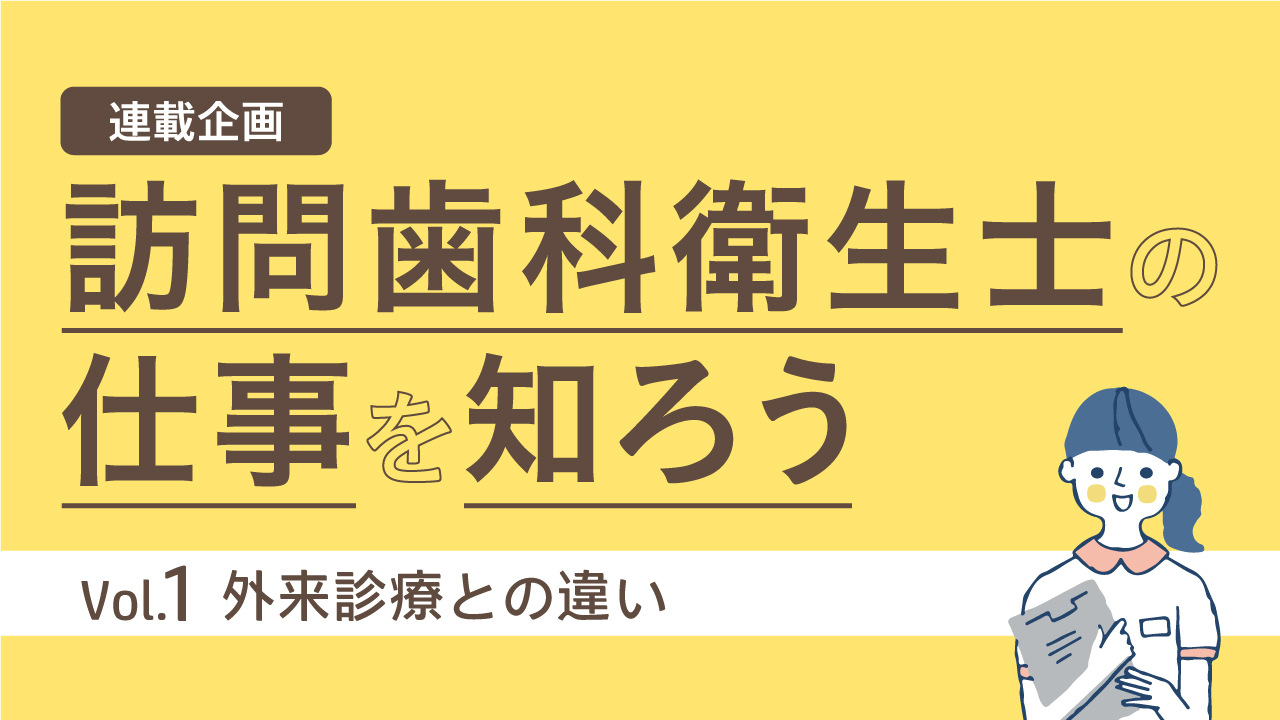【インタビュー】多職種連携は、地域の人を知ることから始めよう(第2回)
インタビュー
2021/02/15
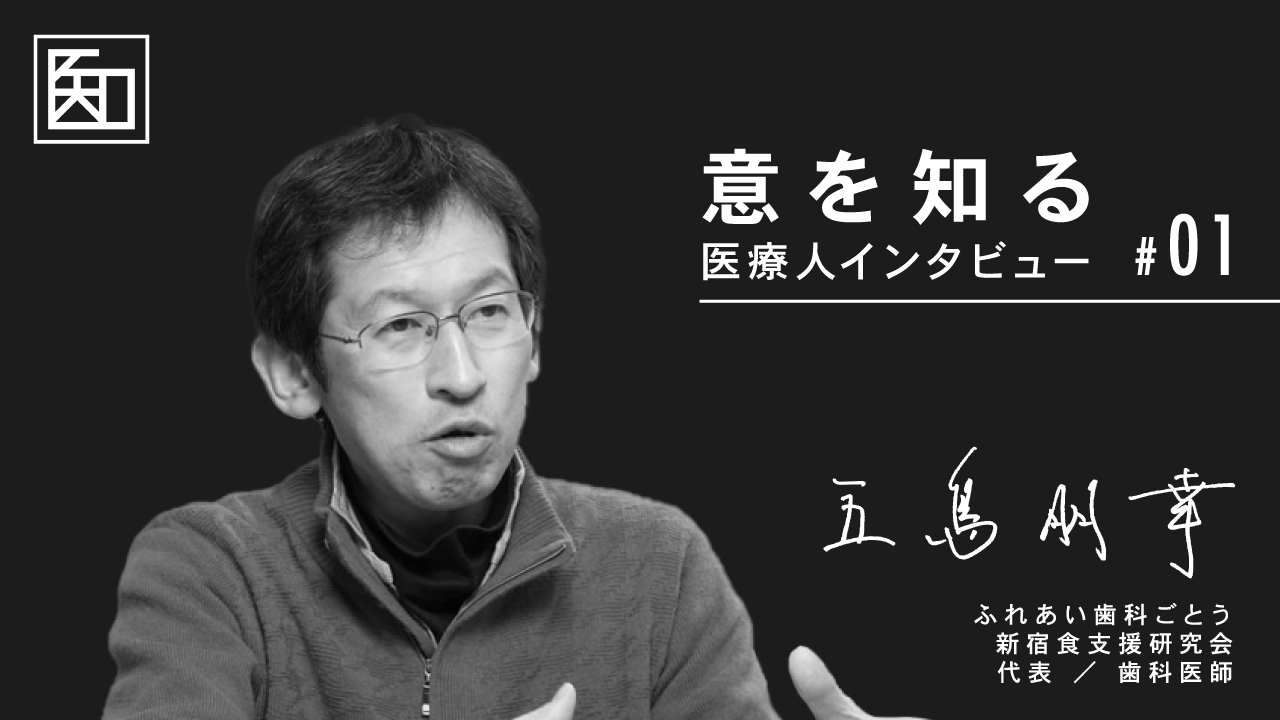
歯科医師 五島朋幸 先生 ・ふれあい歯科ごとう・新宿食支援研究会 代表 ・日本歯科大学附属病院口腔リハビリテーション科臨床准教授 ・日本歯科大学東京短期大学歯科衛生士科講師 ・東京医科歯科大学非常勤講師 ・慶応義塾大学非常勤講師
多職種連携が必要と言われて久しいが、実践できている方はまだまだ多くは無いと思われる。「新宿食支援研究会」は23職種160名が所属し、東京・新宿にて地域食支援・多職種連携を実践しているプロフェッショナル集団。課題ごとに設けられた数人規模のワーキンググループが有機的に活動しながら、日々「最期まで口から食べる」ために何ができるかを追求している。全国でも有数の団体であり、他の食支援・多職種連携グループとの連携も深めている。
代表である歯科医師 五島朋幸先生に、食支援・多職種連携に取り組まれた経緯やポイントを聞いた。
■MTK&H®による「最期まで口から食べられる街」づくり —— 多職種の方々は、具体的にどのような役割を果たされるのでしょうか?
私は、食支援には具体的に以下が必要だと考えます。 1. 全身の管理 2. 栄養管理 3. 口腔環境整備(義歯製作、調整) 4. 口腔ケア 5. 摂食、嚥下リハビリ 6. 食事形態の調整 7. 食事作り 8. 食事姿勢の調整 9. 食事介助 10. 食事環境調整 各専門職がそれぞれの役割りを担いますが、全てに関与できる専門職はいません。だからこそ地域の中では、多くの職種が関わって食支援をする必要があります。これが地域食支援だと思います。そこでは、誰が、誰に対して、何をするのか?がとても重要となります...
続きを読むには会員登録(無料)が必要です
この記事の関連記事

【インタビュー】根拠ある感染対策を目指す 何を継続し、何をなくすか
大毛 宏喜 氏 広島大学病院感染症科教授 新型コロナウイル…
大毛 宏喜 氏 広島大学病院感染症科教授 新型コロナウイル…
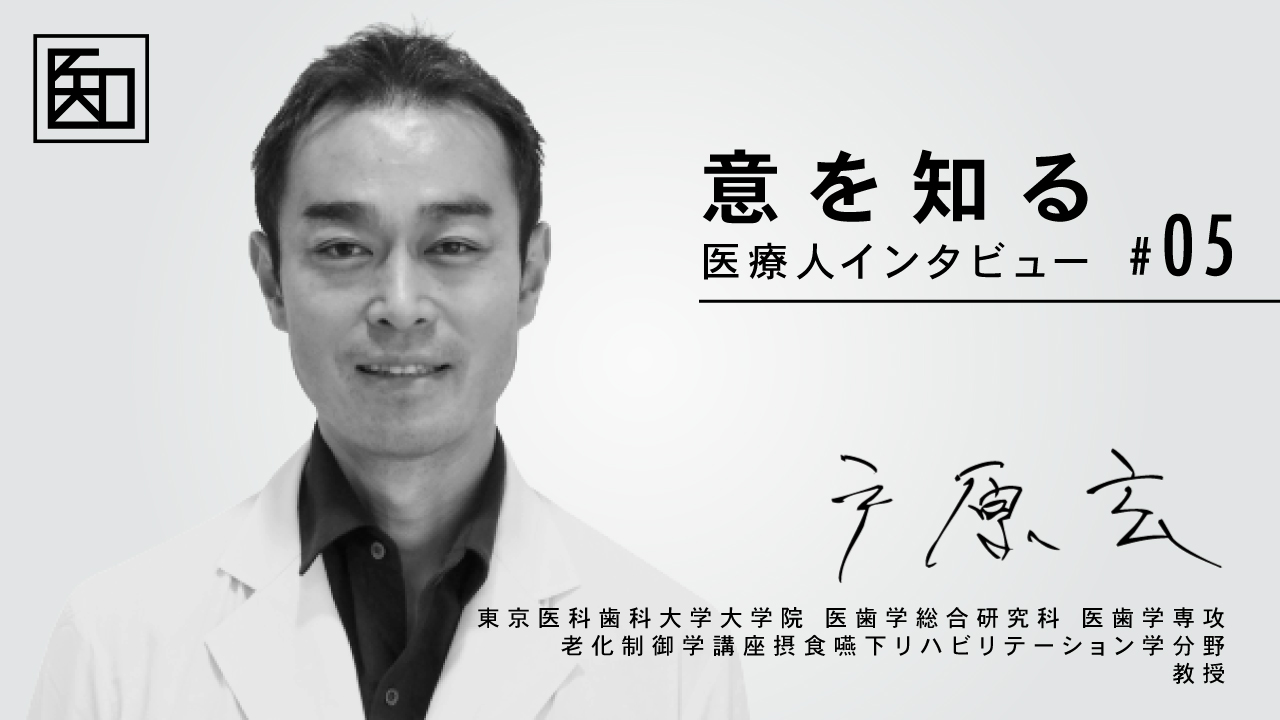
【インタビュー】問われる摂食嚥下障害への対応 /「人生100年時代」の歯科医療
戸原 玄 氏 東京医科歯科大学大学院 教授 「人生100年…
戸原 玄 氏 東京医科歯科大学大学院 教授 「人生100年…
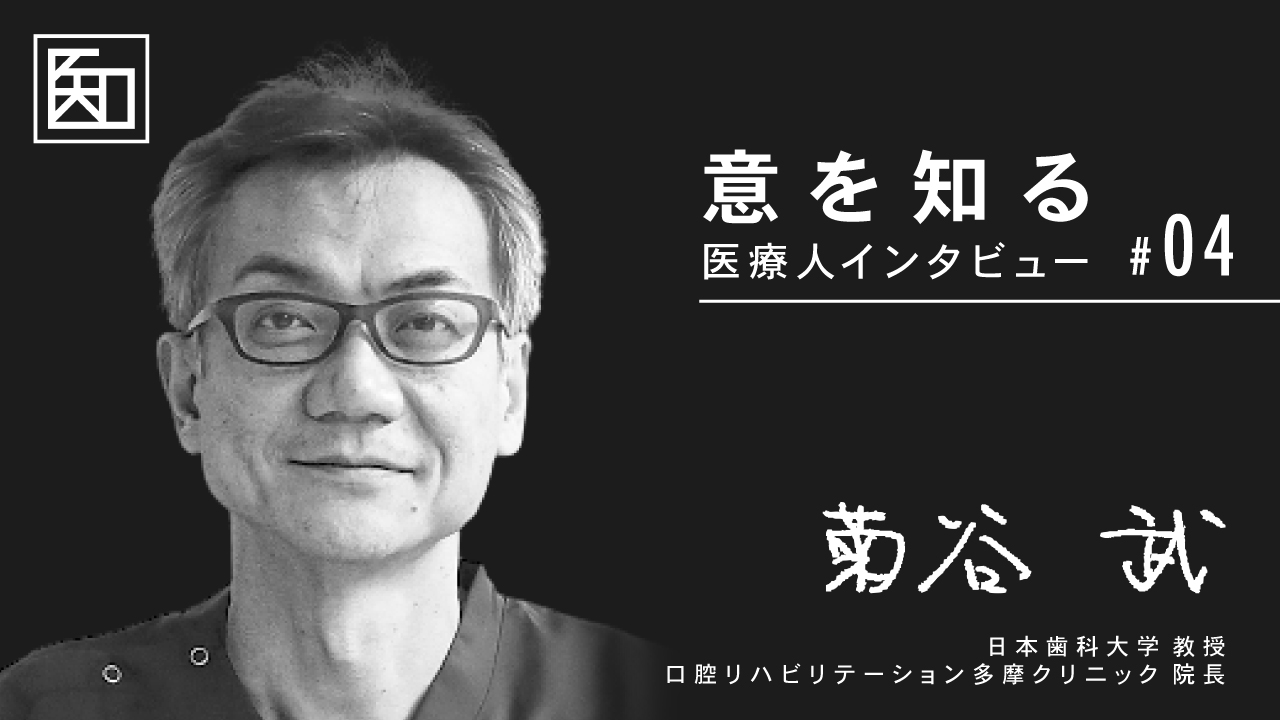
【インタビュー】避けられぬ歯科訪問診療(第2回)
歯科医師 菊谷 武 先生・日本歯科大学 教授・口腔リハビリテ…
歯科医師 菊谷 武 先生・日本歯科大学 教授・口腔リハビリテ…
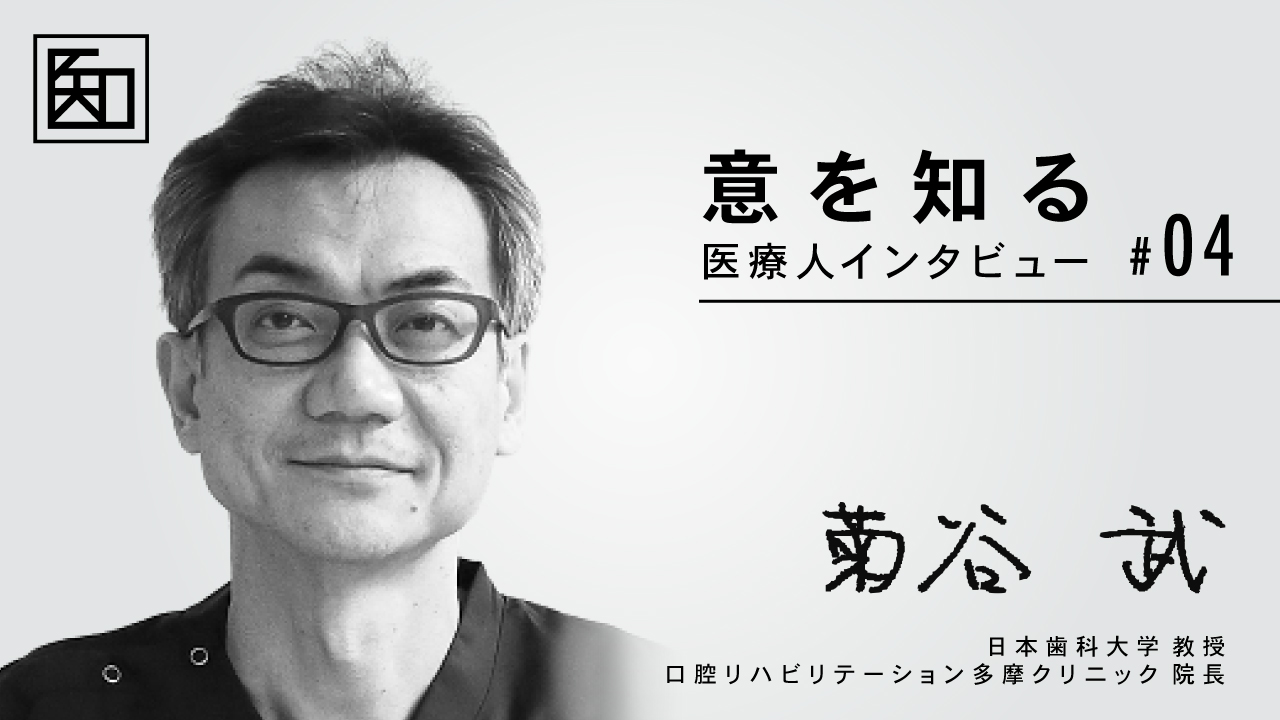
【インタビュー】避けられぬ歯科訪問診療(第1回)
歯科医師 菊谷 武 先生・日本歯科大学 教授・口腔リハビリテ…
歯科医師 菊谷 武 先生・日本歯科大学 教授・口腔リハビリテ…
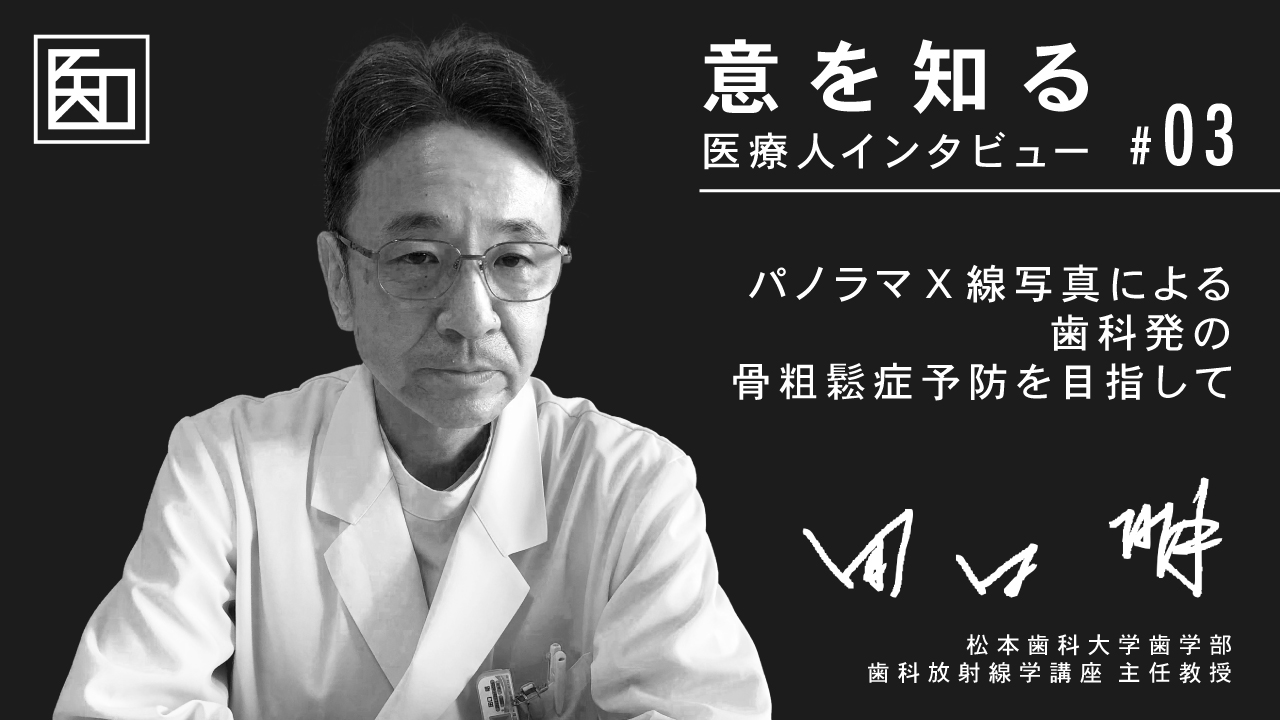
【インタビュー】骨粗鬆症と歯科との関係(第2回)
歯科医師 田口明 先生・松本歯科大学歯学部歯科放射線学講座 …
歯科医師 田口明 先生・松本歯科大学歯学部歯科放射線学講座 …
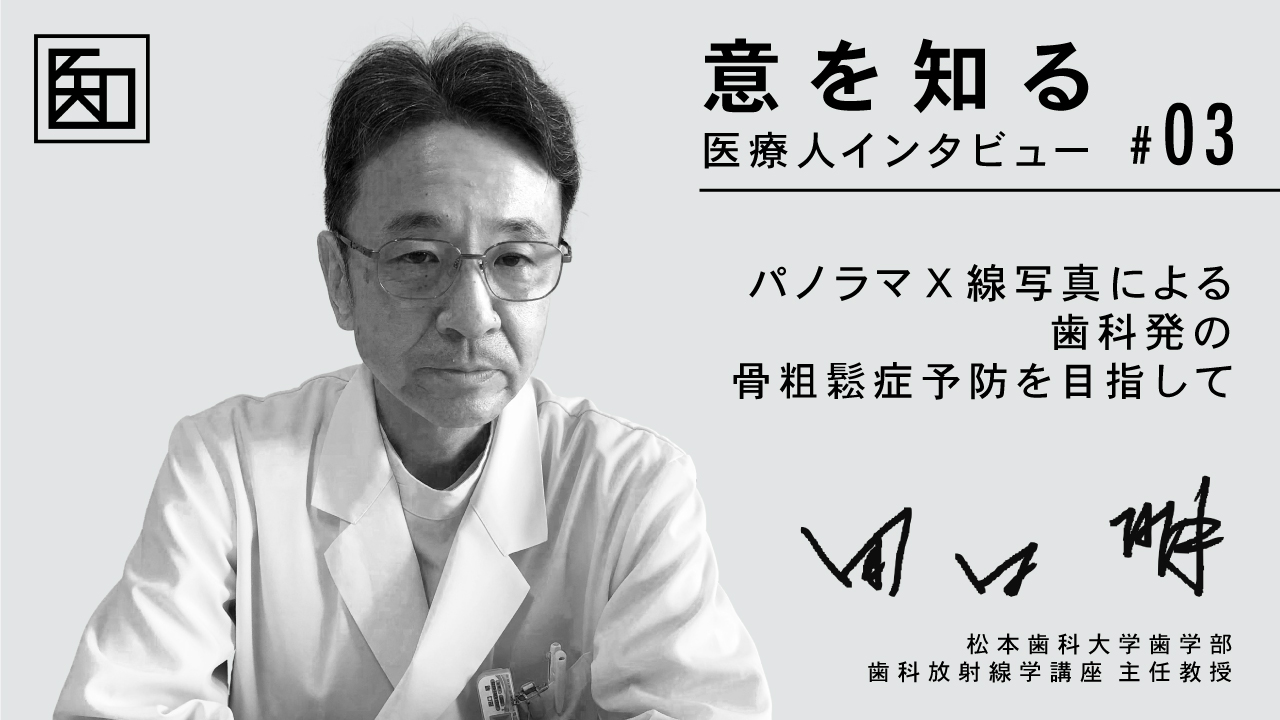
【インタビュー】骨粗鬆症と歯科との関係(第1回)
歯科医師 田口明 先生・松本歯科大学歯学部歯科放射線学講座 …
歯科医師 田口明 先生・松本歯科大学歯学部歯科放射線学講座 …
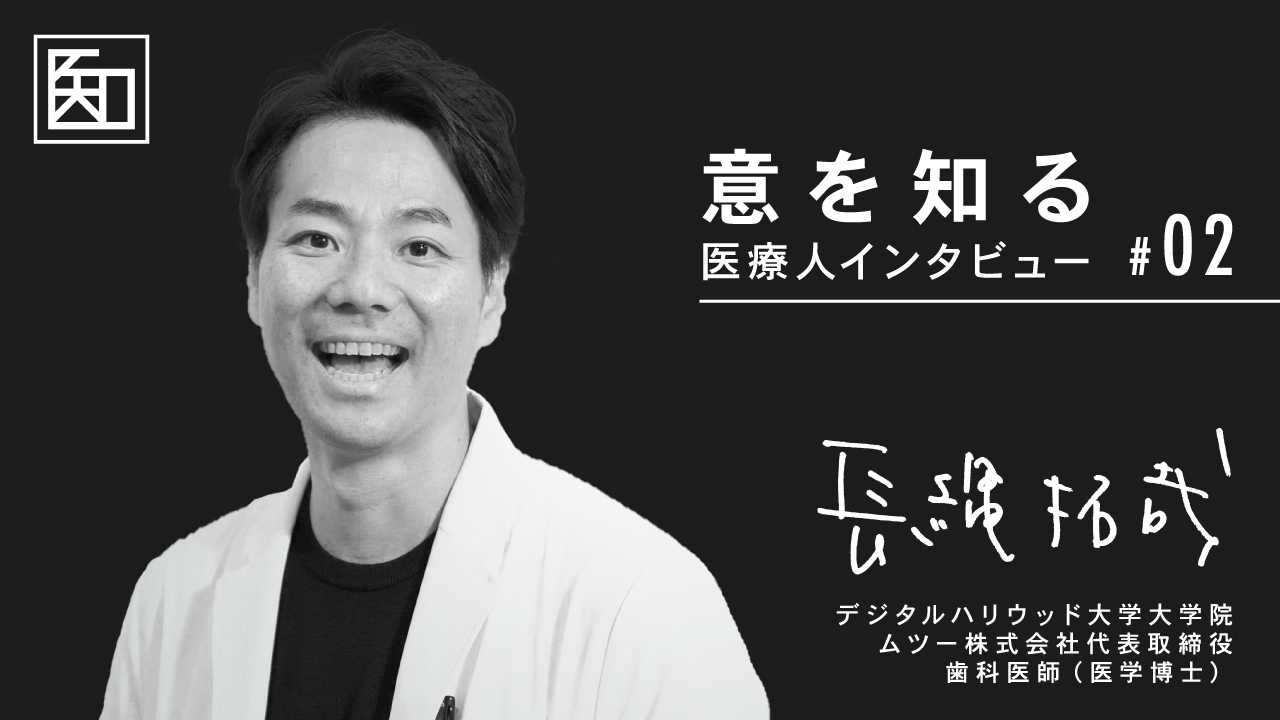
【インタビュー】現代美術、オンライン診療、BOC 医療/+αで社会課題の解決を目指す(第2回)
歯科医師 長縄拓哉 先生 歯科医師(医学博士) デジタルハリ…
歯科医師 長縄拓哉 先生 歯科医師(医学博士) デジタルハリ…
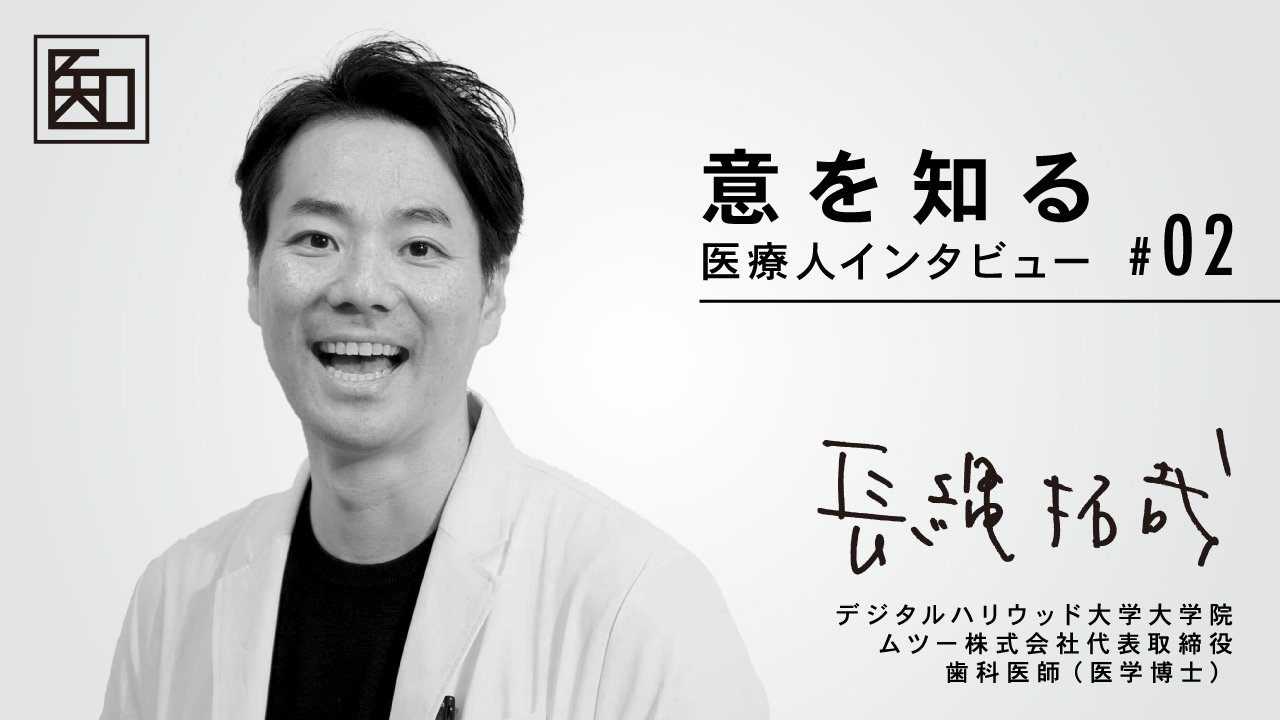
【インタビュー】現代美術、オンライン診療、BOC 医療/+αで社会課題の解決を目指す(第1回)
歯科医師 長縄拓哉 先生 歯科医師(医学博士) デジタルハリ…
歯科医師 長縄拓哉 先生 歯科医師(医学博士) デジタルハリ…