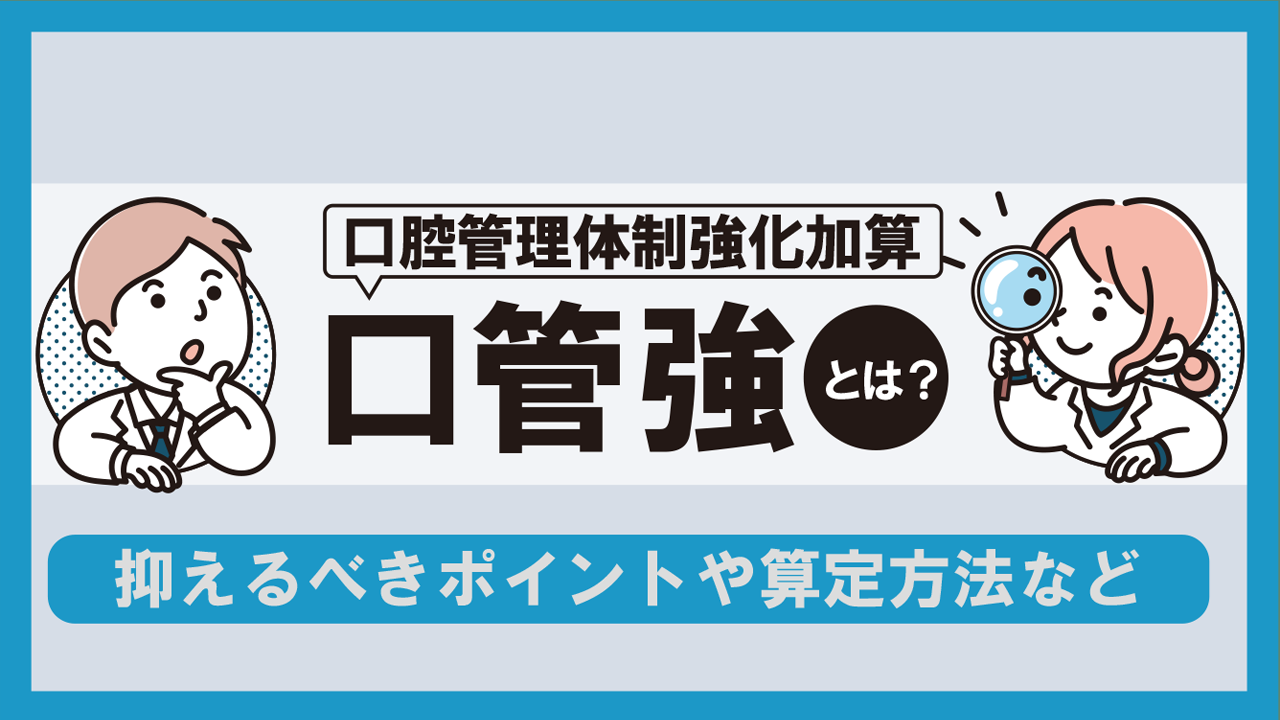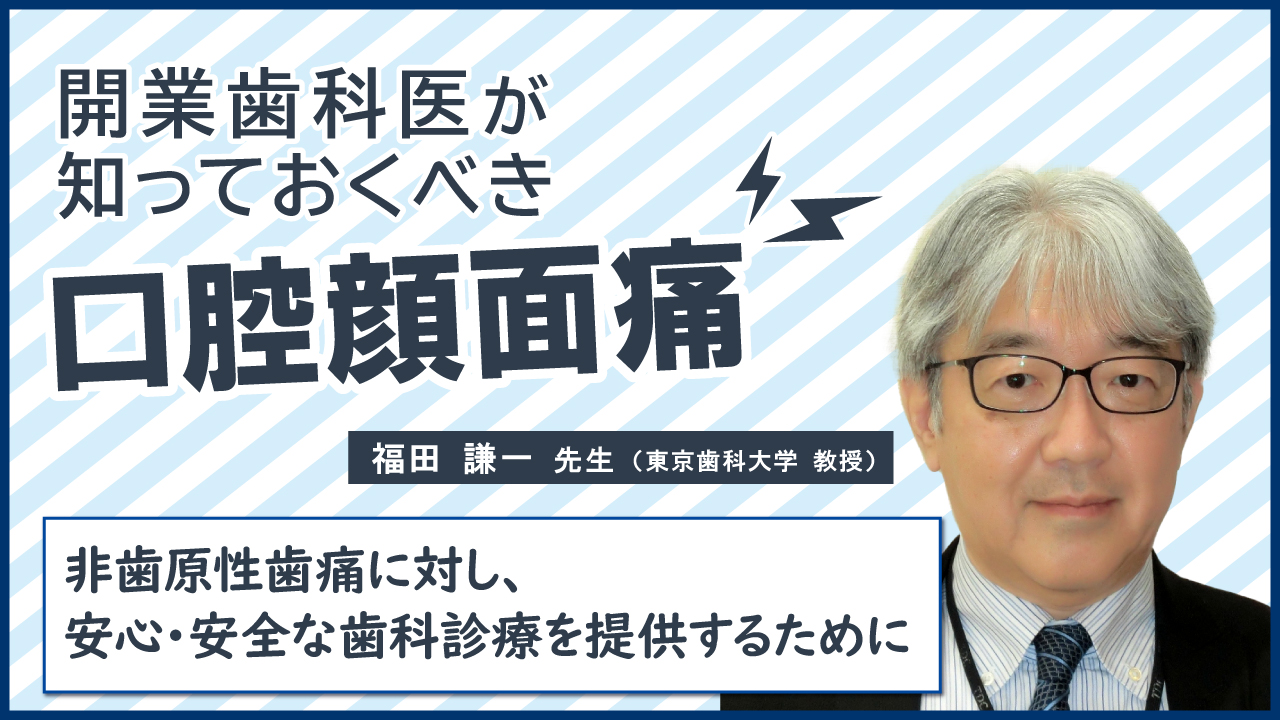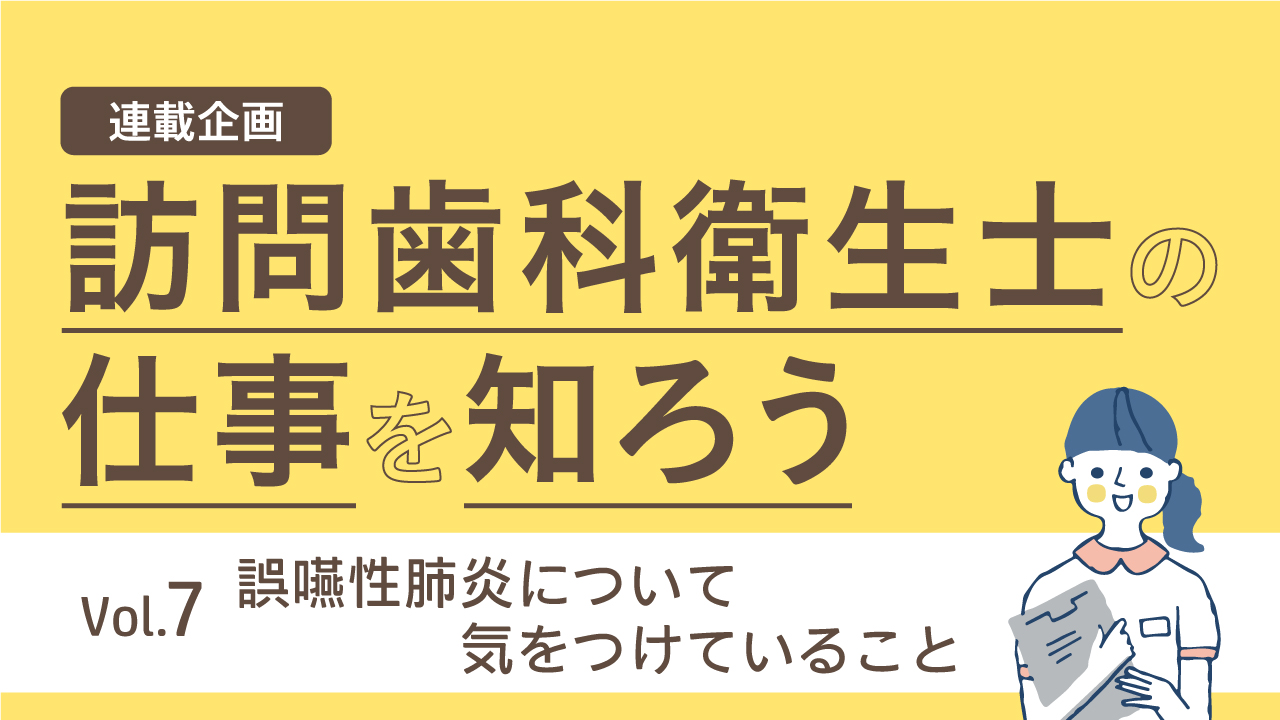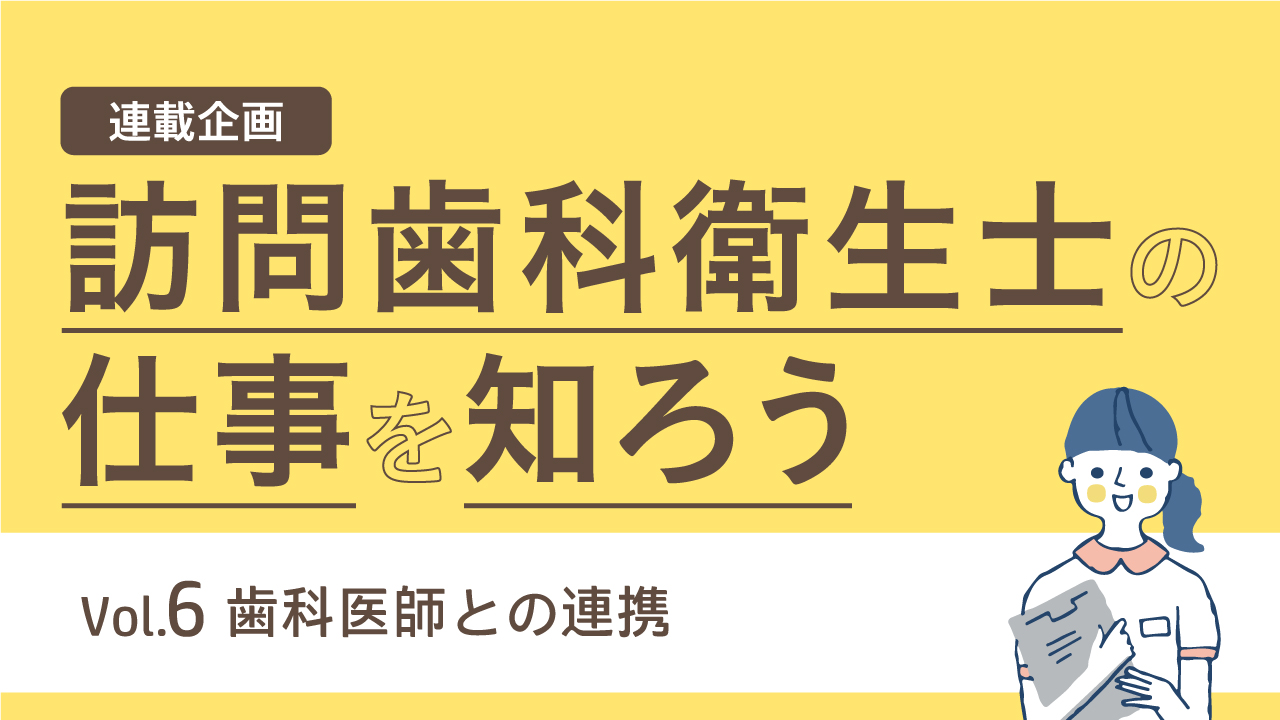今さら聞けない地域包括ケアシステムのこと ~Vol.6 地域包括ケア会議と歯科衛生士~
特集
2023/11/30
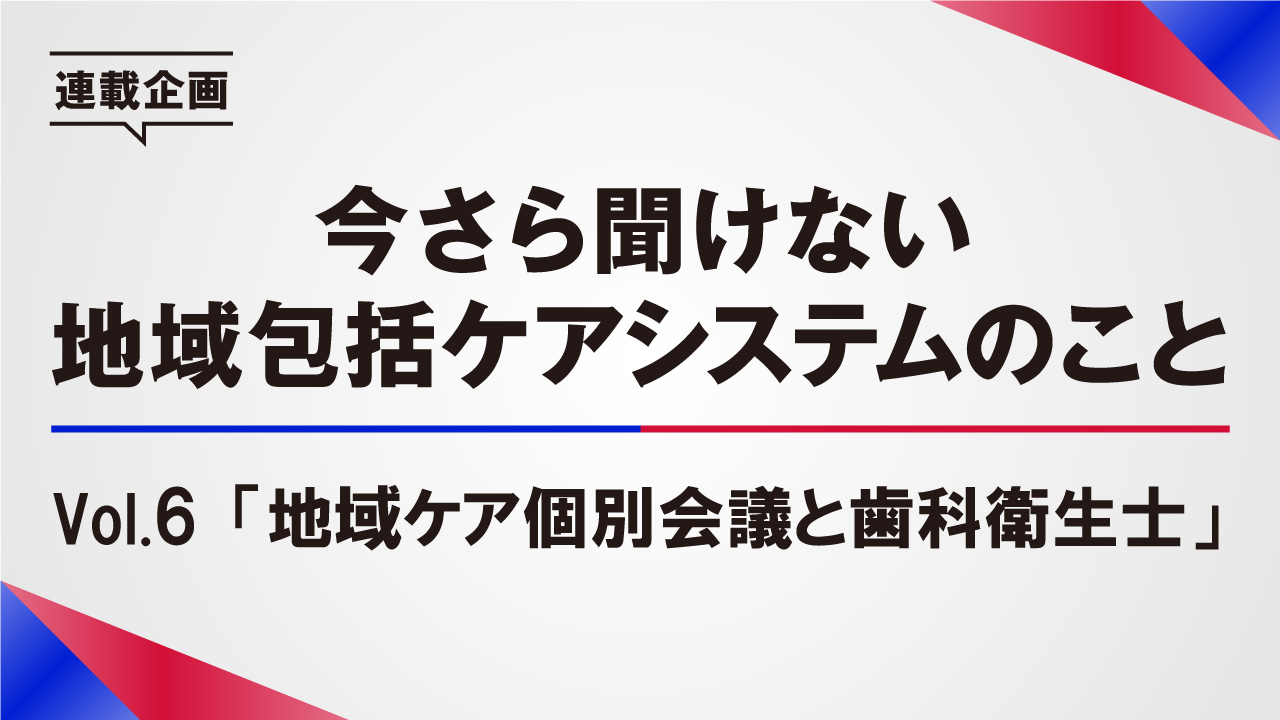
Vol.6:「地域ケア個別会議と歯科衛生士」
超高齢社会において、医療や介護のニーズはますます増えることが予想されています。そのような中、我が国では「地域包括ケアシステム」の構築が推進されています。「地域包括ケアシステム」って一体どのようなものなのでしょうか?なんとなく理解しているつもりだけど、詳しくは知らない・・・。そんな方も多いのではないでしょうか。 この連載記事では、「地域包括ケアシステム」の重要な担い手でもある医療従事者のみなさまに、「地域包括ケアシステム」に関する基本情報を配信してまいります。
自立支援・介護予防に向けた地域ケア個別会議における歯科衛生士の役割
地域ケア会議は、以下の5つの機能で構成されています。
(1)個別課題解決機能
(2)ネットワーク構成機能
(3)地域課題発見機能
(4)地域作り・資源開発機能
(5)政策形成機能
※「地域ケア会議の5つの機能」を詳しく知りたい方は以下をご覧ください。
今さら聞けない地域包括ケアシステムのこと ~Vol.3 地域包括ケア会議とは?~|IOCiL(イオシル)
機能のひとつである「個別課題解決機能」では、他職種がそれぞれの観点から「自立支援に資するケアマネジメントの支援」「支援困難事例などに関する相談・助言」を行います。
ここで、歯科衛生士に求められている役割・視点や、助言・提案を行う手順は以下のとおりです。
(1)歯科衛生士に求められる役割・視点
歯科衛生士に求められているのが、口から食べる機能を維持するために、口腔衛生や咀嚼などの食べ方を支援する観点から助言を行うことです。さらには、必要に応じて、かかりつけ歯科医師と密に連携を取り、助言・提案を行うことが必要であるとされています。
(2)歯科衛生士が助言・提案を行う手順
1.情報収集・事例の把握
情報を収集し、事例を確認します。ケアマネジメントやアセスメント情報から、歯科衛生士が着目すべきポイントを把握します。
2.要因分析
歯科衛生士の視点から生活課題を明確にし、背景や要因を確認します。
3.助言・提案
2の要因分析での内容に応じて、口腔衛生や食べ方の支援内容などについて助言・提案を行います。
1の情報収集における歯科衛生士が着目すべきポイントや、2での生活課題の明確化・背景要因の確認、3の助言・提案のポイントについては、次章以降で解説していきます。
歯科衛生士が着目すべきポイント
歯科衛生士が情報収集を行う際に、着目すべきポイントは以下のとおりです。
(1)全身状態の確認
歯科衛生士が助言を行うには、口腔内だけでなく、全身の状態を把握する必要があります。例えば「認知機能に問題があり、食事をとらなくなる」「視力の低下によって口の中が見えづらく、歯ブラシをうまく当てられずに口腔環境が悪くなる」など、さまざまな要因から口腔問題につながっているケースがあります。
(2)IADL(手段的日常生活動作)の状況
当事者の生活状況を把握することで、より適切な助言・提案を行えるようになります。例えば、献立や調理方法に偏りがあり、口腔に問題が生じているケースがあります。
口腔状況を把握する上で、特に以下の3つの項目のチェックが必要です。
・半年前に比べて固いものが食べにくくなりましたか
・お茶や汁物等でむせることがありますか
・口の渇きが気になりますか
※厚生労働省が策定する「基本チェックリスト」の口腔に関する項目から抜粋
(3)社会参加の状況
当事者の社会参加の状況も、あわせて把握する必要があります。例えば「入れ歯が合わない」「口臭が気になる」などの口腔の問題によって、人との関わりに苦手意識を感じているケースがあります。
歯科衛生士の視点からみた生活課題の明確化と背景要因の確認
当事者の生活課題と、その背景要因を明確にするため、歯科衛生士は以下の項目をチェックします。
(1)口腔衛生状況の確認
適切に歯磨きができているかを確認します。歯ブラシ以外にも、歯間ブラシやデンタルフロスなどの補助用具を使用することで、健康な歯の維持が可能です。
(2)食べ方(食内容・食形態)の確認
食事の内容や食べるタイミング、誰と食べているかなどの食事環境を確認します。
(3)食べ方(咀嚼・嚥下状況)の確認
咀嚼や飲み込みを適切に行えているかを確認します。
(4)歯科医療の必要性の有無
歯科医療が必要か、かかりつけの歯科医師はいるかを確認します。
歯科衛生士からの助言・提案のポイント
当事者の状況確認や、課題と背景要因の明確化を実施した後、実際に助言・提案を行う際のポイントは以下のとおりです。
(1)日常生活における口腔健康管理に関する助言
口腔健康管理の観点から、以下のような助言・提案を行います。
・糖尿病等有病者における口腔清掃の重要性と継続的な支援の必要性
・脳卒中罹患者への口腔機能・口腔衛生の重要性と継続的な支援の必要性
・転倒、骨折等を繰り返す者への噛み合わせの確認の必要性
・微熱を繰り返す者への口腔機能・口腔衛生の重要性と継続的な支援の必要性
・栄養状態不良の者への口腔機能・口腔衛生の重要性と継続的な支援の必要性
(2)受診勧告
う蝕や歯周疾患などの症状、嚥下・摂食・咀嚼障害、義歯の未装着・不適合などが見られ、歯科医療が必要な人には、歯科診療所・病院または訪問歯科診療による受診を勧告します。また、かかりつけ歯科医師を持つよう助言します。
(3)適切な支援内容の提案
自治体や地域住民などによって開催されている、口腔機能向上や口腔衛生の改善に関する取り組み・イベントへの参加を提案します。
参照:東京都福祉局|「自立支援・介護予防に向けた地域ケア会議実践者養成研修事業」文章版研修テキスト 第9章 地域ケア個別会議での歯科衛生士の役割
この記事の関連記事
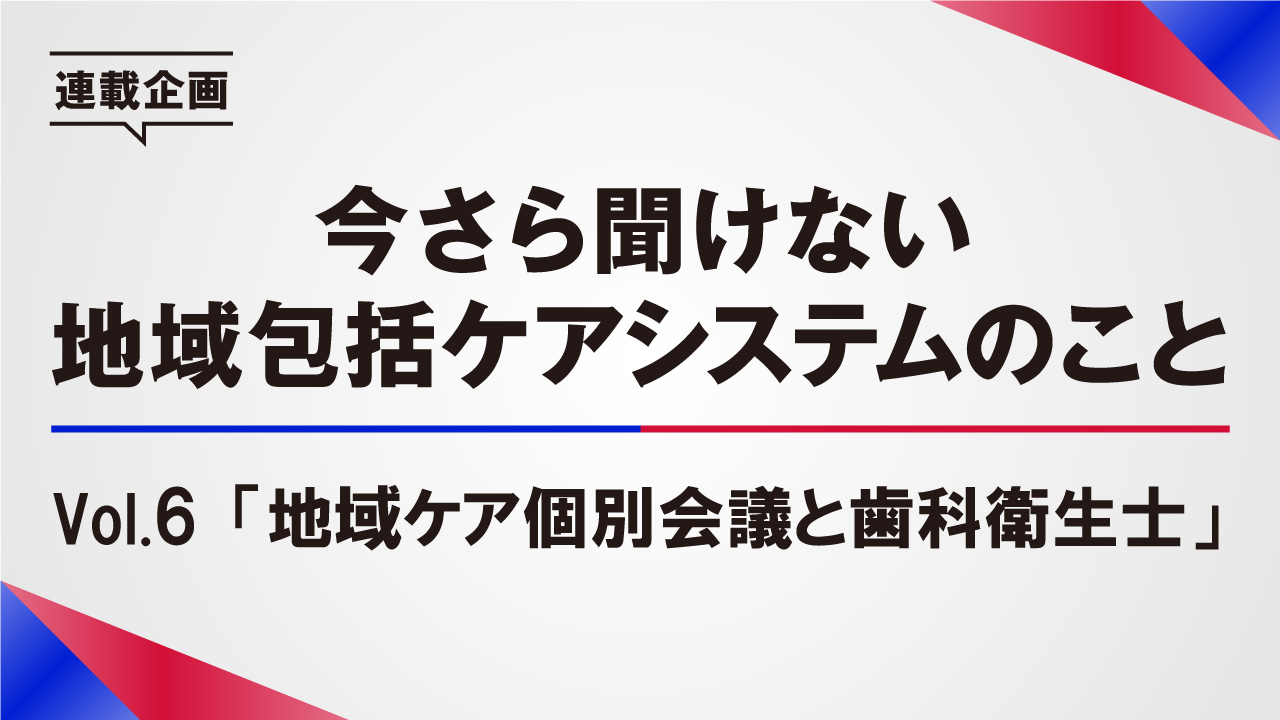
今さら聞けない地域包括ケアシステムのこと ~Vol.6 地域包括ケア会議と歯科衛生士~
Vol.6:「地域ケア個別会議と歯科衛生士」 超高齢社会に…
Vol.6:「地域ケア個別会議と歯科衛生士」 超高齢社会に…
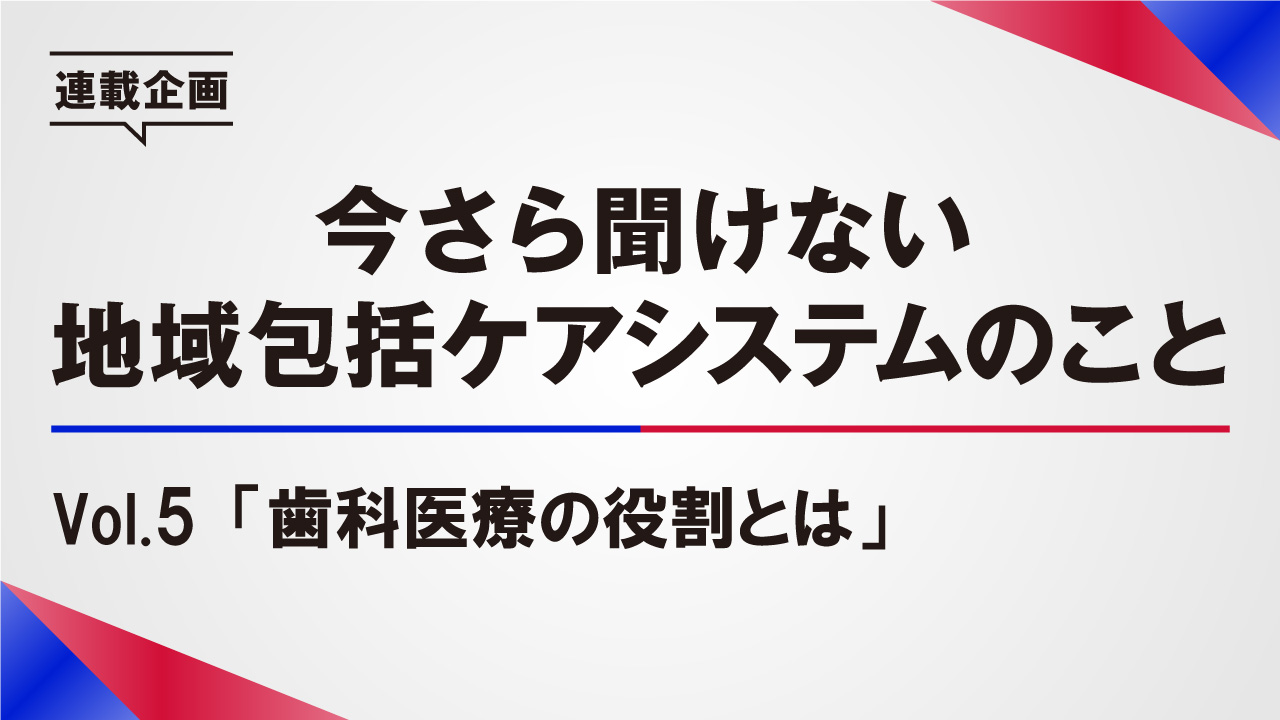
今さら聞けない地域包括ケアシステムのこと ~Vol.5 歯科医療の役割とは~
Vol.5:「歯科医療の役割とは」 超高齢社会において、医…
Vol.5:「歯科医療の役割とは」 超高齢社会において、医…
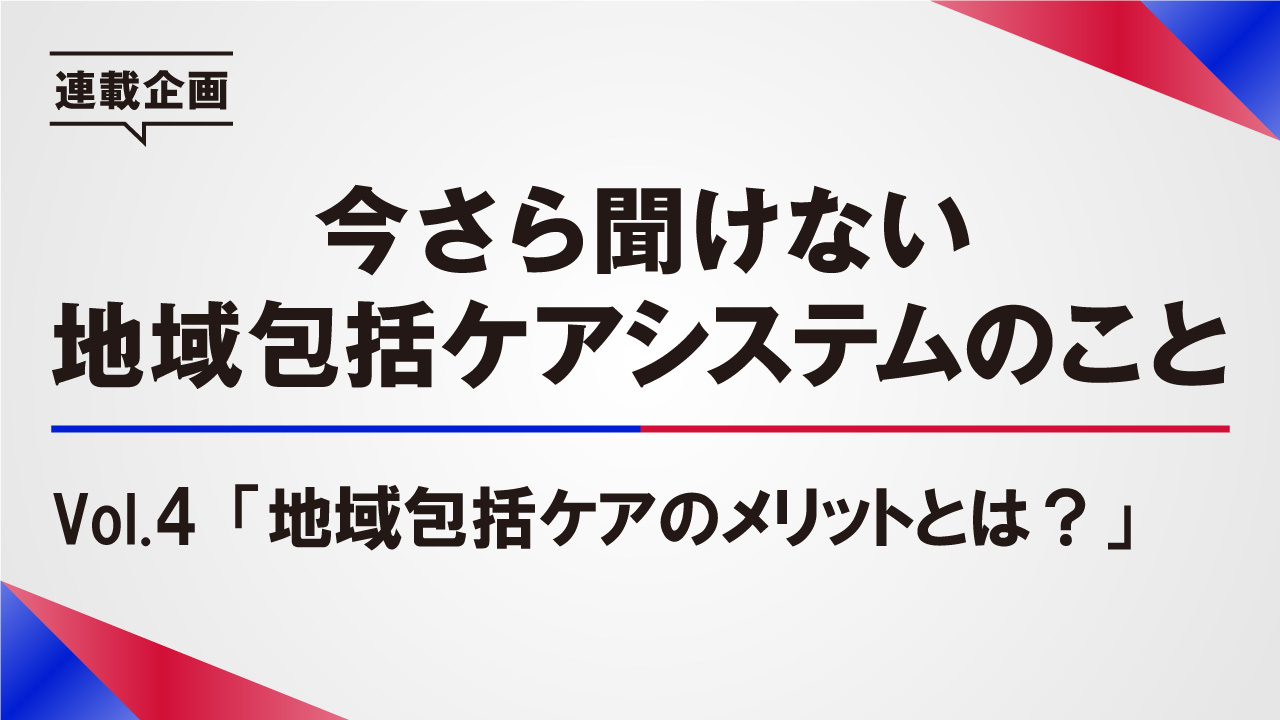
今さら聞けない地域包括ケアシステムのこと ~Vol.4 地域包括ケアのメリットとは?~
Vol.4:「地域包括ケアのメリットとは?」 超高齢社会に…
Vol.4:「地域包括ケアのメリットとは?」 超高齢社会に…
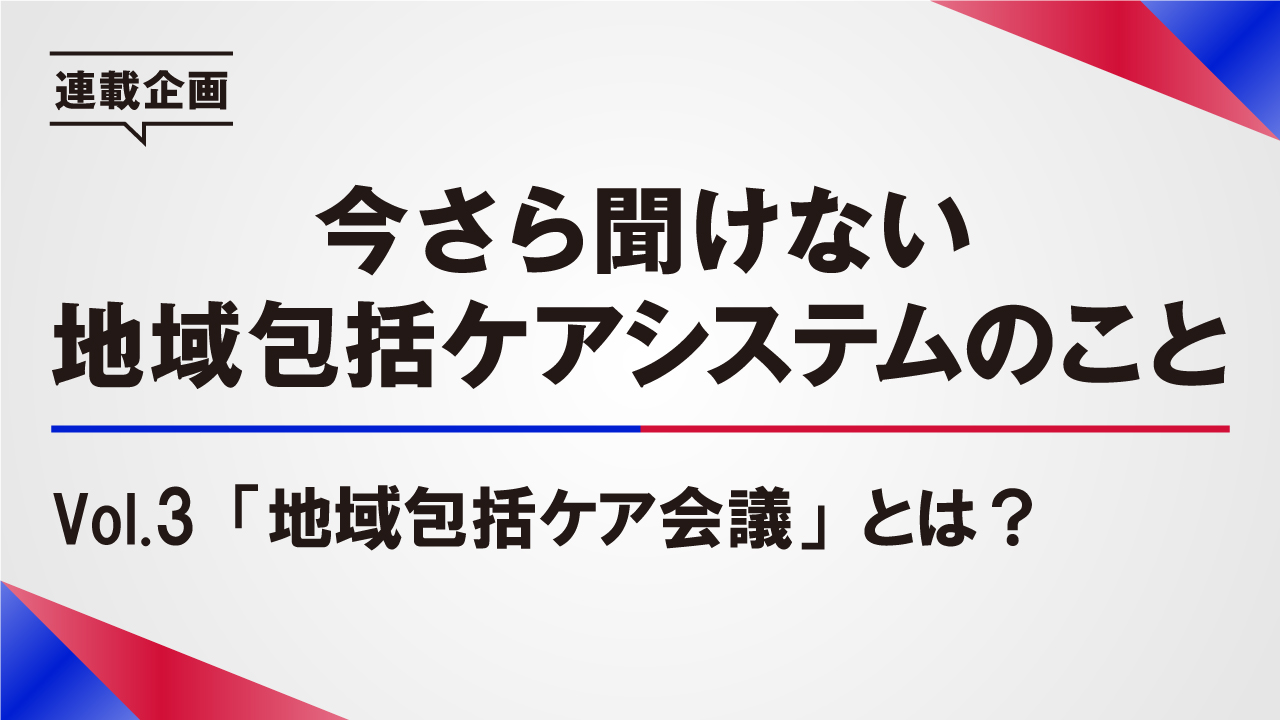
今さら聞けない地域包括ケアシステムのこと ~Vol.3 地域包括ケア会議とは?~
Vol.3:「地域包括ケア会議とは?」 超高齢社会において…
Vol.3:「地域包括ケア会議とは?」 超高齢社会において…
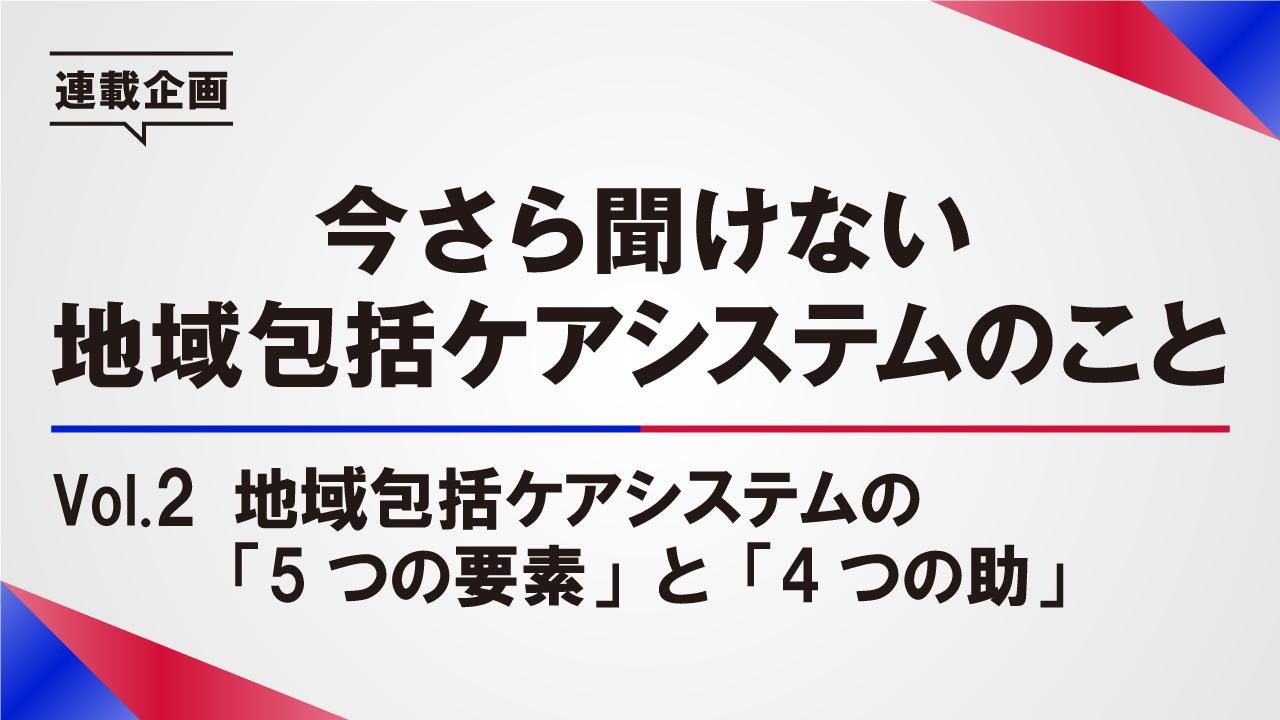
今さら聞けない地域包括ケアシステムのこと ~Vol.2 地域包括ケアシステムの5つの要素と4つの助~
Vol.2 地域包括ケアシステムの5つの要素と4つの助 超…
Vol.2 地域包括ケアシステムの5つの要素と4つの助 超…
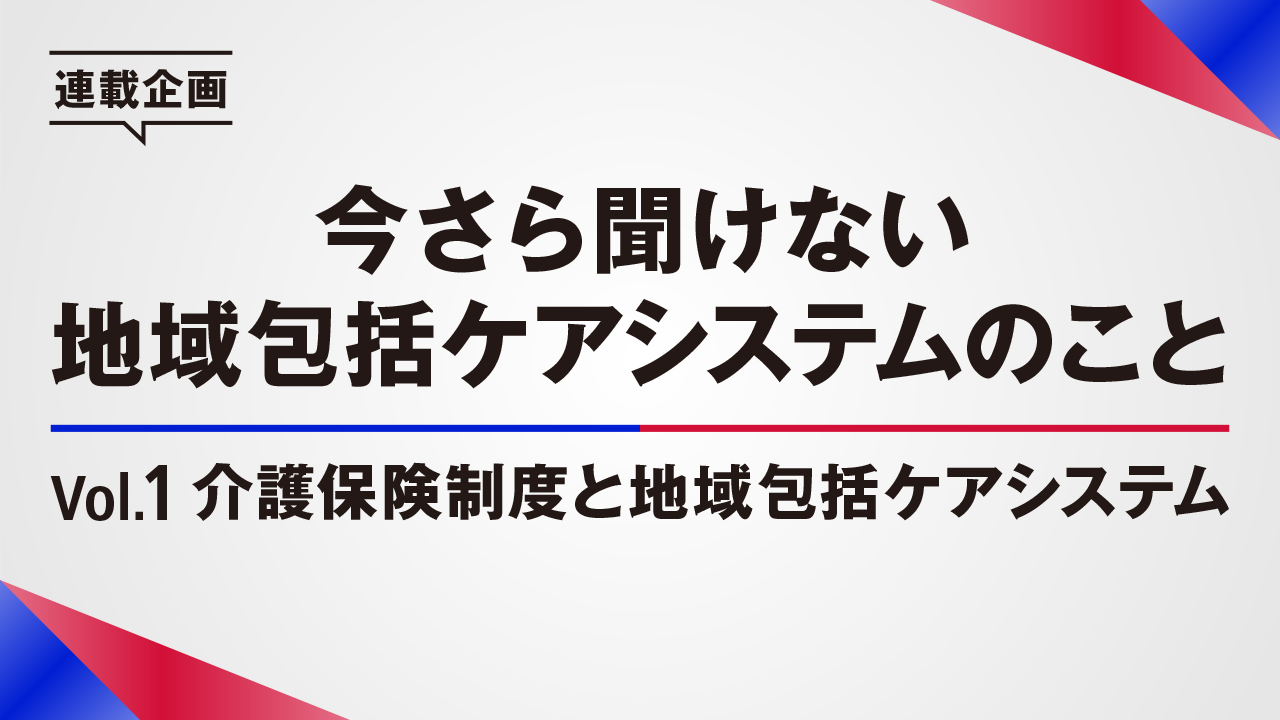
今さら聞けない地域包括ケアシステムのこと ~Vol.1 介護保険制度と地域包括ケアシステム~
Vol.1 介護保険制度と地域包括ケアシステム 超高齢社会…
Vol.1 介護保険制度と地域包括ケアシステム 超高齢社会…

【解説】歯科オンライン診療 スタートアップガイド(第2回)
<解説者>歯科医師 長縄拓哉 先生 歯科医師(医学博士) デ…
<解説者>歯科医師 長縄拓哉 先生 歯科医師(医学博士) デ…

【解説】歯科オンライン診療 スタートアップガイド(第1回)
<解説者>歯科医師 長縄拓哉 先生 歯科医師(医学博士) デ…
<解説者>歯科医師 長縄拓哉 先生 歯科医師(医学博士) デ…