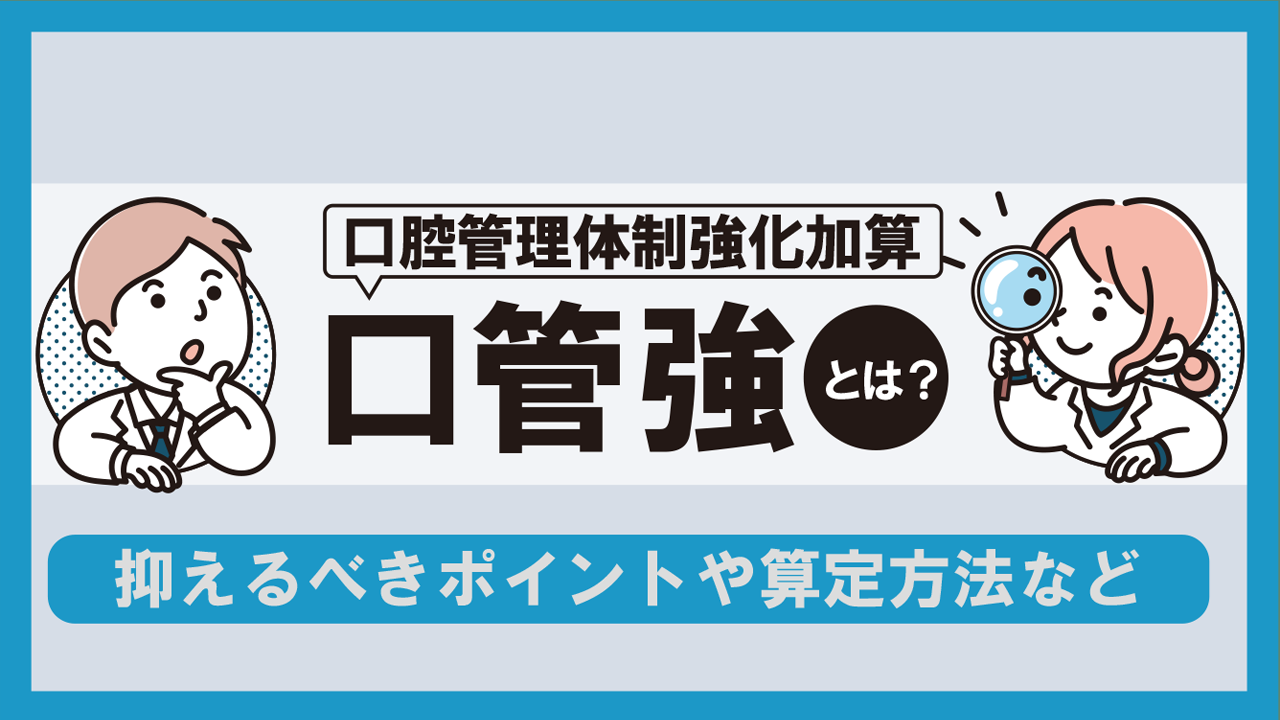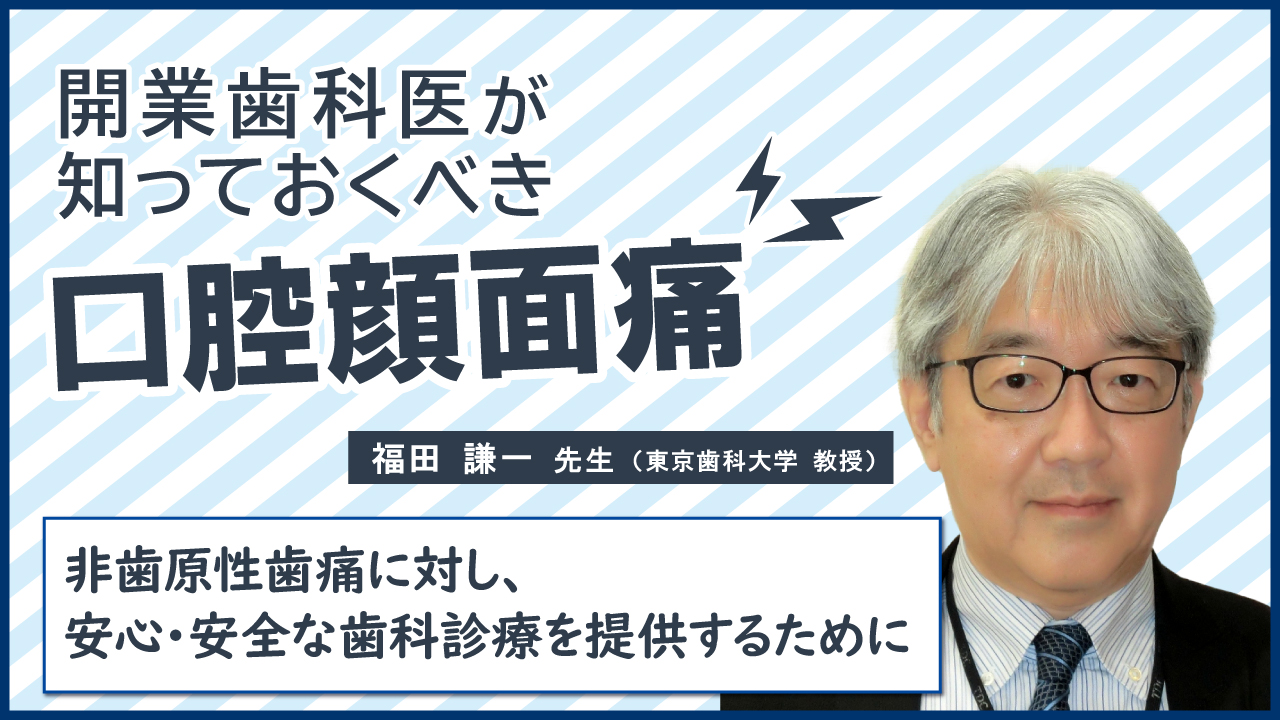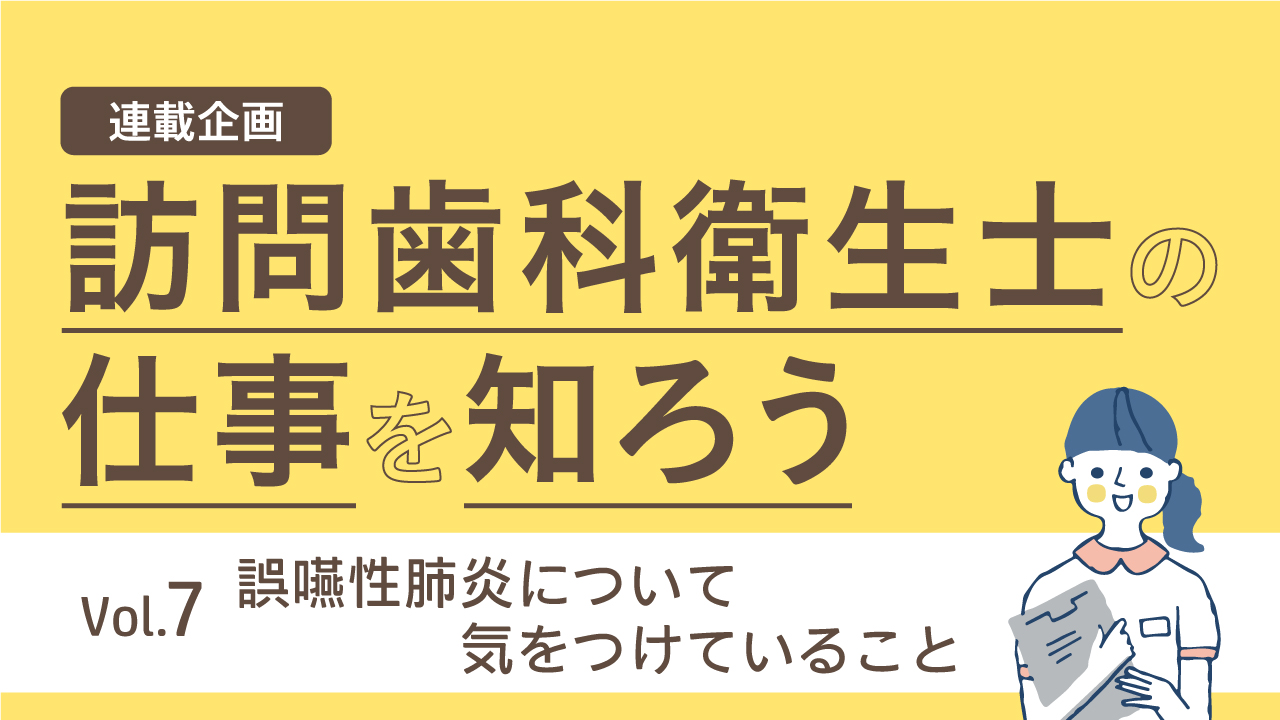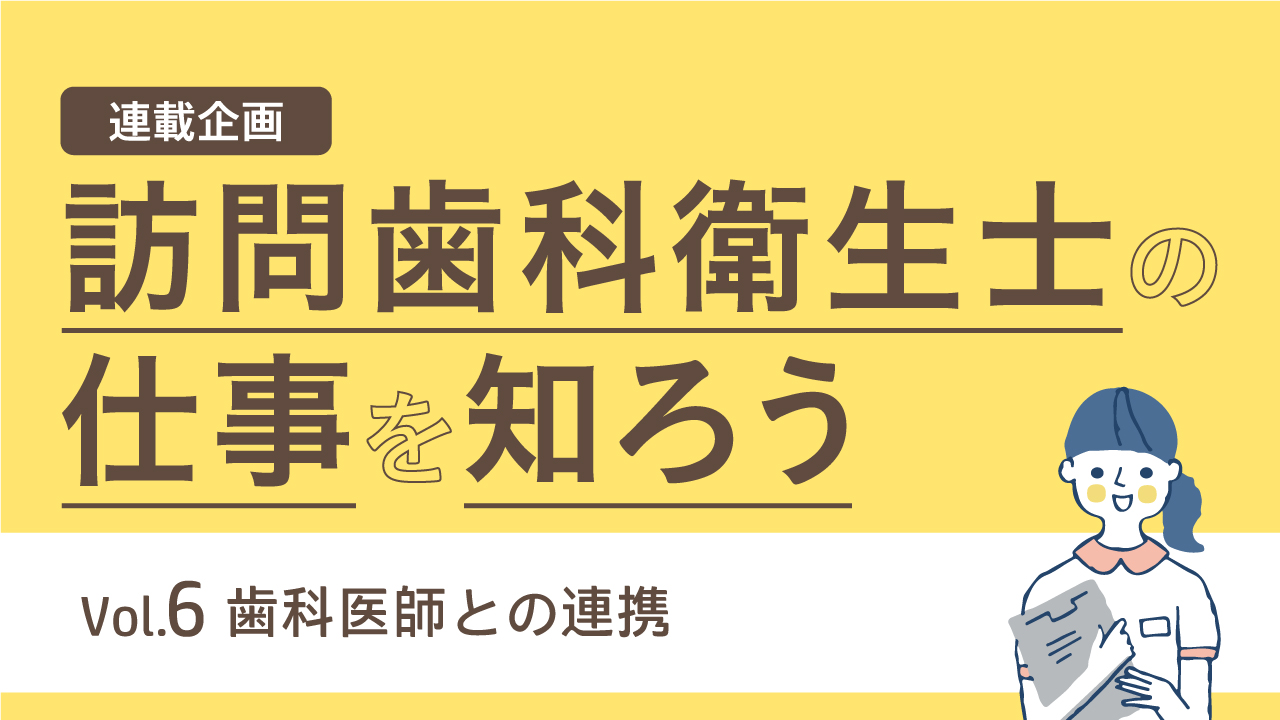今さら聞けない地域包括ケアシステムのこと ~Vol.5 歯科医療の役割とは~
特集
2023/10/30
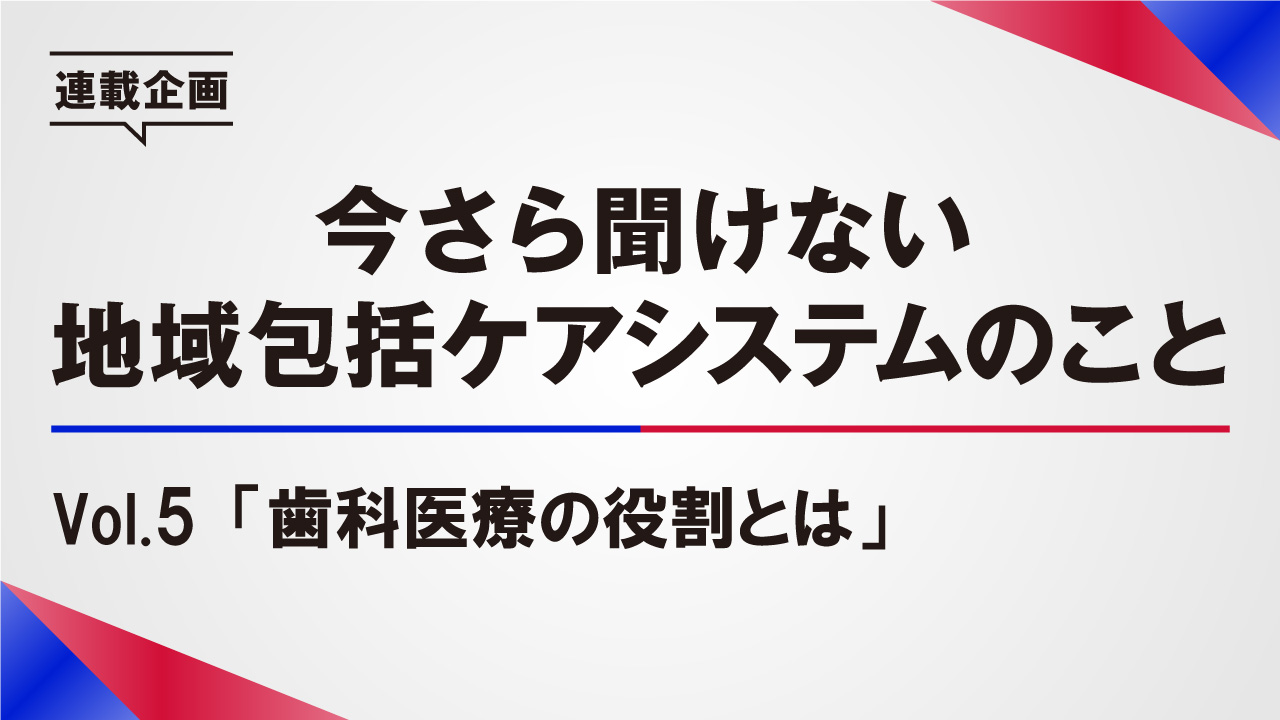
Vol.5:「歯科医療の役割とは」
超高齢社会において、医療や介護のニーズはますます増えることが予想されています。そのような中、我が国では「地域包括ケアシステム」の構築が推進されています。「地域包括ケアシステム」って一体どのようなものなのでしょうか?なんとなく理解しているつもりだけど、詳しくは知らない・・・。そんな方も多いのではないでしょうか。 この連載記事では、「地域包括ケアシステム」の重要な担い手でもある医療従事者のみなさまに、「地域包括ケアシステム」に関する基本情報を配信してまいります。
歯科医療に求められる役割とは
地域包括ケアシステムにおいて、歯科医療の主な役割は、以下の4つに分けて考えられています。
(1)認知症対策における歯科の役割
(2)在宅療養における歯科の役割
(3)介護予防と地域ケア会議における歯科の役割
(4)介護保険施設における歯科の役割
上記の歯科医療におけるそれぞれの役割を満たすことで、地域包括ケアシステムの充実につながります。以降の章で、4つの役割について詳しく紹介します。
役割(1) 認知症対策における歯科の役割
2025年には、65歳以上の5人に1人が認知症またはその予備軍であるといわれ、認知症対策は今や日本の喫緊の課題です。そこで、厚生労働省は「認知症の人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けることができる社会の実現」を目的に、2015年に「認知症施策推進総合戦略(新オレンジプラン)」を掲げました。
新オレンジプランの中で、早期診断・早期対応のための体制整備として明記されているのが「歯科医師の認知症対応力向上」です。新オレンジプランの考え方では、歯科医師の役割として、認知症の早期発見だけでなく、かかりつけ医との連携や、高齢者一人ひとりに適した口腔機能の管理が求められています。
役割(2) 在宅療養における歯科の役割
地域包括ケアシステムでは、高齢者が医療と介護のどちらも必要な場合でも、住み慣れた地域で自分らしく生活し続けることができるよう、医療・介護の関係機関が連携して、一体的に在宅医療・介護サービスを提供する体制の構築が重要だとされています。ここで登場する「関係機関」の中には歯科診療所も含まれています。
在宅医療と介護の連携のための具体的な取り組みの1つが、地域の医師・歯科医師・薬剤師・看護師・医療ソーシャルワーカー・ケアマネジャーなどが参加する他職種研修の実施です。ネットワークづくりや新たな知識の獲得、他職種からのフィードバックによるモチベーションの向上などを通じて、在宅医療と介護の連携強化を図っています。
役割(3) 介護予防と地域ケア会議における歯科の役割
地域包括ケアシステムを構築する上で、高齢者の自立支援や介護予防に向けた取り組みを行うことが重要です。厚生労働省は、先進的に自立支援・介護予防を進め、要介護認定率の低下に成功した自治体の事例をもとに、全国展開を図っています。
全国展開を進める上での好事例の1つが、埼玉県の和光市での取り組みです。和光市は、自立支援・介護予防への取り組みとして、主に以下の3つを実施しました。
1.本人や家族への徹底した自立の意識づけ
自治体職員や地域包括支援センター、介護サービス事業者などを通じて、高齢者本人やその家族へ、要介護度が軽くなる(=自立する)ことは喜ばしいことであるという意識づけを行っています。
2.介護サービス以外の豊富なメニューの用意
マシーントレーニングやヨガ、パソコン・英会話などの講座、囲碁クラブや料理教室など豊富なメニューを用意している高齢者福祉センターを設置しています。他にも、高齢者福祉センターへの無料送迎、通院や保険福祉施設への移動のための費用の給付、ゴミの個別収集など、さまざまなサービスを提供しています。
3.コミュニティケア会議の開催
月3回のコミュニティケア会議を開催し、自立支援が必要な高齢者に対するプランの調整や地域課題の解決を行っています。会議には、保健師や看護師、理学療法士、歯科衛生士、薬剤師、社会福祉士、介護福祉士などのメンバーが参加します。
要介護認定率の全国平均が4年連続で上がり続ける中、和光市は上記の取り組みによって、認定率低下に成功しました。全国展開の参考となる取り組みとして、注目されています。
参考: https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/yobou/dl/jitsurei3-07.pdf https://www.city.wako.lg.jp/home/fukushi/kaigo/_21310/_21312/_21325.html
役割(4) 介護保険施設における歯科の役割
地域包括ケアシステム構築に向けた取り組みとして、中重度の要介護者や認知症高齢者に対する「口腔・栄養管理の係る取組の充実」が挙げられています。
・口腔・栄養管理に係る取組の充実とは
施設などに入所する高齢者が、認知機能や摂食・嚥下機能の低下によって、食事の経口摂取が困難になったとしても、口から食べる楽しみを感じられるように、歯科医師や歯科衛生士をはじめ多職種による支援を充実させることを目指しています。例えば「咀嚼・嚥下能力に応じた食形態・水分量の工夫」「認知機能に応じた食事介助の工夫」「食べるときの姿勢の工夫」などを実施します。
・口から食べる楽しみの支援の流れ・効果
施設利用者の食事を多職種で観察し、咀嚼能力や嚥下機能などの口腔機能、食事の環境、食べる姿勢、食物の認知機能などを適切に評価します。また、動画でも食べる様子を確認し、他職種間での意見交換を通じて、状況や環境に応じた経口維持計画を検討。これにより口から食べるための支援を適切に行えるようになり、必要な栄養の摂取や体重増加、誤嚥性肺炎の予防につながります。
この記事の関連記事
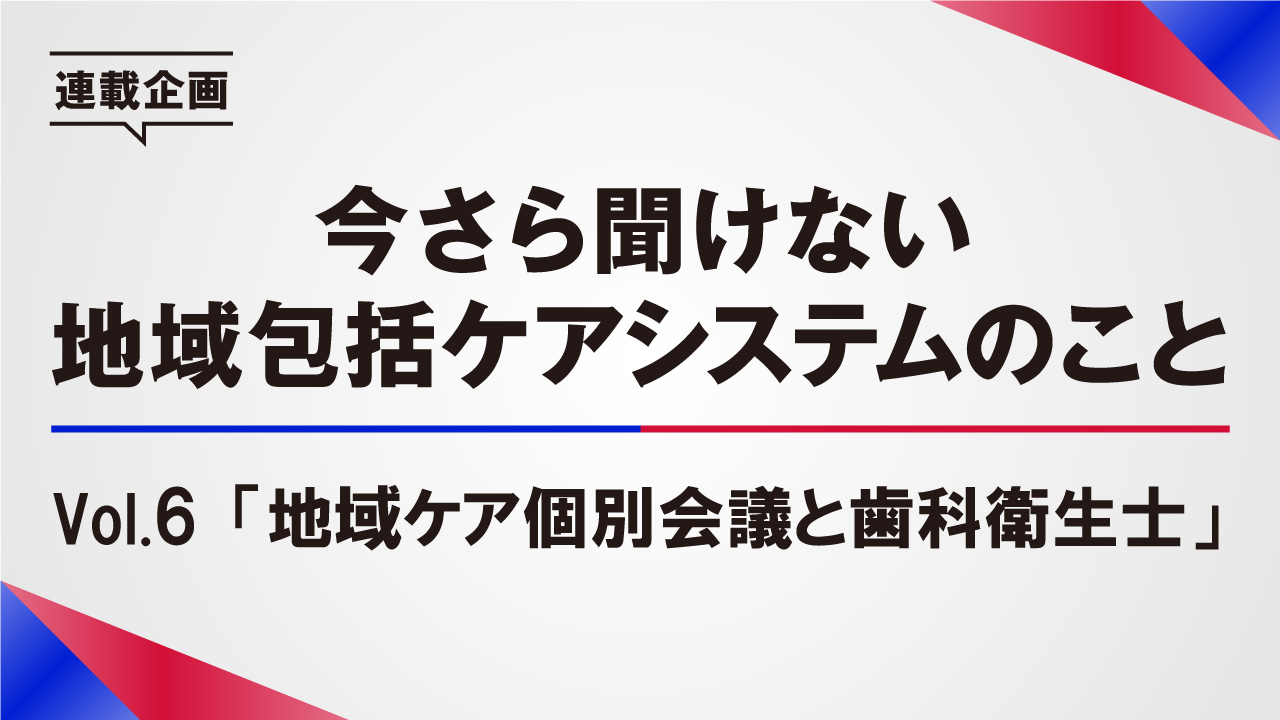
今さら聞けない地域包括ケアシステムのこと ~Vol.6 地域包括ケア会議と歯科衛生士~
Vol.6:「地域ケア個別会議と歯科衛生士」 超高齢社会に…
Vol.6:「地域ケア個別会議と歯科衛生士」 超高齢社会に…
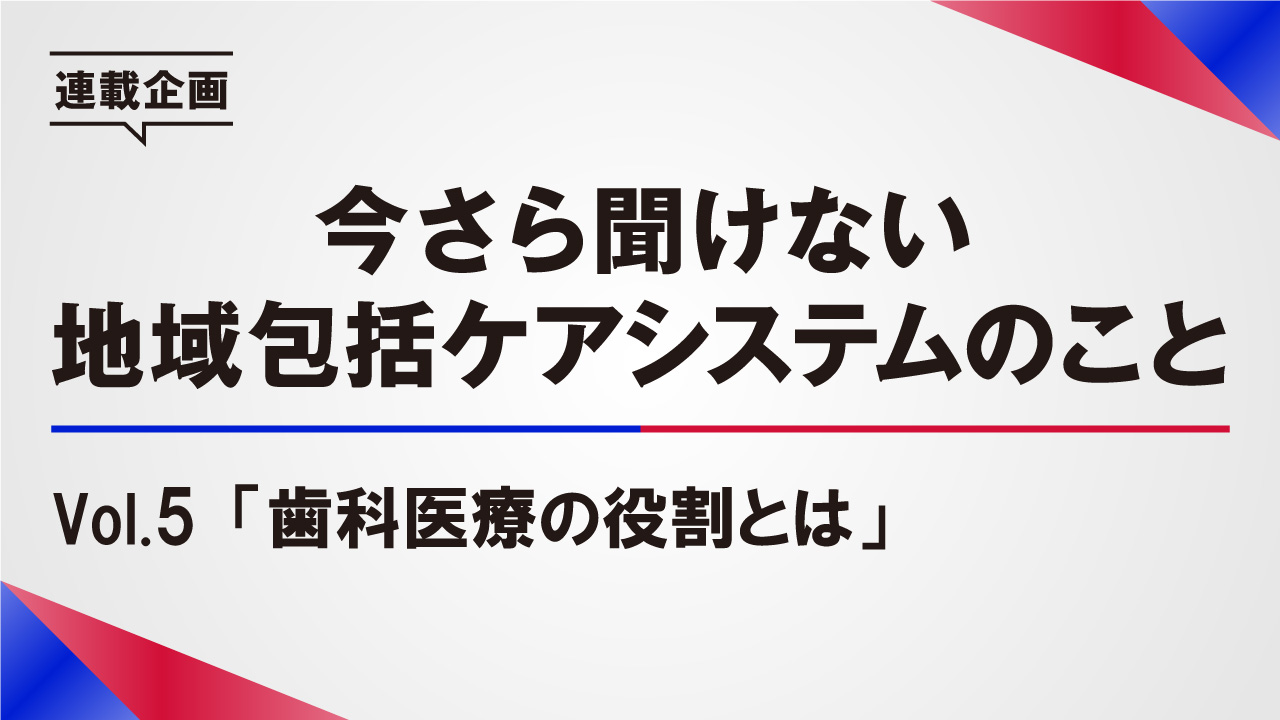
今さら聞けない地域包括ケアシステムのこと ~Vol.5 歯科医療の役割とは~
Vol.5:「歯科医療の役割とは」 超高齢社会において、医…
Vol.5:「歯科医療の役割とは」 超高齢社会において、医…
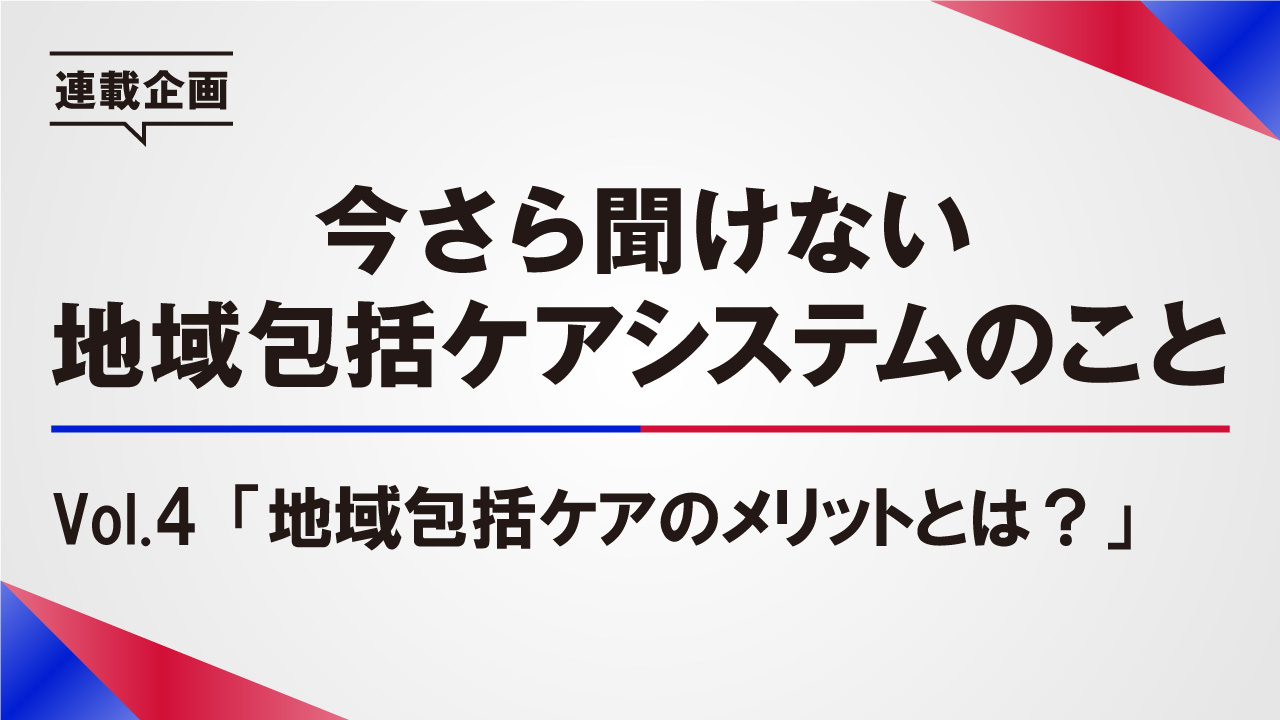
今さら聞けない地域包括ケアシステムのこと ~Vol.4 地域包括ケアのメリットとは?~
Vol.4:「地域包括ケアのメリットとは?」 超高齢社会に…
Vol.4:「地域包括ケアのメリットとは?」 超高齢社会に…
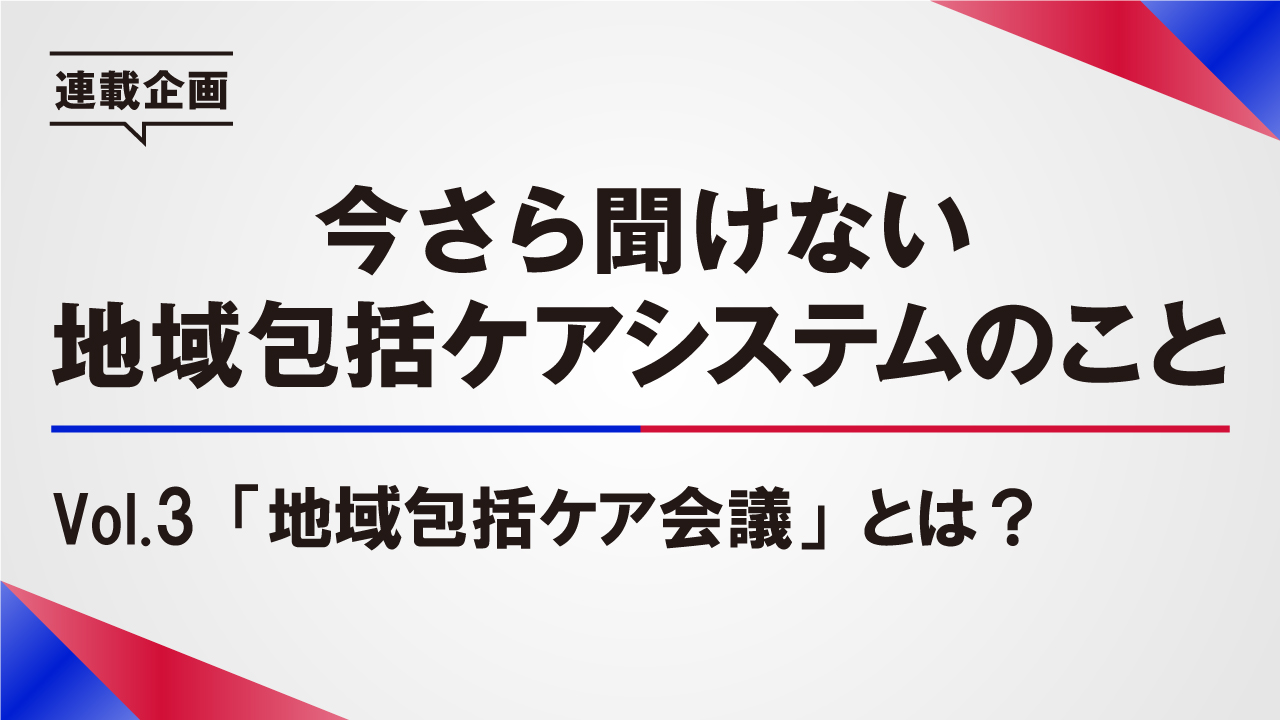
今さら聞けない地域包括ケアシステムのこと ~Vol.3 地域包括ケア会議とは?~
Vol.3:「地域包括ケア会議とは?」 超高齢社会において…
Vol.3:「地域包括ケア会議とは?」 超高齢社会において…
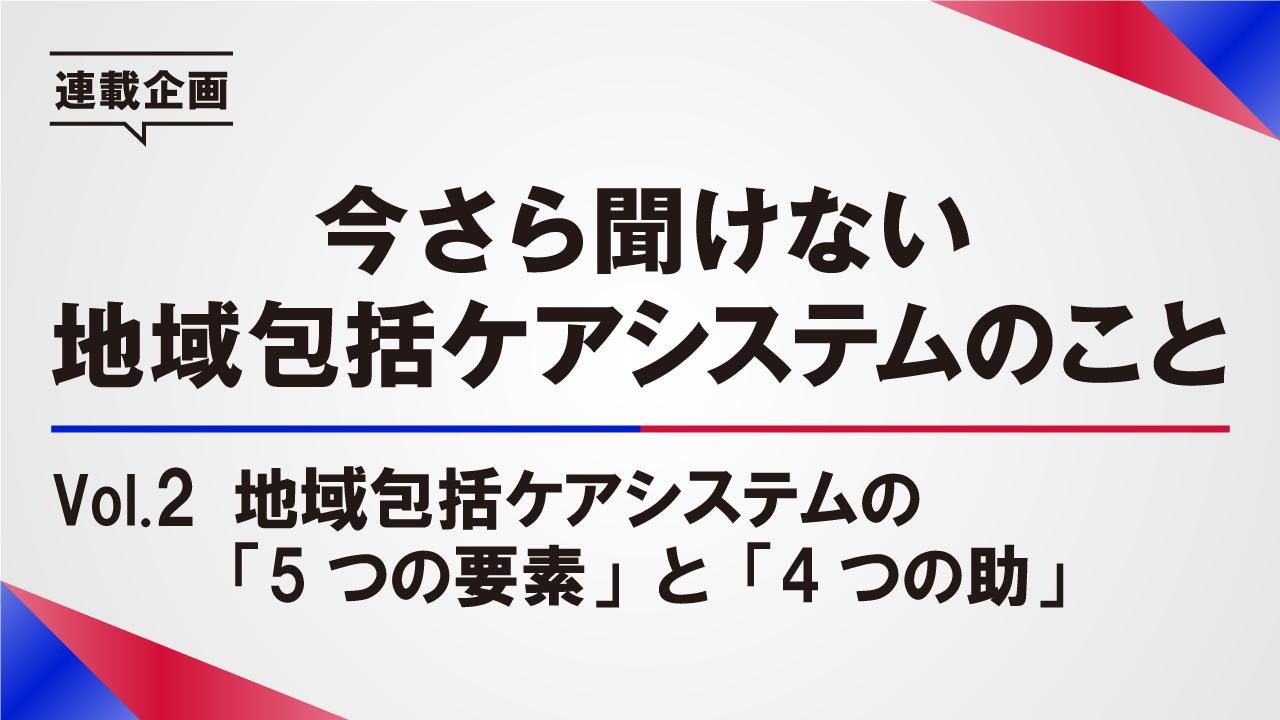
今さら聞けない地域包括ケアシステムのこと ~Vol.2 地域包括ケアシステムの5つの要素と4つの助~
Vol.2 地域包括ケアシステムの5つの要素と4つの助 超…
Vol.2 地域包括ケアシステムの5つの要素と4つの助 超…
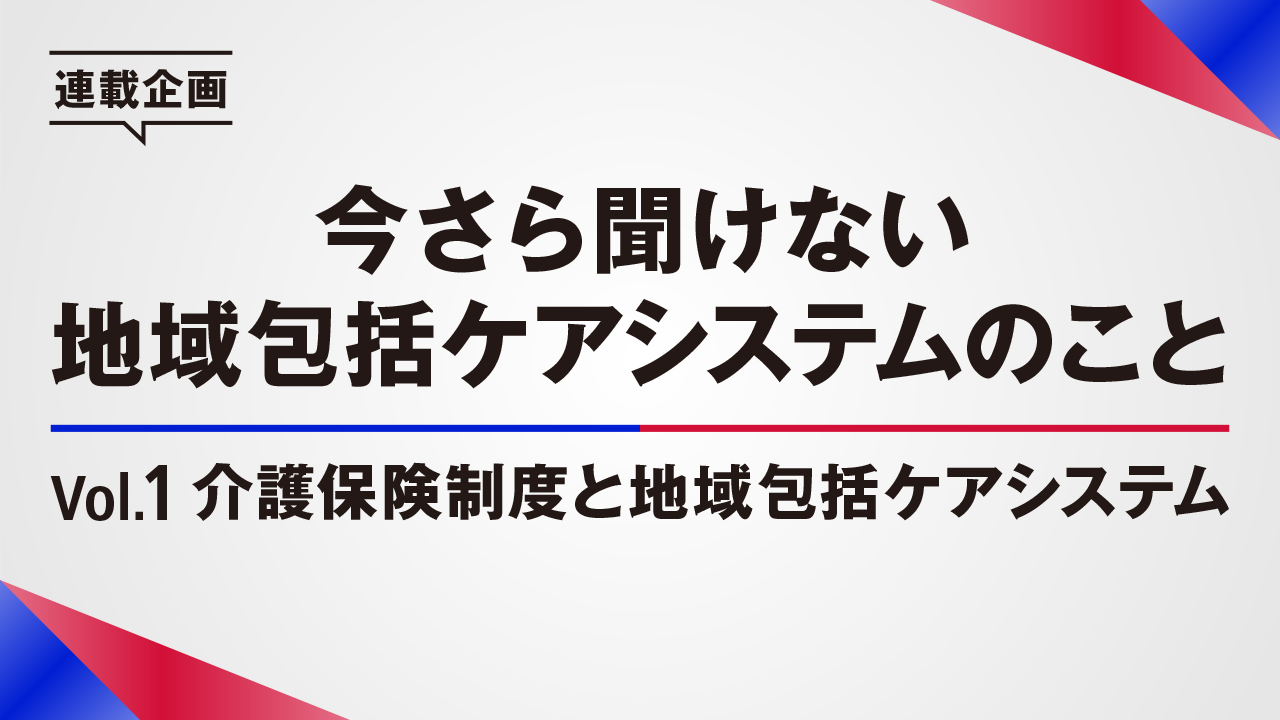
今さら聞けない地域包括ケアシステムのこと ~Vol.1 介護保険制度と地域包括ケアシステム~
Vol.1 介護保険制度と地域包括ケアシステム 超高齢社会…
Vol.1 介護保険制度と地域包括ケアシステム 超高齢社会…

【解説】歯科オンライン診療 スタートアップガイド(第2回)
<解説者>歯科医師 長縄拓哉 先生 歯科医師(医学博士) デ…
<解説者>歯科医師 長縄拓哉 先生 歯科医師(医学博士) デ…

【解説】歯科オンライン診療 スタートアップガイド(第1回)
<解説者>歯科医師 長縄拓哉 先生 歯科医師(医学博士) デ…
<解説者>歯科医師 長縄拓哉 先生 歯科医師(医学博士) デ…