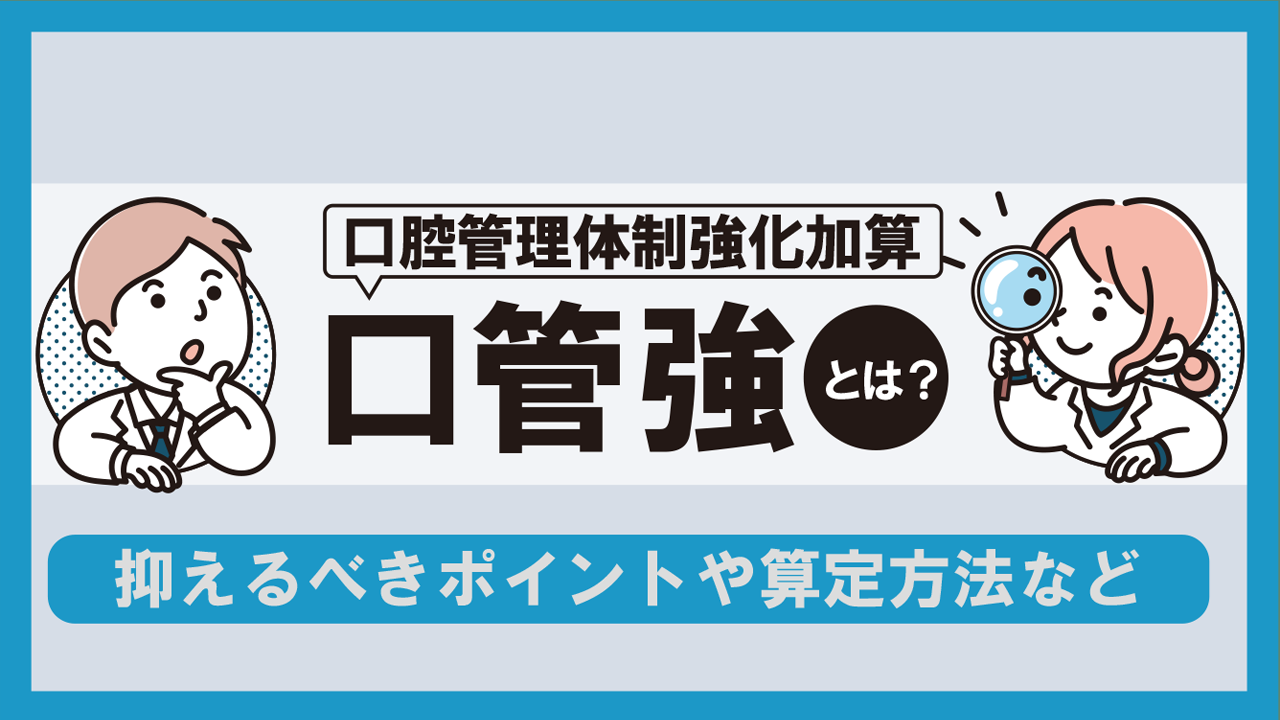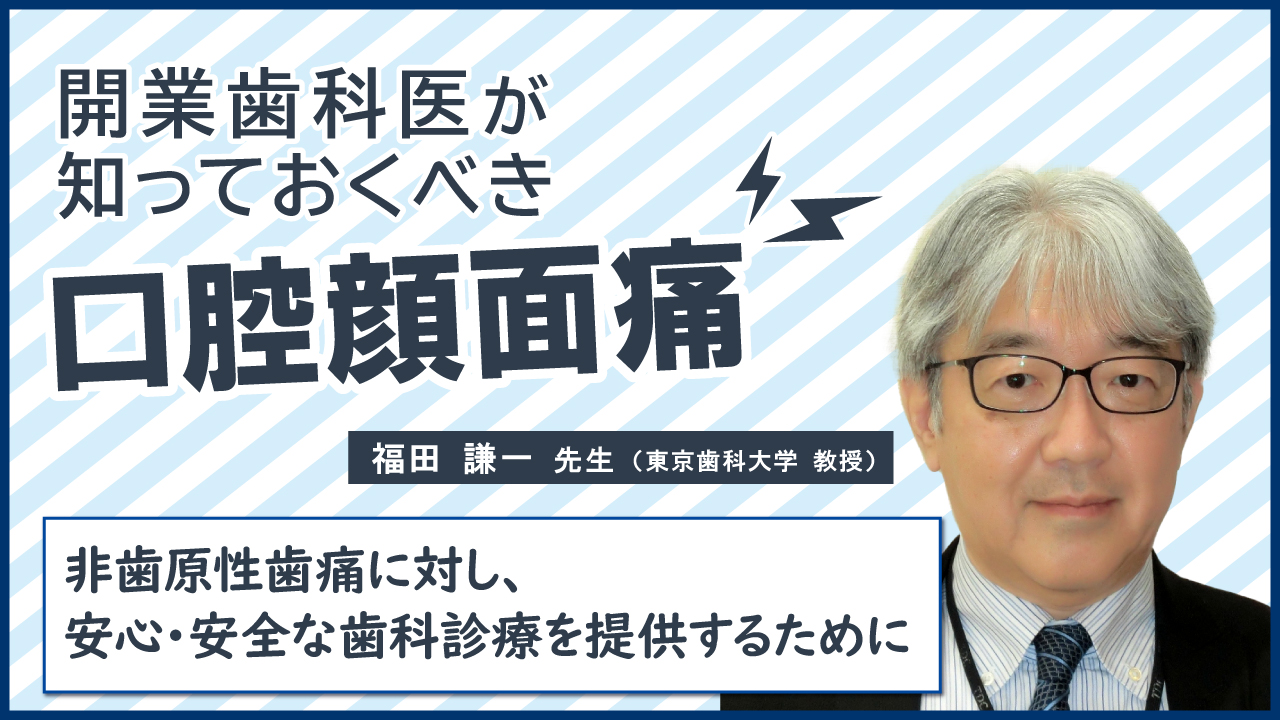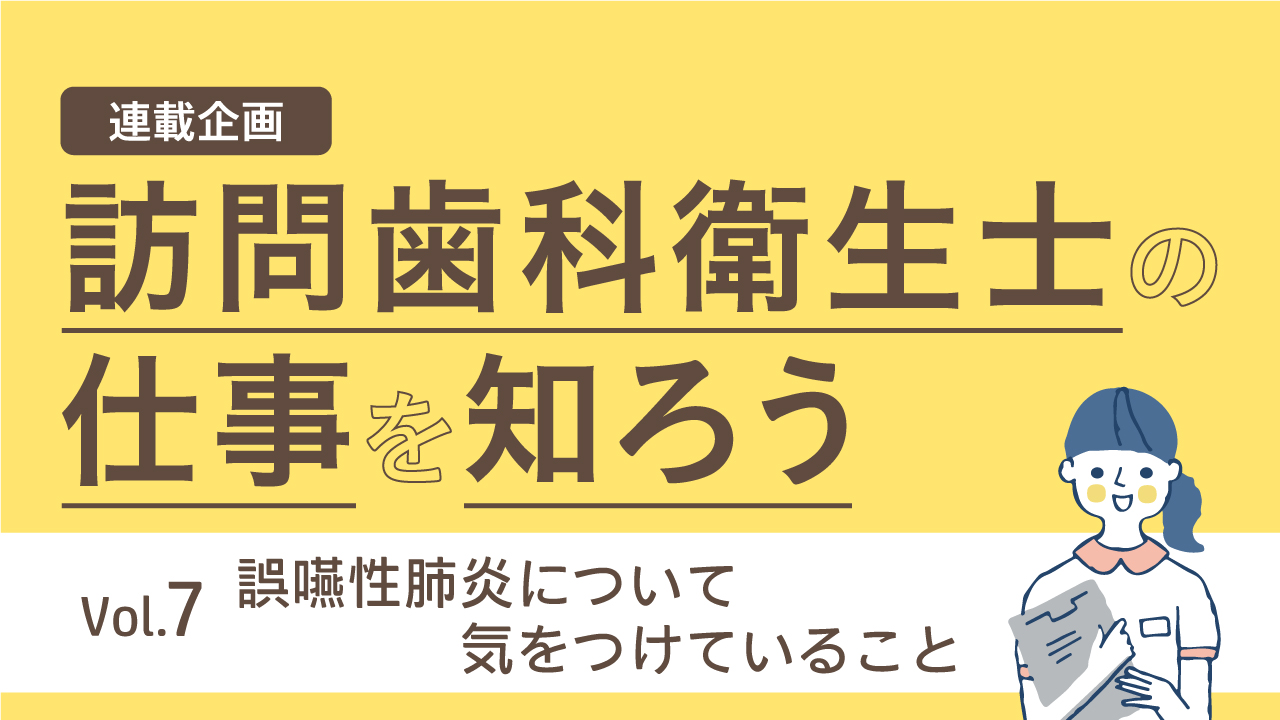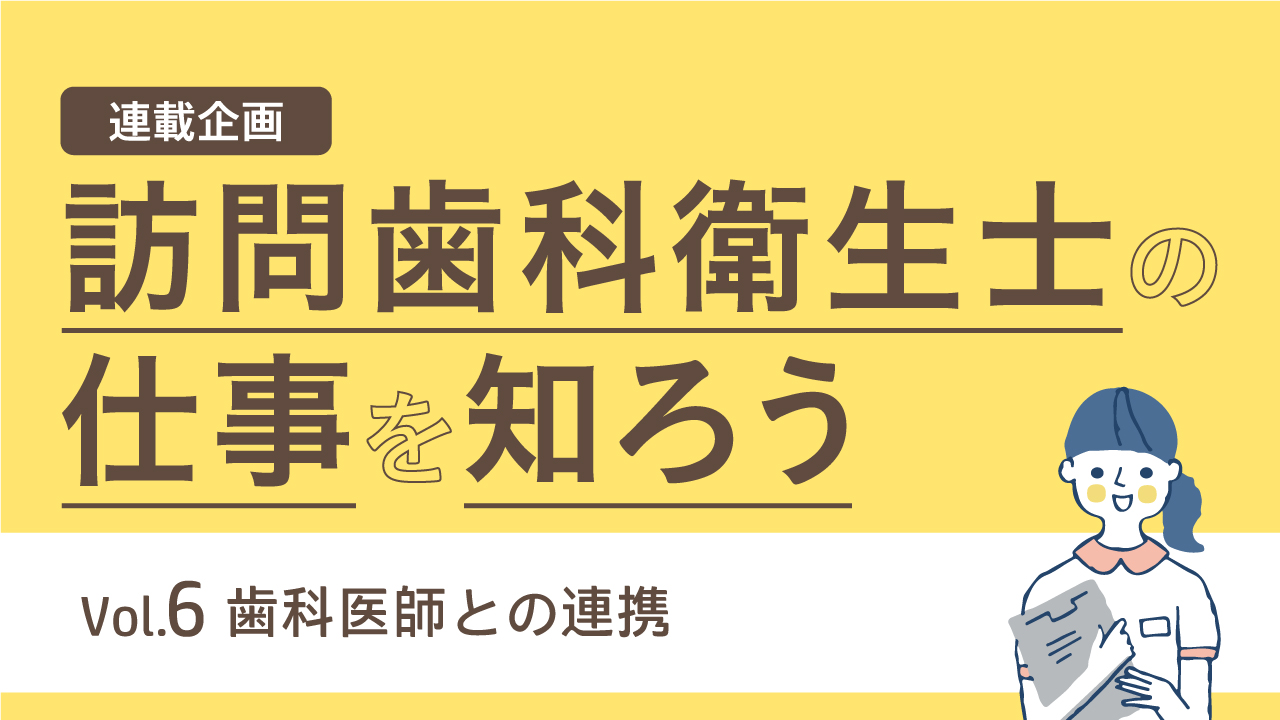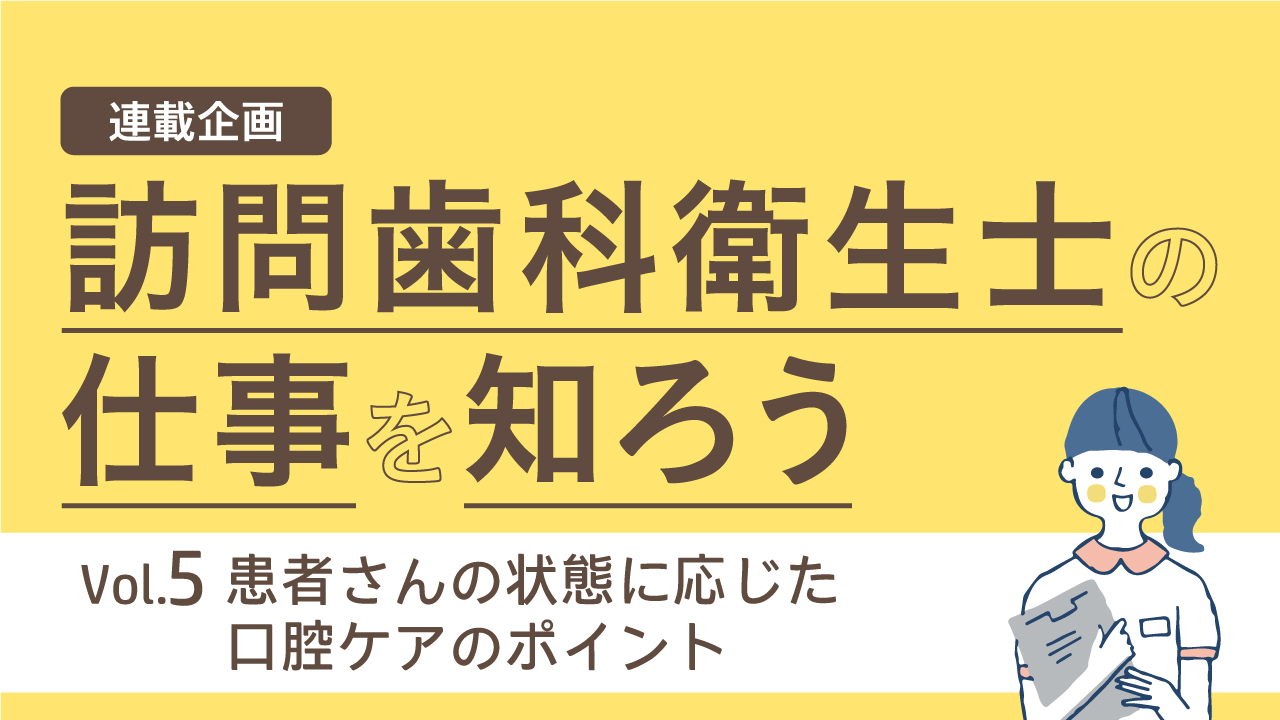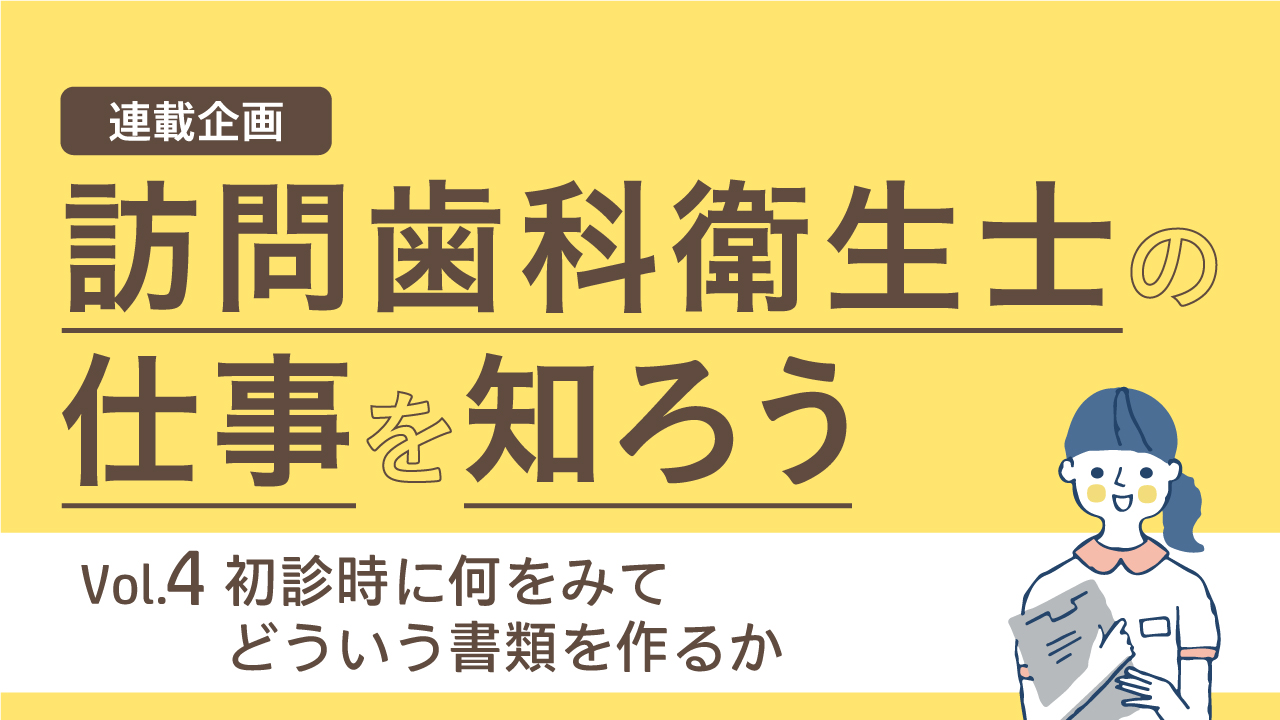今さら聞けない地域包括ケアシステムのこと ~Vol.1 介護保険制度と地域包括ケアシステム~
特集
2023/05/16
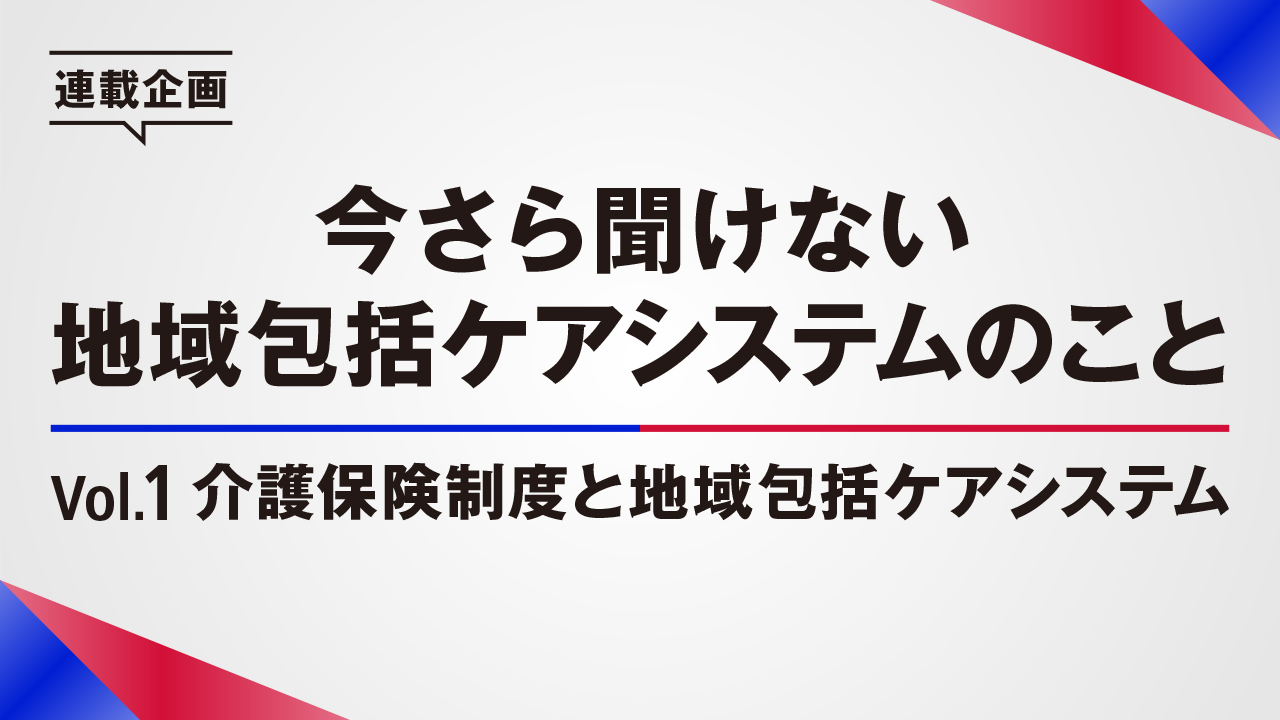
Vol.1 介護保険制度と地域包括ケアシステム
超高齢社会において、医療や介護のニーズはますます増えることが予想されています。そのような中、我が国では「地域包括ケアシステム」の構築が推進されています。「地域包括ケアシステム」って一体どのようなものなのでしょうか?なんとなく理解しているつもりだけど、詳しくは知らない・・・。そんな方も多いのではないでしょうか。 この連載記事では、「地域包括ケアシステム」の重要な担い手でもある医療従事者のみなさまに、「地域包括ケアシステム」に関する基本情報を配信してまいります。
2005年の介護保険制度改正で、「地域包括ケアシステム」の構築が掲げられた
地域包括ケアシステムとは、要介護状態になっても、住み慣れた地域で自分らしい生活を最後まで続けることができるように地域内で助け合う体制のことです。この「地域包括ケアシステム」という言葉は、2005年の介護保険改正で初めて使われました。そもそも、介護保険制度は「介護保険法」に基づき、2000年から始まりました。高齢化が進む我が国において、要介護者の増加や介護期間の長期化が懸念され、従来の制度では対応が困難になると考えられたのです。そこで、社会全体で高齢者を支えていく仕組みとして介護保険制度が制定されました。
介護保険制度の制定時は、在宅ケアが重視されていましたが、実際にはサービスの提供体制が整っていなかったため、介護施設の利用希望者数は増えていくばかりでした。そこで、2005年に1回目の介護保険制度改正が行われます。この制度改正では、高齢者が必要なサービスやケアを受けながら、住み慣れた場所で安心して生活を送ることができる「地域包括ケアシステム」の構築が掲げられました。しかし、制度改正後も、サービス受給者や要介護認定者は増え続ける結果となります。
2011年、地方自治体が推進の義務を請け負うことが決定
2011年の介護保険制度の改正では「地域包括ケアシステムの構築の義務化」を目指し、地方自治体が推進の義務を請け負うことが決定しました。「介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律」を2011年6月15日に制定し、以下の5つの取り組みが包括的かつ継続的に行われることを目指しました。
(1)医療と介護の連携強化
(2)介護サービスの充実強化
(3)予防の推進
(4)見守り、配食、買い物
(5)高齢期になっても住み続けることのできる高齢者住まいの整備
具体的な取り組みとしては、医療と介護の連携強化のための24時間定期巡回サービスや複合型サービスの提供などの施策があります。また、介護業界での人材確保やサービスの質向上を目指し、介護スタッフによるサポート内容の見直しや、介護福祉士の資格取得方法の見直しの延期など、さまざまな施策が行われました。ほかにも、高齢者の住居整備や認知症対策、保険料の増加の緩和など、さまざまな観点から地域包括ケアシステムの構築を目指して、施策を実施していきました。この結果、高齢者への医療と介護、生活支援を継続的に提供する「地域包括ケアシステム」が改めて注目され始めることとなります。
介護保険制度の改正とともに、より充実したシステム構築が推進されていく
その後、2015年の介護保険法改正によって、地域包括ケアシステムの体制づくりはますます充実したものになっていきます。改正後は、各地方自治体が中心となり、在宅医療・介護連携の推進が行われ、生活支援や介護予防サービスも充実していきました。例えば、今まではサービスの種類や内容などが全国一律となっていましたが、新たに「介護予防・日常生活支援総合事業」を創設し、地域の高齢者の状況に合わせて、必要で最適なサービスを地方自治体が提供できるようにしました。
また、特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)の利用者条件の再設定や、低所得者の保険料の見直し、所得に応じた利用者の自己負担料金の見直しなどを実施。地域包括ケアシステムの構築と、費用負担の公平化を目指しました。 このような流れの中、地方自治体では、要介護者の自立支援や重度化の防止に向けて、積極的な取り組みが求められるようになりました。さらに、幾度にわたる制度改正の内容を適切に把握した上で、対応・周知を行わなければなりません。地方自治体は住民や医療従事者に対して制度への理解や協力を仰ぎ、連携しながら地域包括ケアシステムを推進していく必要がありました。
高齢者の自立支援や地域共生社会の実現のために
我が国は、第一次ベビーブームで生まれた「団塊の世代」が75歳以上になる2025年に、75歳以上の後期高齢者が人口の約18%※になると言われています。さらに、2040年には65歳以上が人口の約35%※になると予測されています。このように、昨今、日本の高齢化は急速に進み、それに伴い医療・介護サービスの需要が増加し、現役世代の負担もより大きくなっていくことが見込まれています。
そのような背景から、国は地域包括ケアシステムの構築を急速に進めています。2017年には、介護保険制度による費用給付を継続しながら、高齢者が住み慣れた地域で、自立して日常生活を送れるよう、「地域ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律」を制定しました。この法律では「地域包括ケアシステムの深化・推進」「介護保険制度の持続可能性の確保」の2点に焦点を当て、「高齢者の自立支援」や「地域共生社会の実現」のさらなる強化を目指したものとなっています。
2025年問題に立ち向かうべく、我が国が推進する「地域包括ケアシステム」は、このように介護保険制度改正の経緯とともに成り立ちを理解することができます。
※出典:厚生労働省「我が国の人口について」https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21481.html
この記事の関連記事
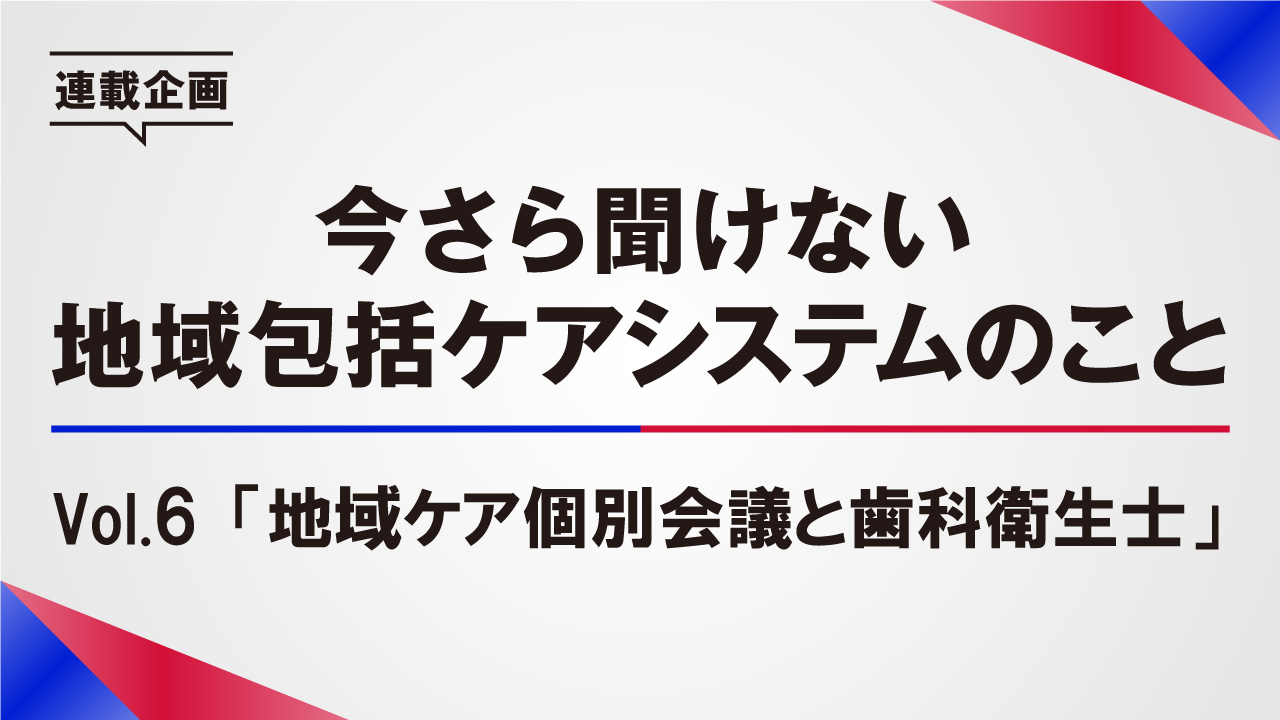
今さら聞けない地域包括ケアシステムのこと ~Vol.6 地域包括ケア会議と歯科衛生士~
Vol.6:「地域ケア個別会議と歯科衛生士」 超高齢社会に…
Vol.6:「地域ケア個別会議と歯科衛生士」 超高齢社会に…
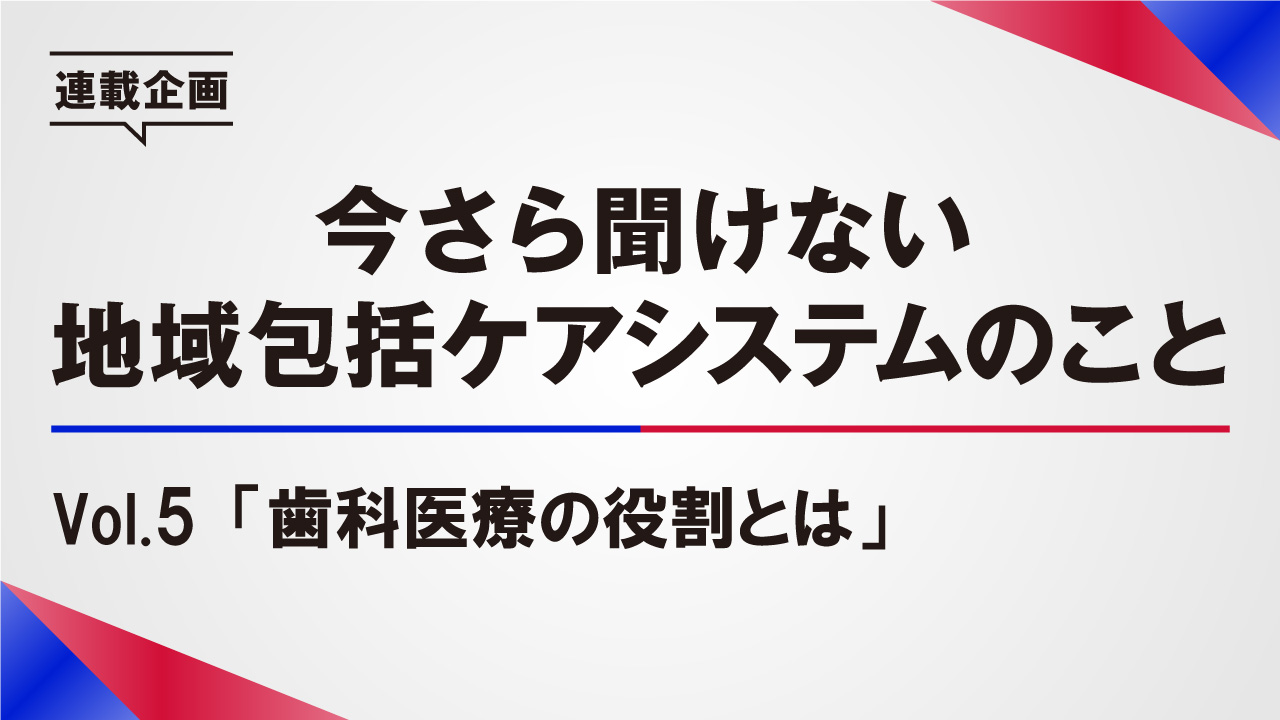
今さら聞けない地域包括ケアシステムのこと ~Vol.5 歯科医療の役割とは~
Vol.5:「歯科医療の役割とは」 超高齢社会において、医…
Vol.5:「歯科医療の役割とは」 超高齢社会において、医…
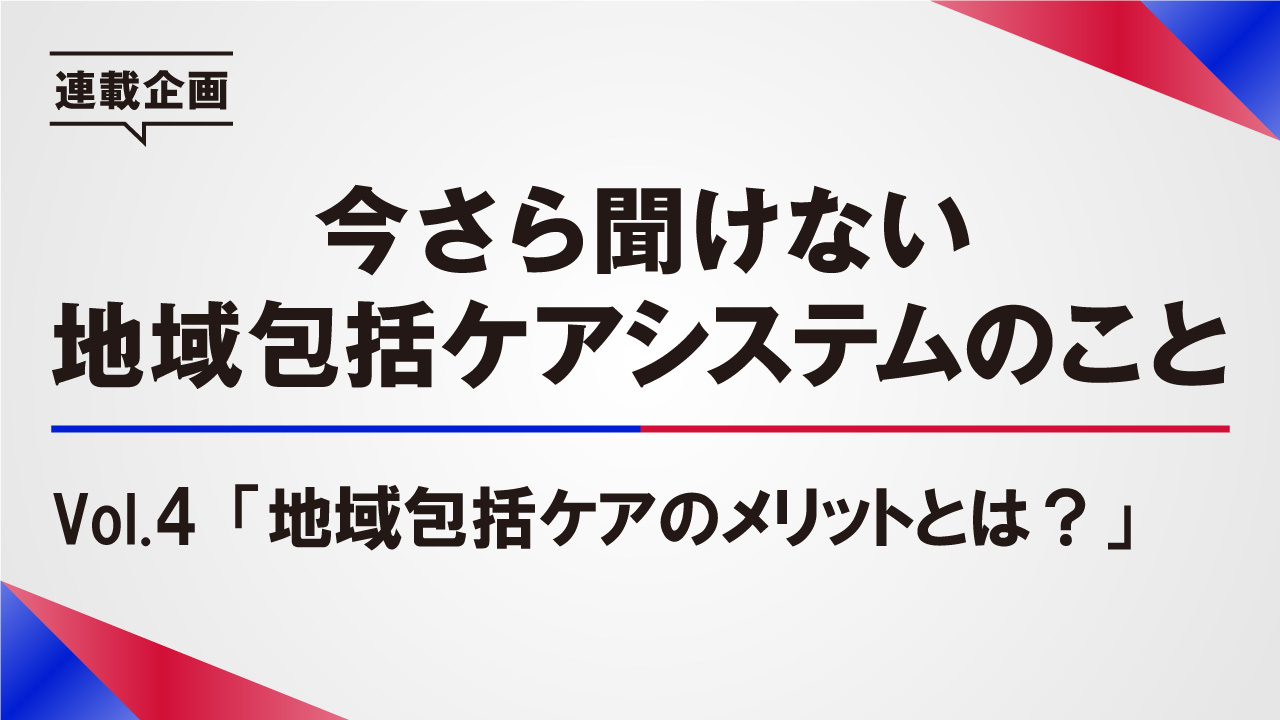
今さら聞けない地域包括ケアシステムのこと ~Vol.4 地域包括ケアのメリットとは?~
Vol.4:「地域包括ケアのメリットとは?」 超高齢社会に…
Vol.4:「地域包括ケアのメリットとは?」 超高齢社会に…
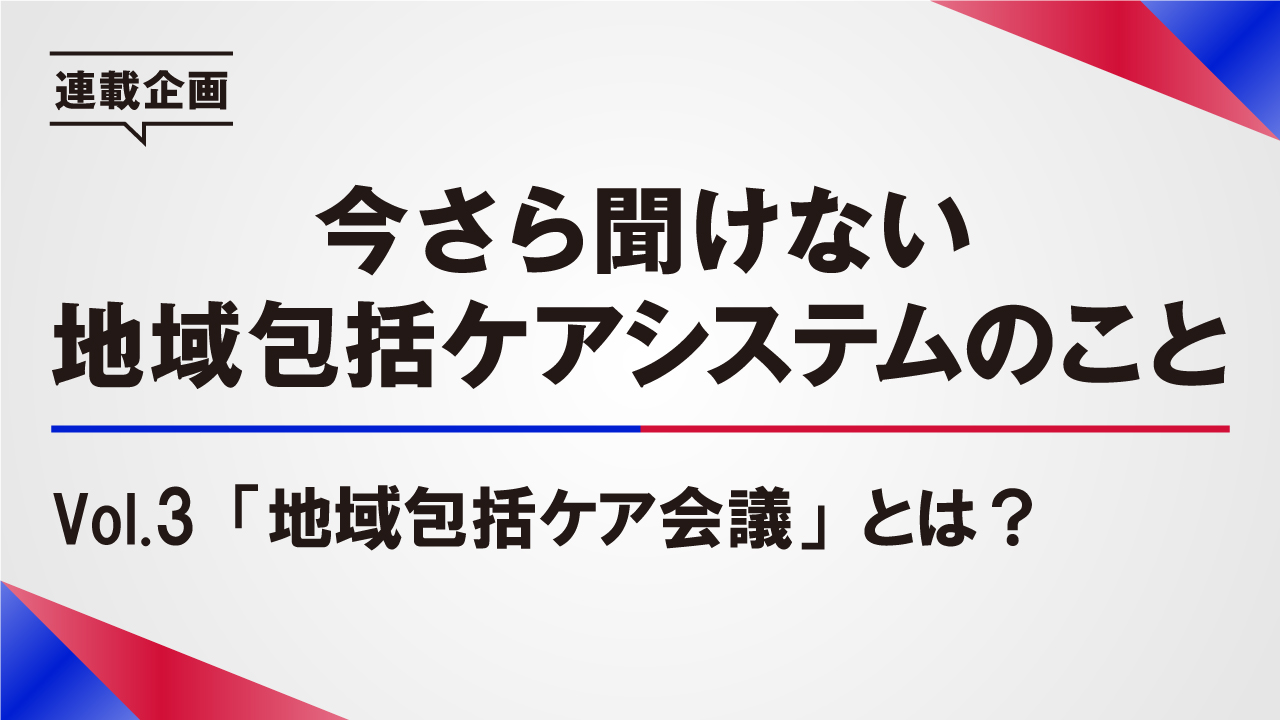
今さら聞けない地域包括ケアシステムのこと ~Vol.3 地域包括ケア会議とは?~
Vol.3:「地域包括ケア会議とは?」 超高齢社会において…
Vol.3:「地域包括ケア会議とは?」 超高齢社会において…
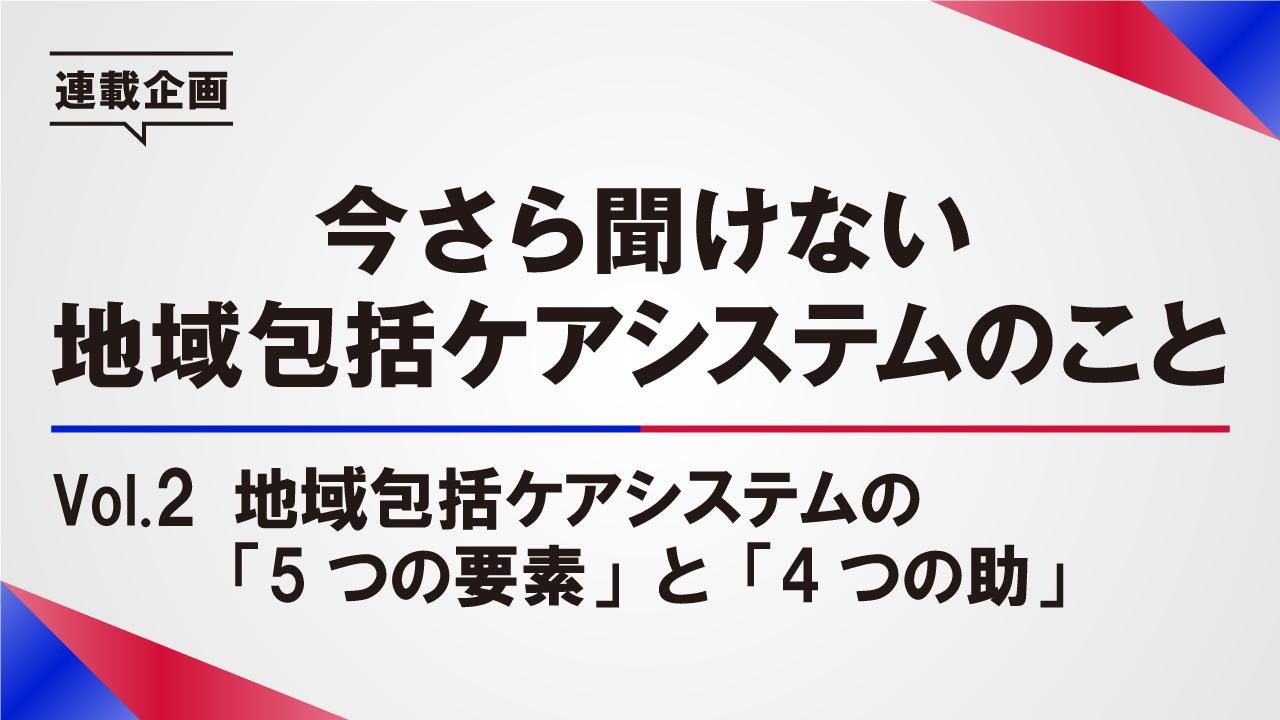
今さら聞けない地域包括ケアシステムのこと ~Vol.2 地域包括ケアシステムの5つの要素と4つの助~
Vol.2 地域包括ケアシステムの5つの要素と4つの助 超…
Vol.2 地域包括ケアシステムの5つの要素と4つの助 超…
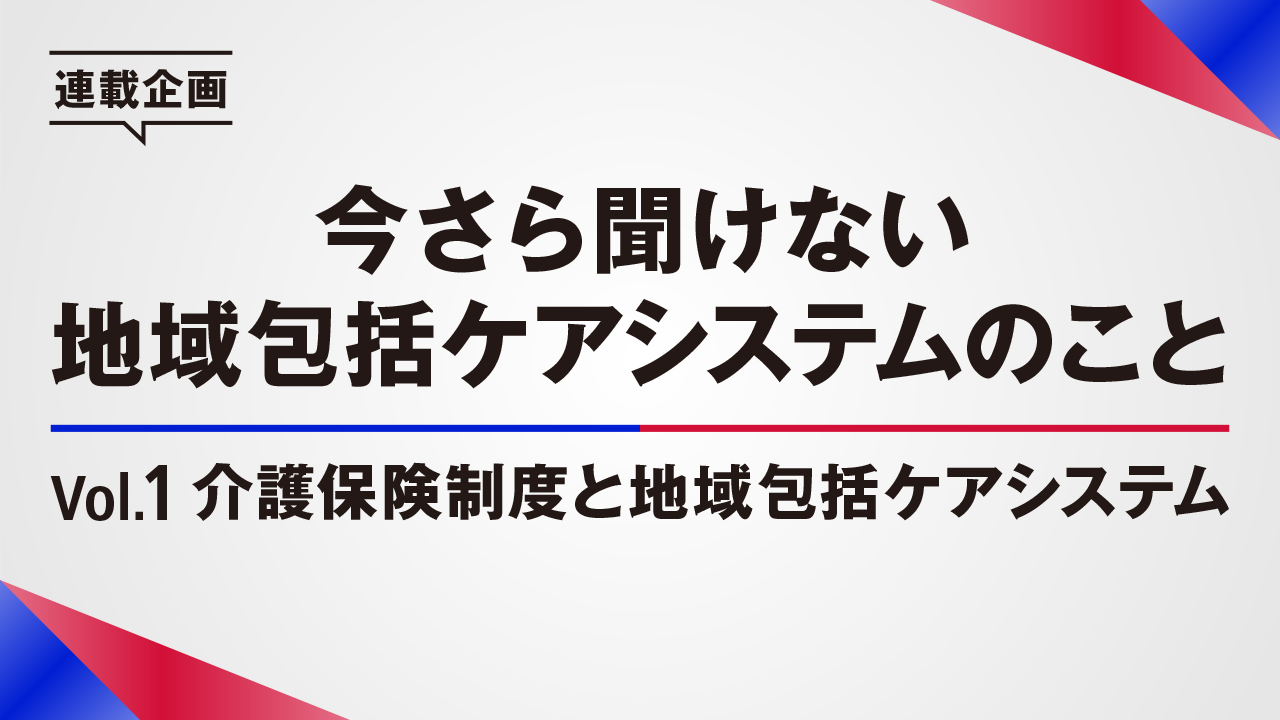
今さら聞けない地域包括ケアシステムのこと ~Vol.1 介護保険制度と地域包括ケアシステム~
Vol.1 介護保険制度と地域包括ケアシステム 超高齢社会…
Vol.1 介護保険制度と地域包括ケアシステム 超高齢社会…

【解説】歯科オンライン診療 スタートアップガイド(第2回)
<解説者>歯科医師 長縄拓哉 先生 歯科医師(医学博士) デ…
<解説者>歯科医師 長縄拓哉 先生 歯科医師(医学博士) デ…

【解説】歯科オンライン診療 スタートアップガイド(第1回)
<解説者>歯科医師 長縄拓哉 先生 歯科医師(医学博士) デ…
<解説者>歯科医師 長縄拓哉 先生 歯科医師(医学博士) デ…