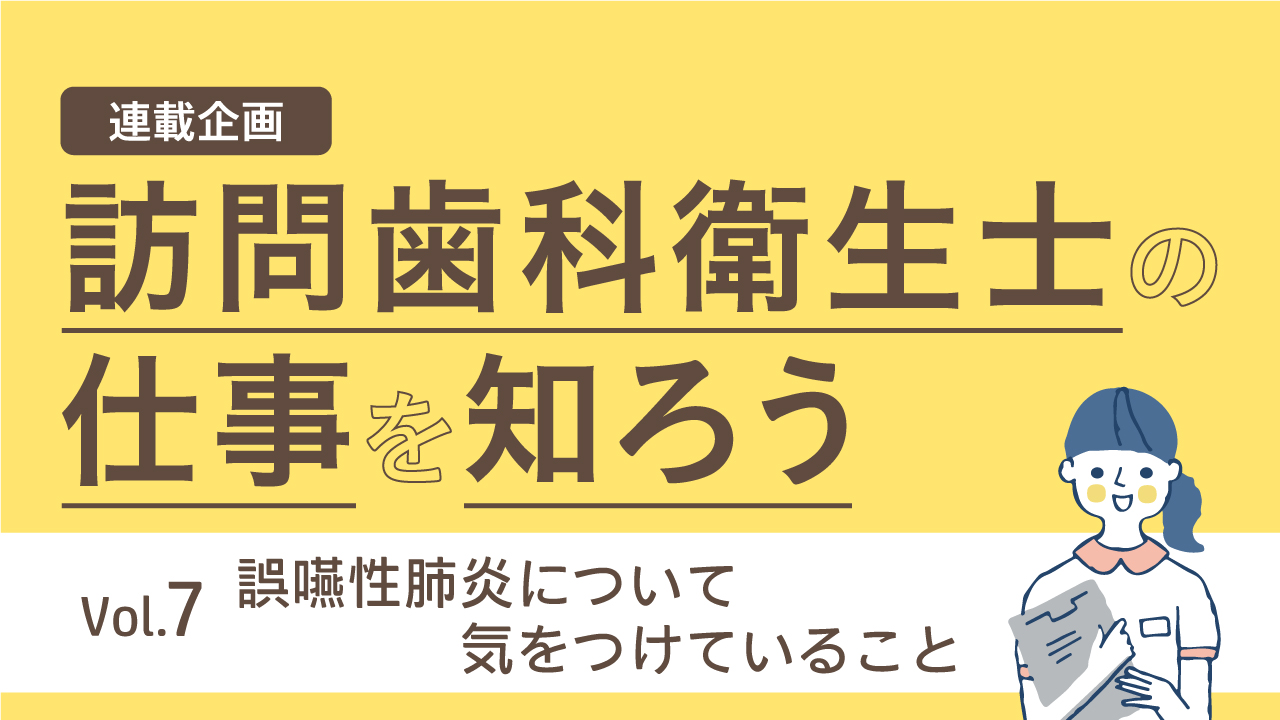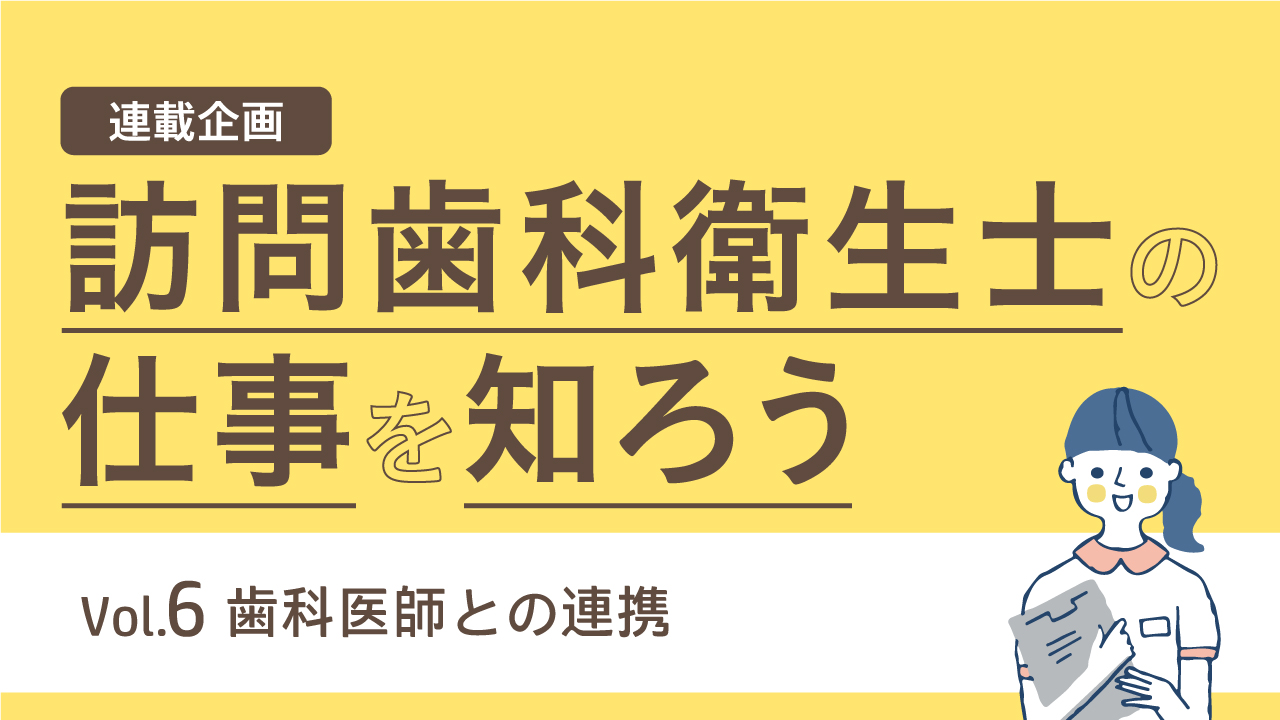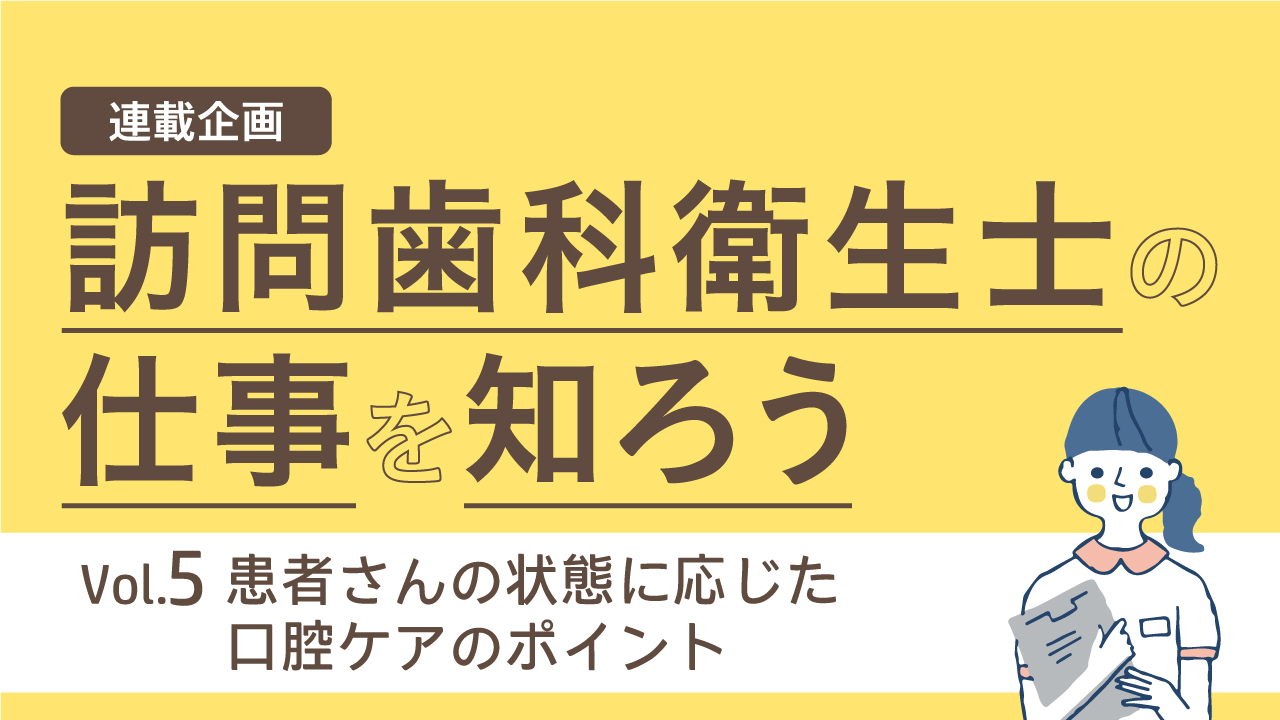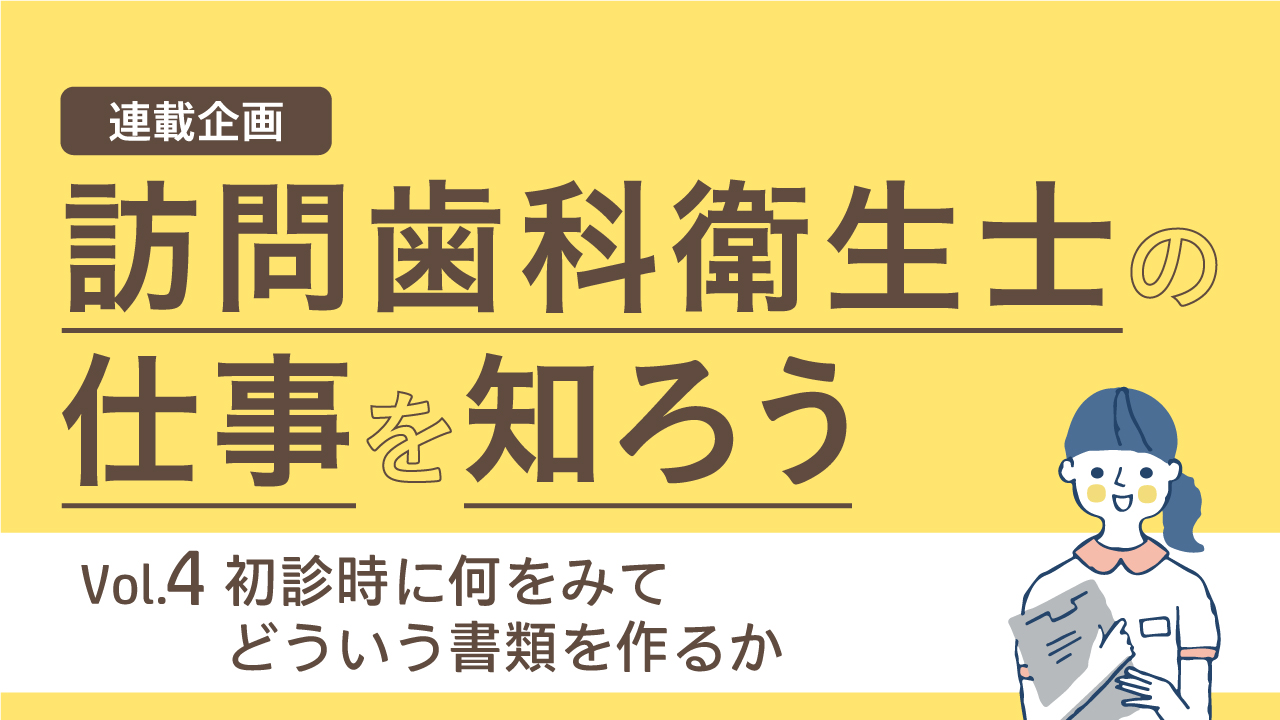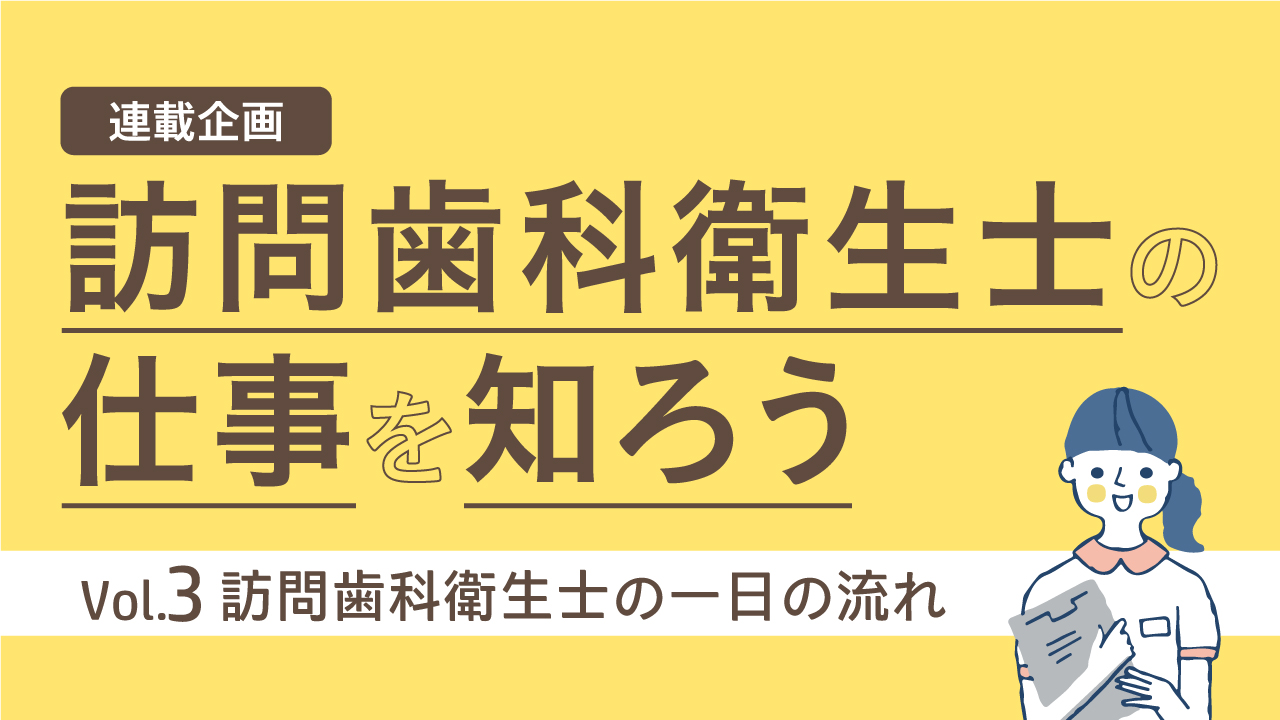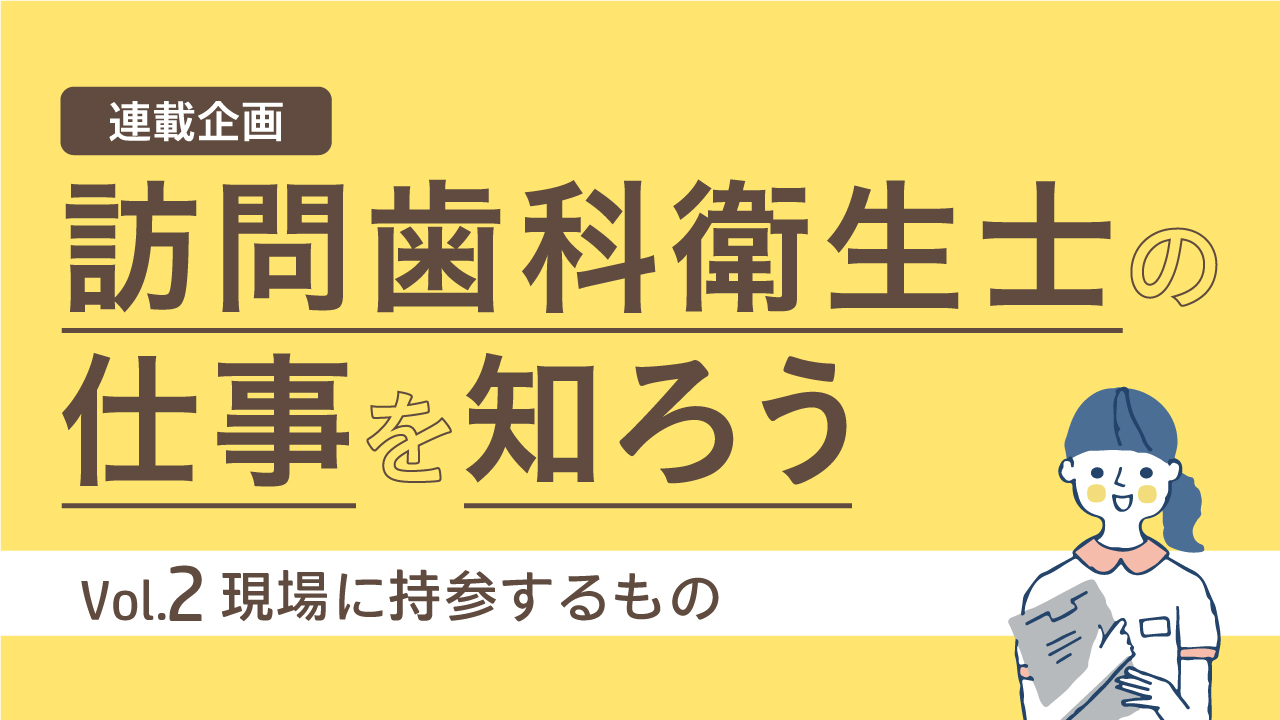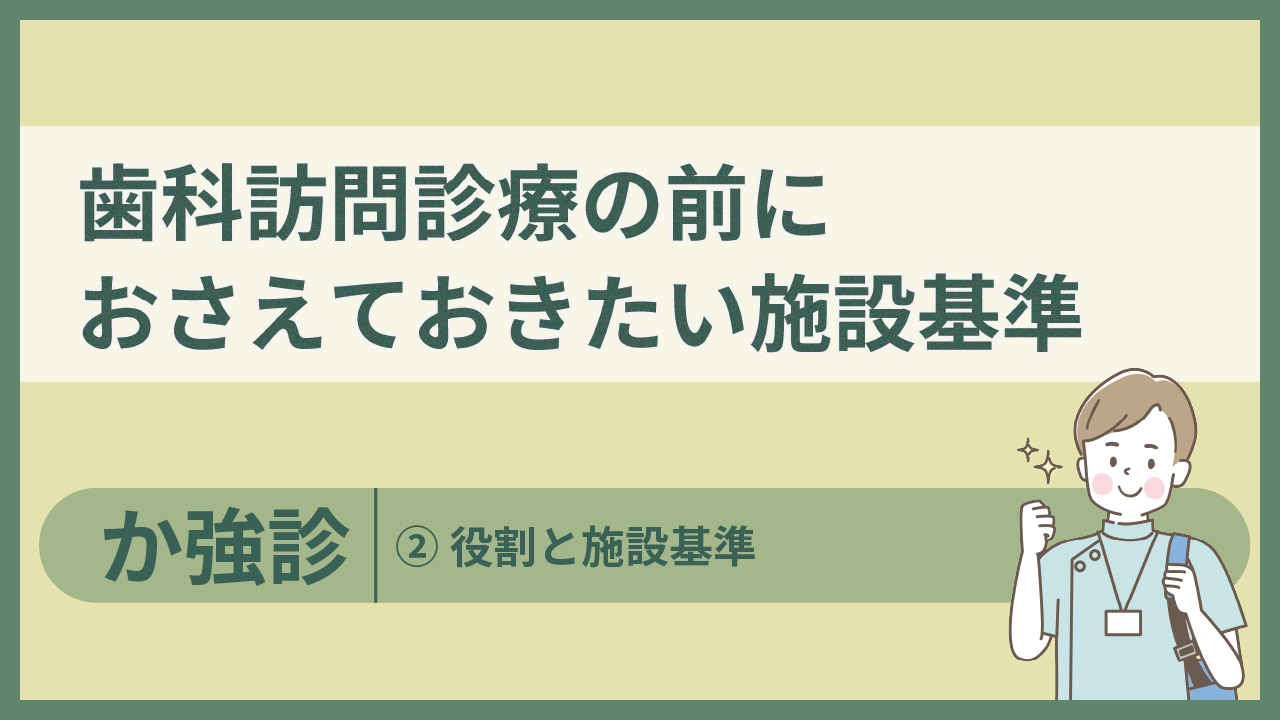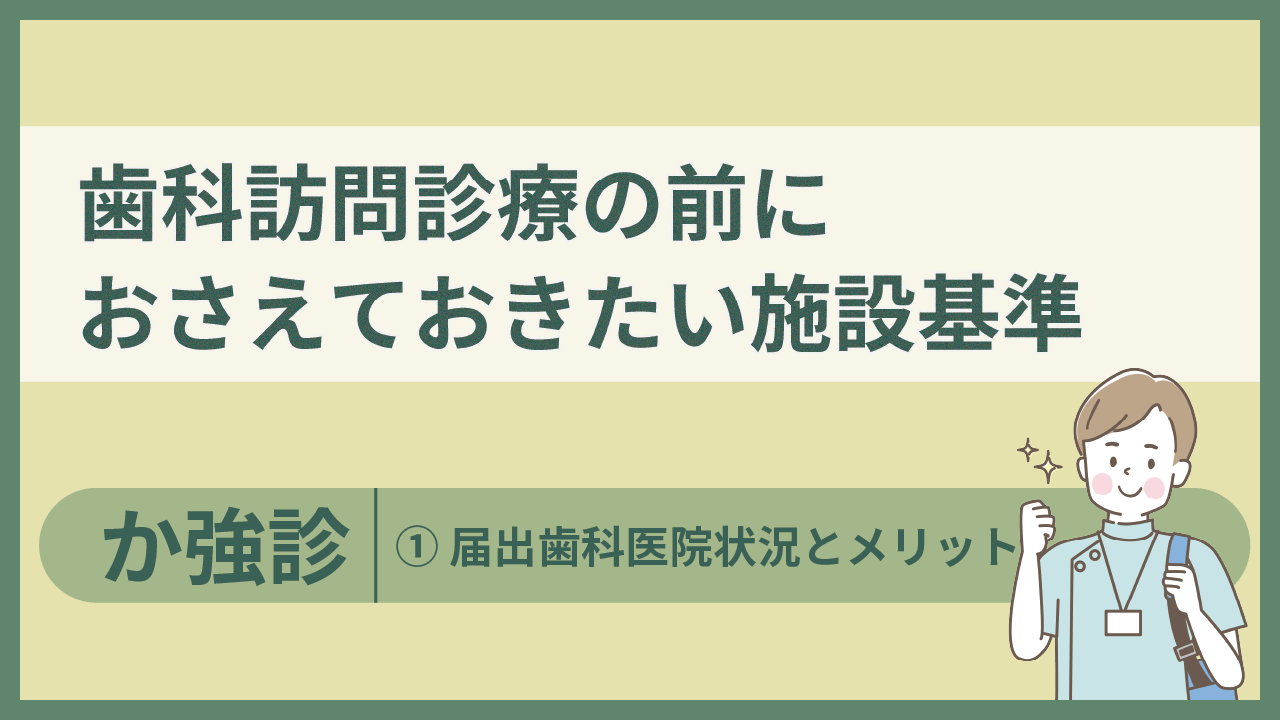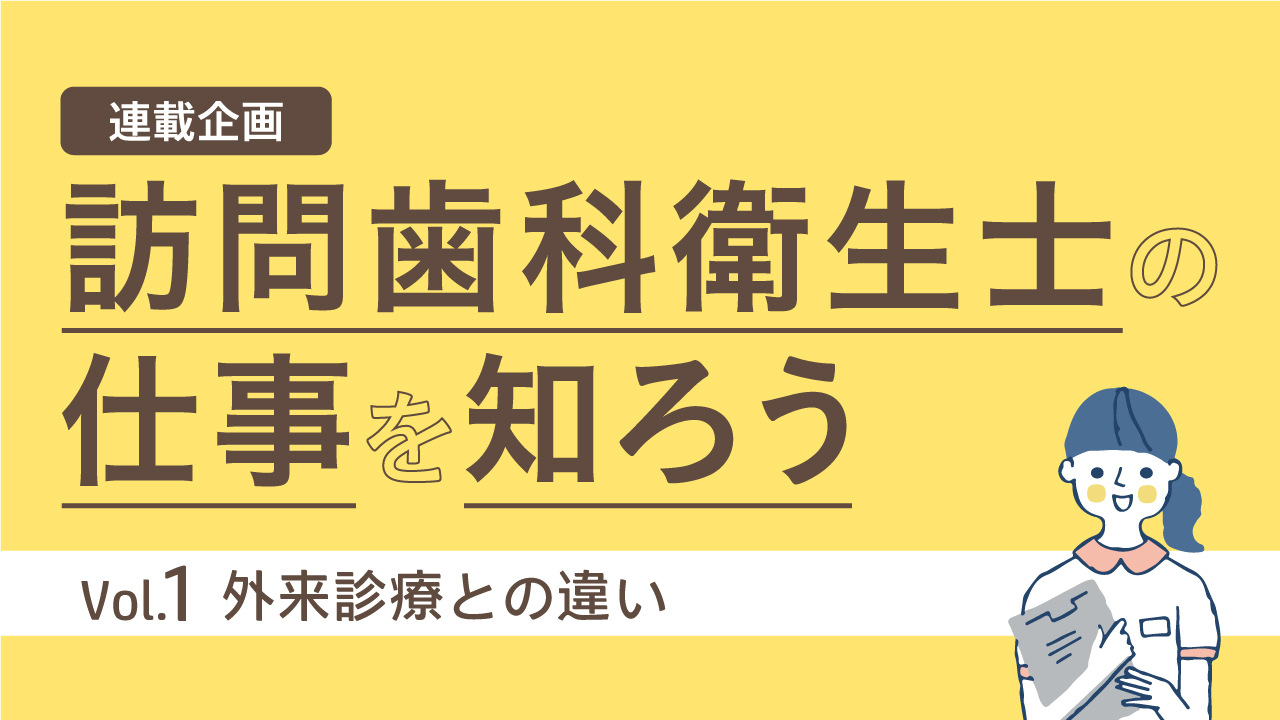今さら聞けない地域包括ケアシステムのこと ~Vol.2 地域包括ケアシステムの5つの要素と4つの助~
特集
2023/06/07
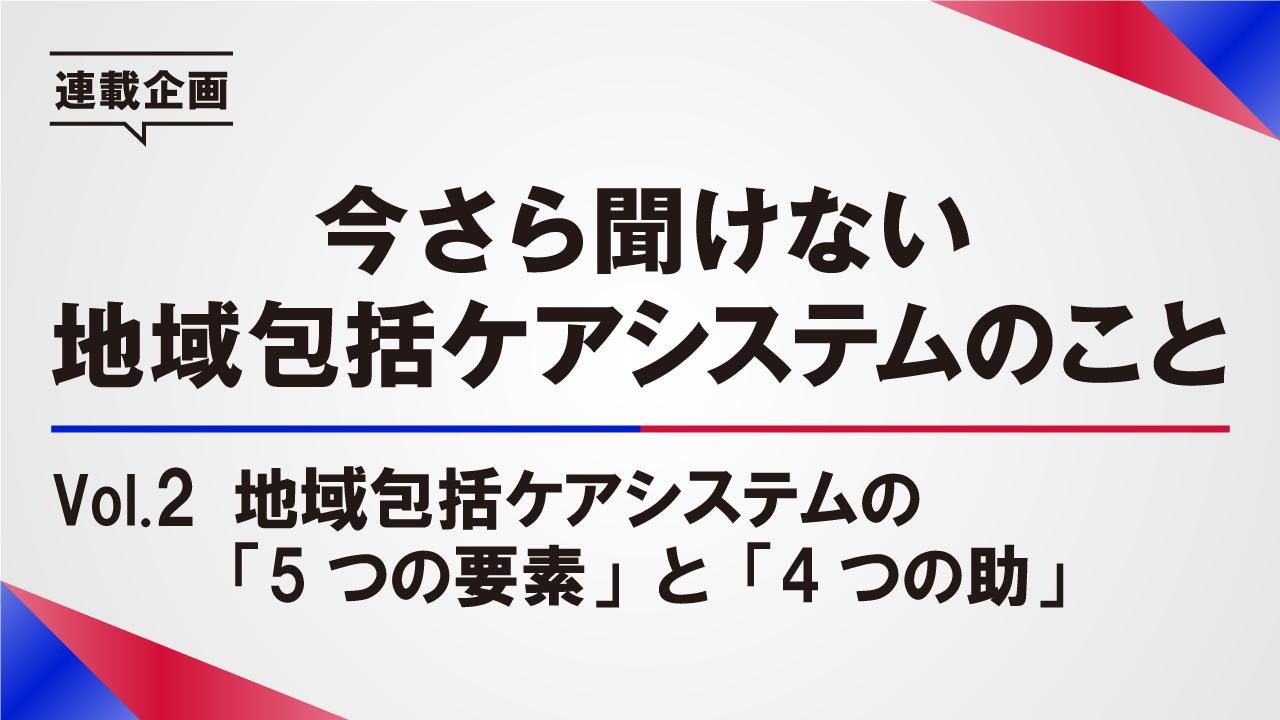
Vol.2 地域包括ケアシステムの5つの要素と4つの助
超高齢社会において、医療や介護のニーズはますます増えることが予想されています。そのような中、我が国では「地域包括ケアシステム」の構築が推進されています。「地域包括ケアシステム」って一体どのようなものなのでしょうか?なんとなく理解しているつもりだけど、詳しくは知らない・・・。そんな方も多いのではないでしょうか。 この連載記事では、「地域包括ケアシステム」の重要な担い手でもある医療従事者のみなさまに、「地域包括ケアシステム」に関する基本情報を配信してまいります。
「5つの要素」を一体的に提供できるケア体制
地域包括ケアシステムは、高齢者が、介護が必要になった場合も、自宅や住み慣れた地域で可能な限り最後まで安心して日常生活を送れるようなサービスを提供する仕組みです。地域包括ケアシステムでは、全国一律のサービスを提供するのではなく、地域の実情に合わせて医療や介護などのサービスが一体的に提供されています。地域包括ケアシステムは「住まい」「医療」「介護」「生活支援」「介護予防」の5つの要素によって構成されています。これらの5つのサービスが包括的に提供されることで、地域包括ケアシステムが実現します。
◆住まい
「住まい」とは高齢者が生活を送る場所のことで、自宅やサービス付き高齢者向け住宅などを指しています。住まいの提供だけでなく、賃貸住宅への入居時の保証人確保、手続きのサポートなど、高齢者が住まいを確保するための支援全般が含まれています...
続きを読むには会員登録(無料)が必要です
この記事の関連記事
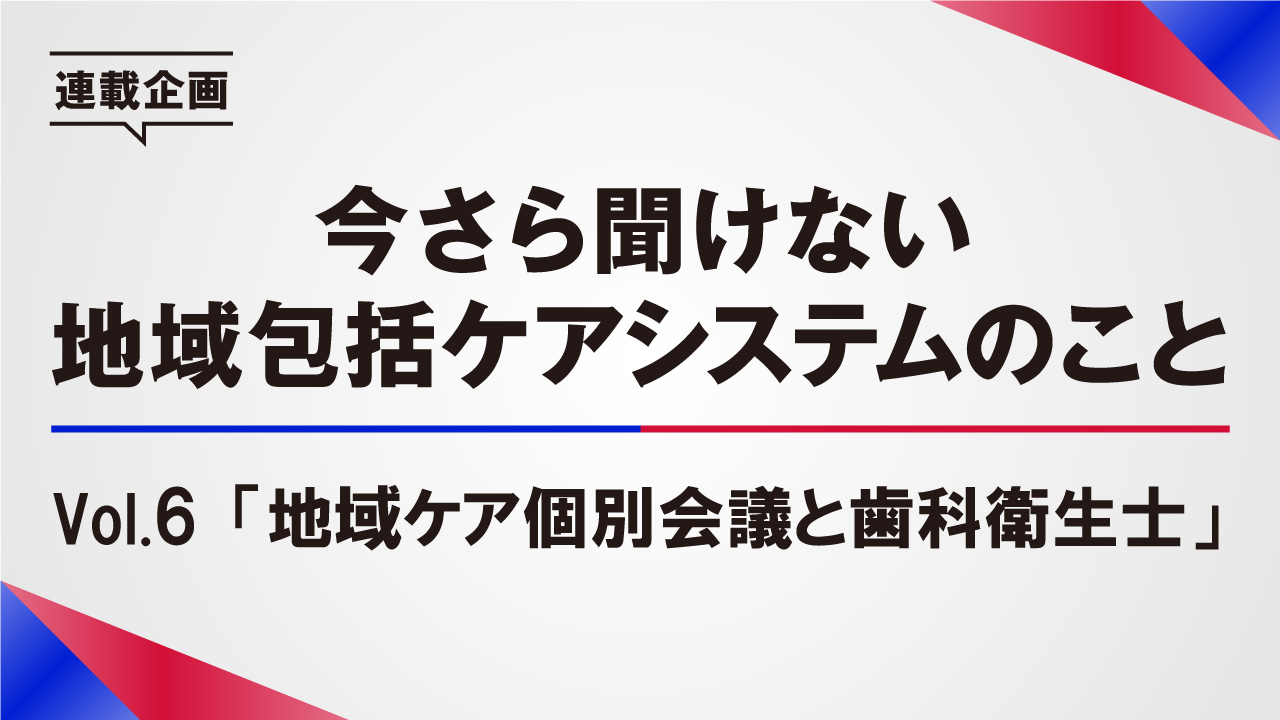
今さら聞けない地域包括ケアシステムのこと ~Vol.6 地域包括ケア会議と歯科衛生士~
Vol.6:「地域ケア個別会議と歯科衛生士」 超高齢社会に…
Vol.6:「地域ケア個別会議と歯科衛生士」 超高齢社会に…
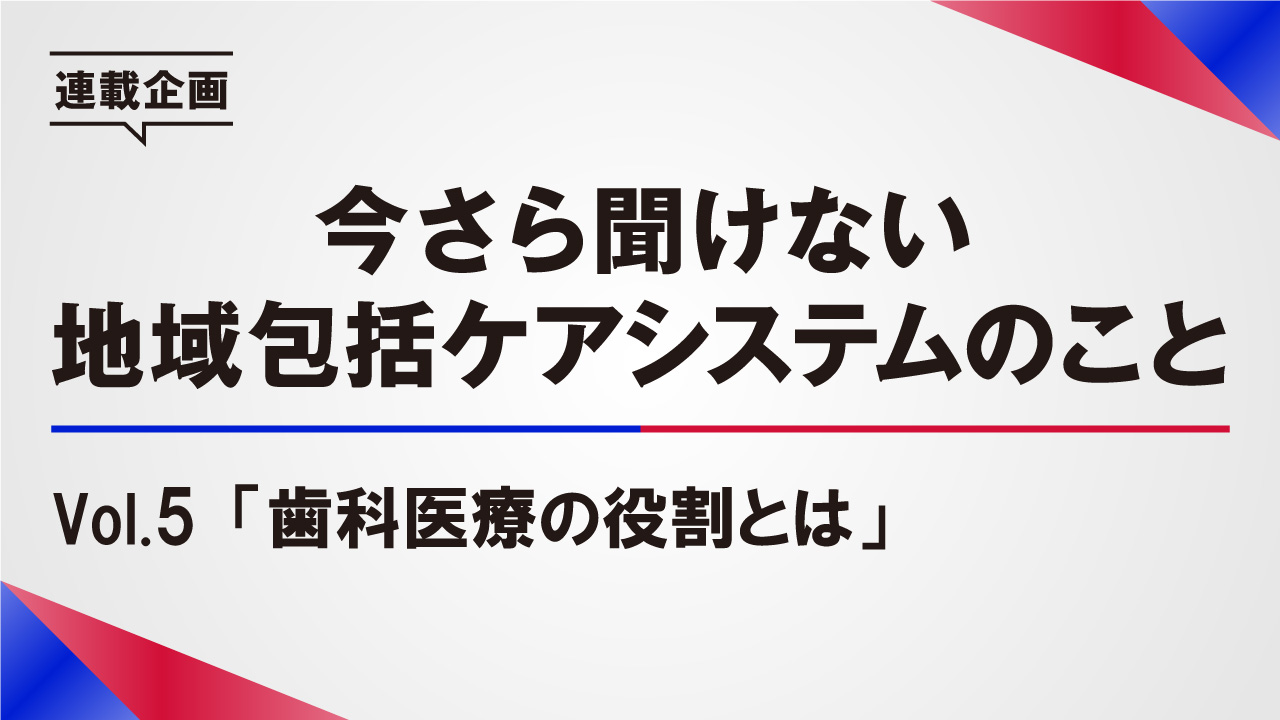
今さら聞けない地域包括ケアシステムのこと ~Vol.5 歯科医療の役割とは~
Vol.5:「歯科医療の役割とは」 超高齢社会において、医…
Vol.5:「歯科医療の役割とは」 超高齢社会において、医…
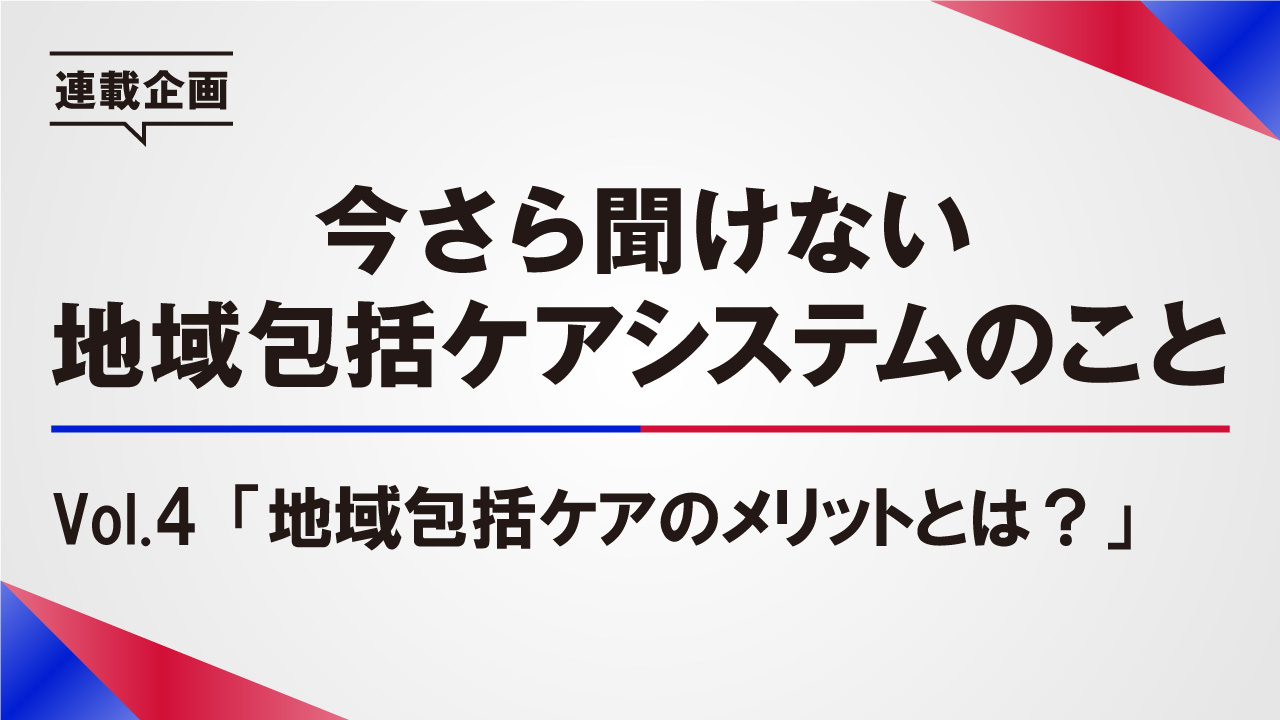
今さら聞けない地域包括ケアシステムのこと ~Vol.4 地域包括ケアのメリットとは?~
Vol.4:「地域包括ケアのメリットとは?」 超高齢社会に…
Vol.4:「地域包括ケアのメリットとは?」 超高齢社会に…
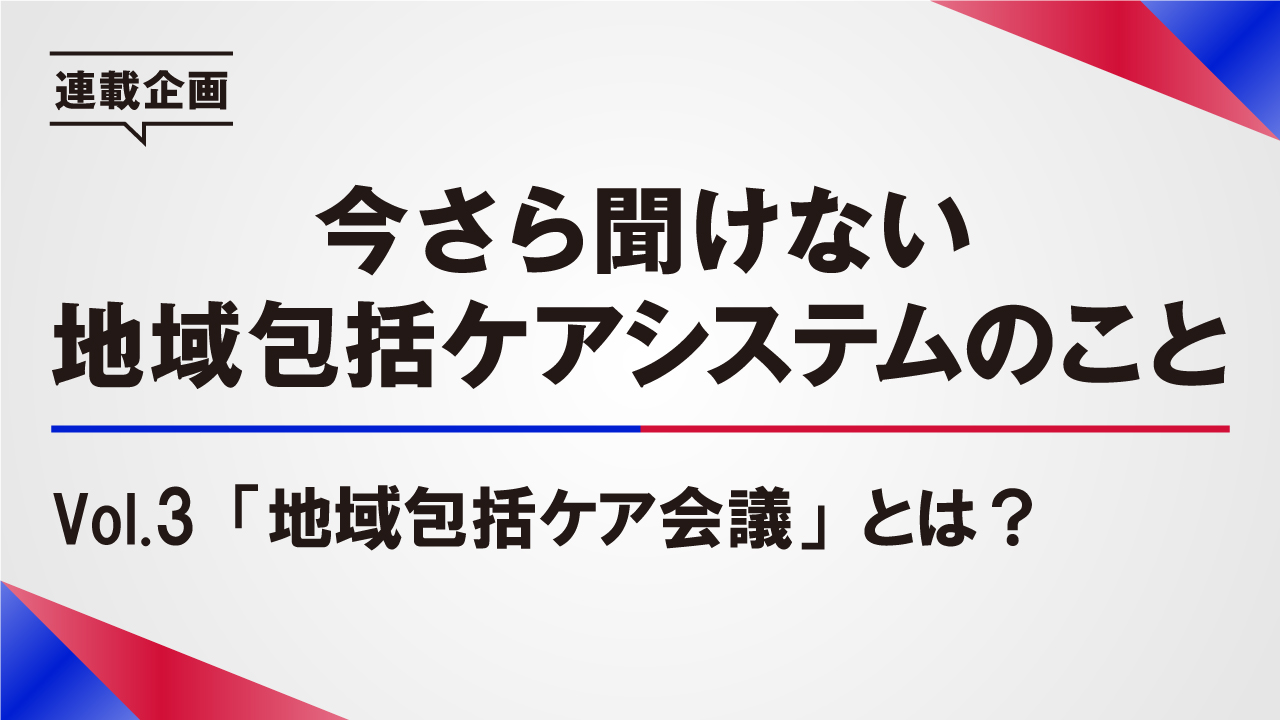
今さら聞けない地域包括ケアシステムのこと ~Vol.3 地域包括ケア会議とは?~
Vol.3:「地域包括ケア会議とは?」 超高齢社会において…
Vol.3:「地域包括ケア会議とは?」 超高齢社会において…
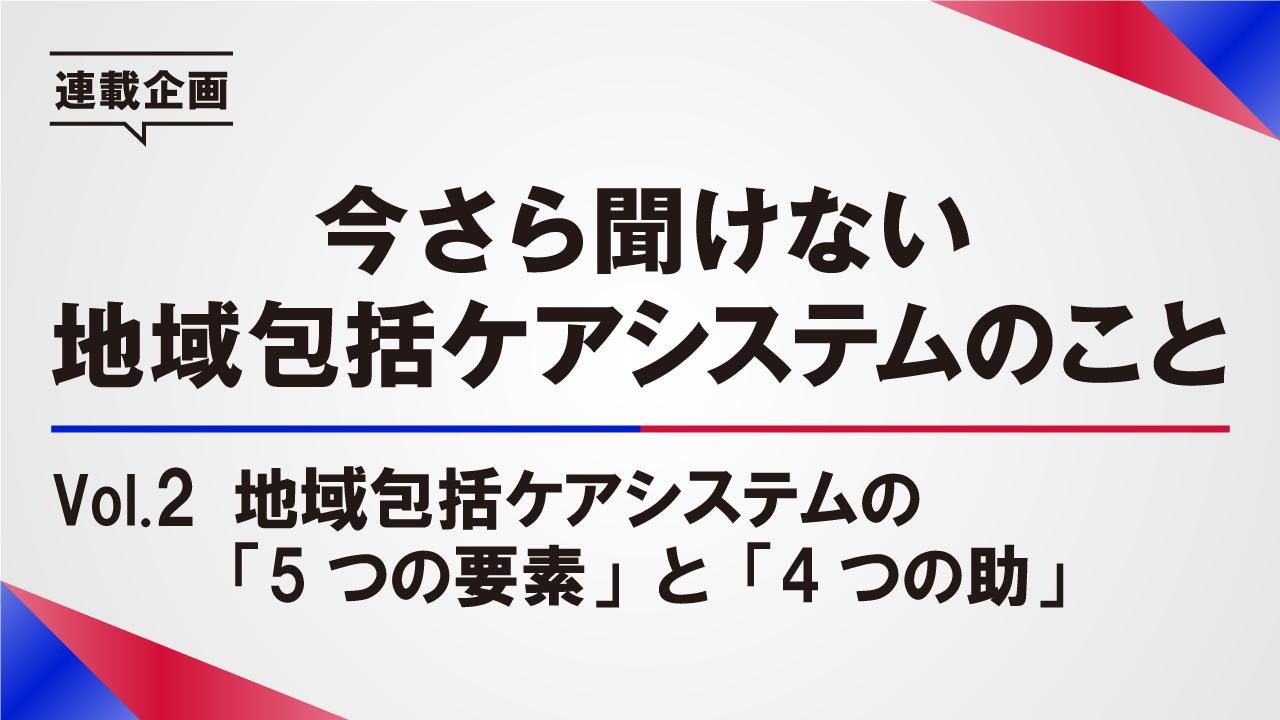
今さら聞けない地域包括ケアシステムのこと ~Vol.2 地域包括ケアシステムの5つの要素と4つの助~
Vol.2 地域包括ケアシステムの5つの要素と4つの助 超…
Vol.2 地域包括ケアシステムの5つの要素と4つの助 超…
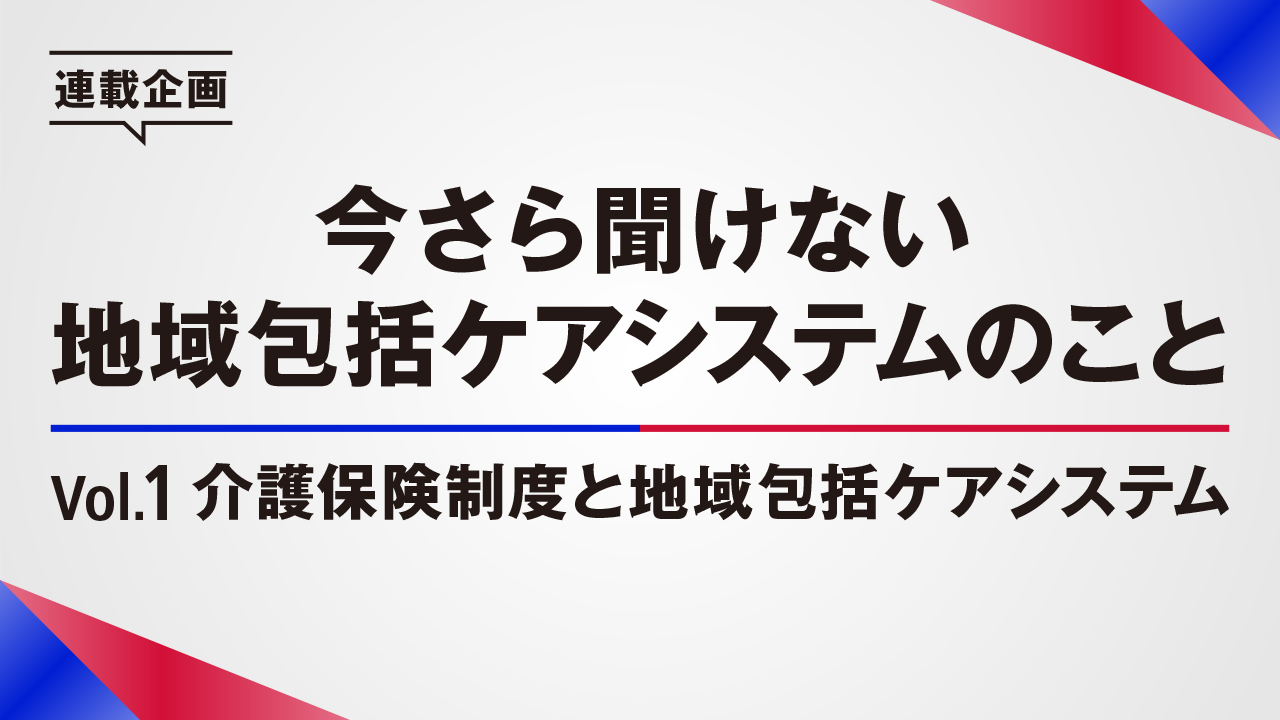
今さら聞けない地域包括ケアシステムのこと ~Vol.1 介護保険制度と地域包括ケアシステム~
Vol.1 介護保険制度と地域包括ケアシステム 超高齢社会…
Vol.1 介護保険制度と地域包括ケアシステム 超高齢社会…

【解説】歯科オンライン診療 スタートアップガイド(第2回)
<解説者>歯科医師 長縄拓哉 先生 歯科医師(医学博士) デ…
<解説者>歯科医師 長縄拓哉 先生 歯科医師(医学博士) デ…

【解説】歯科オンライン診療 スタートアップガイド(第1回)
<解説者>歯科医師 長縄拓哉 先生 歯科医師(医学博士) デ…
<解説者>歯科医師 長縄拓哉 先生 歯科医師(医学博士) デ…